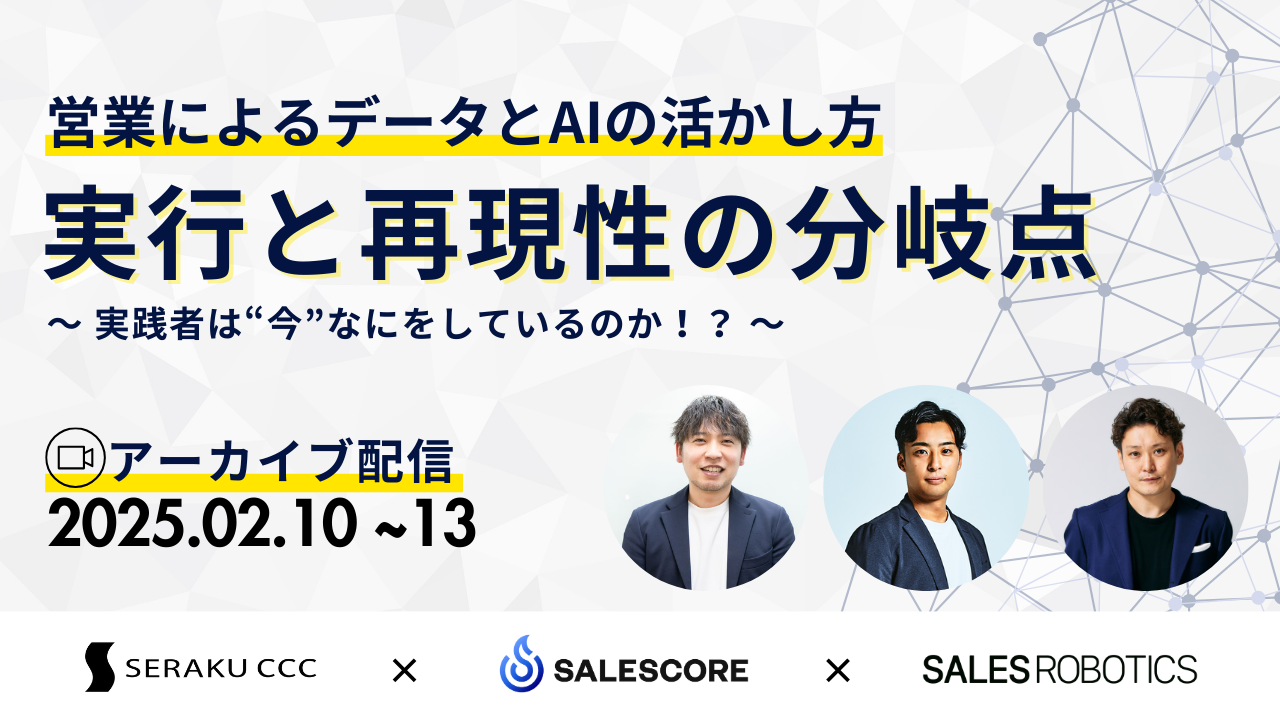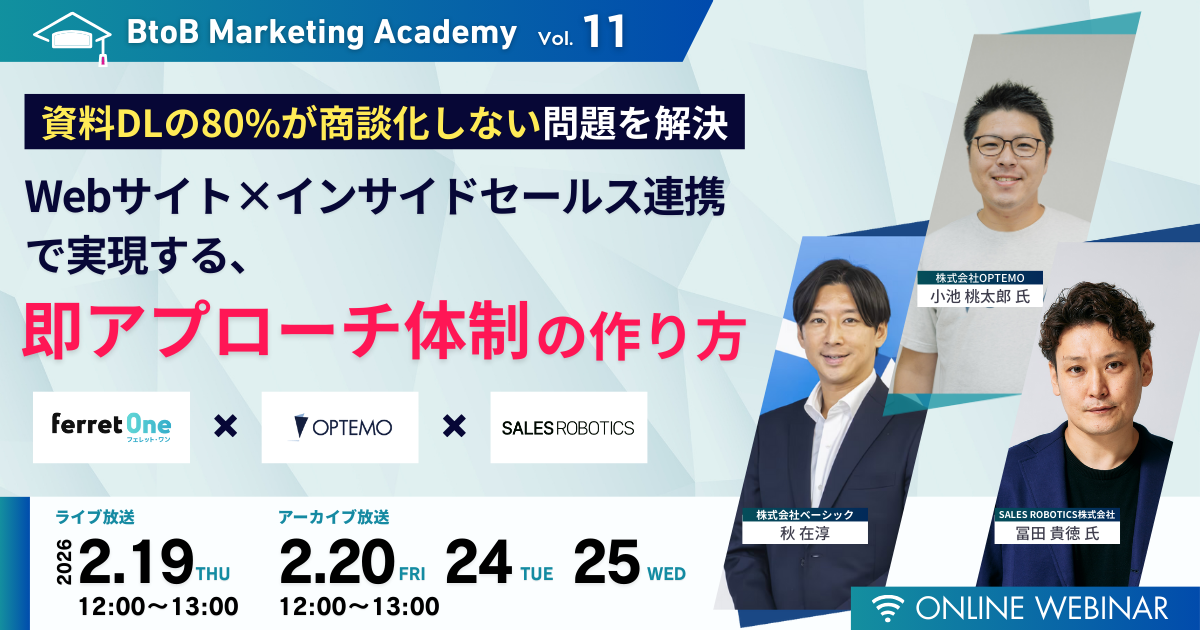【後編】お客様の期待に、一途に向き合う #THELEADERS特別編

現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳が取材する連載企画「THE LEADERS」。特別企画である今回は、インサイドセールスを支援する「BPOの現在地」を題材に、業界を代表するリーダーが本音で語り合います。
前編は「BPOの定義」と「BPOでよくある失敗」についてそれぞれの意見を出し合い、BPO事業者と発注業者とのあるべき関係性などを模索しました。後編ではさらに一歩踏み込んで、BPO事業者に今後求められる能力や、起こすべき変化について意見を出し合いました。
前編はこちら
(執筆:サトートモロー 撮影・映像編集:シンフォニティ株式会社)
向井 俊介
ウェルディレクション合同会社 代表社員
約20年、主に外資ITの業界において中小から大企業のB2Bの営業領域の職務に従事。 グローバルNo.1のセールスやマネージャーに複数回選出されるなど、常に卓越した成果を創出。2020年7月にウェルディレクションを創業し、業種・規模を問わず、組織が自律的に成長し続ける「自走型営業組織とプロセスの構築」を支援。
阿部 慎平
スマートキャンプ株式会社 取締役執行役員COO
2017年3月にスマートキャンプへ入社し、取締役執行役員COOとして事業戦略、組織戦略、新規事業戦略の策定、『SaaS業界レポート』の執筆、インサイドセールス代行サービス「BALES」の立ち上げを担う。新規事業としてオンライン展示会「BOXIL EXPO」やセールスエンゲージメントツール「BALES CLOUD」を生み出し、事業の成長を牽引。
原 秀一
株式会社セールスリクエスト 代表取締役
2015年弁護士ドットコムにて集客メディア営業・インサイドセールス立ち上げに従事。2019年、スマートキャンプにて営業・営業企画・Bales営業を経て、スタートアップ企業の成長に特化した株式会社セールスリクエストを設立。 2024年書籍「インサイドセールス 実践の教科書 立ち上げから組織づくり、事業成長まで」を株式会社才流と共著にて出版(翔泳社)。
山梨 寛弥
株式会社Maroo 代表取締役
株式会社ZUUにて、20ジャンル以上のオウンドメディアにおけるグロースマーケティングを担当。グローバルIT企業で数百社の営業・マーケティング戦略や顧客エンゲージメントのシナリオ構築を支援した後、2021年に株式会社Marooを設立。顧客の事業成長を支援する統合型インサイドセールスDXサービス「インサイドセールスエンジニアリング」を提供。
冨田 貴徳
SALES ROBOTICS株式会社 取締役
SaaS事業責任者や複数の新規事業立ち上げを経験し、2021年にSALES ROBOTICSにてCMOに着任、2023年より現職。 マーケティング組織立ち上げ、リブランディング、ISサービス拡大、CSBPOサービスを新規開発。セールスフォースユーザー会、『インサイドセールス分科会』2023年度の会長を務め、インサイドセールスカンファレンス2024の復活にも寄与。
お客様の成果=売上に向き合うこと
向井:
3つ目のテーマは「(BPO)ベンダーに必要な変化はなにか?」です。まずは原さん、フリップを上げてください。
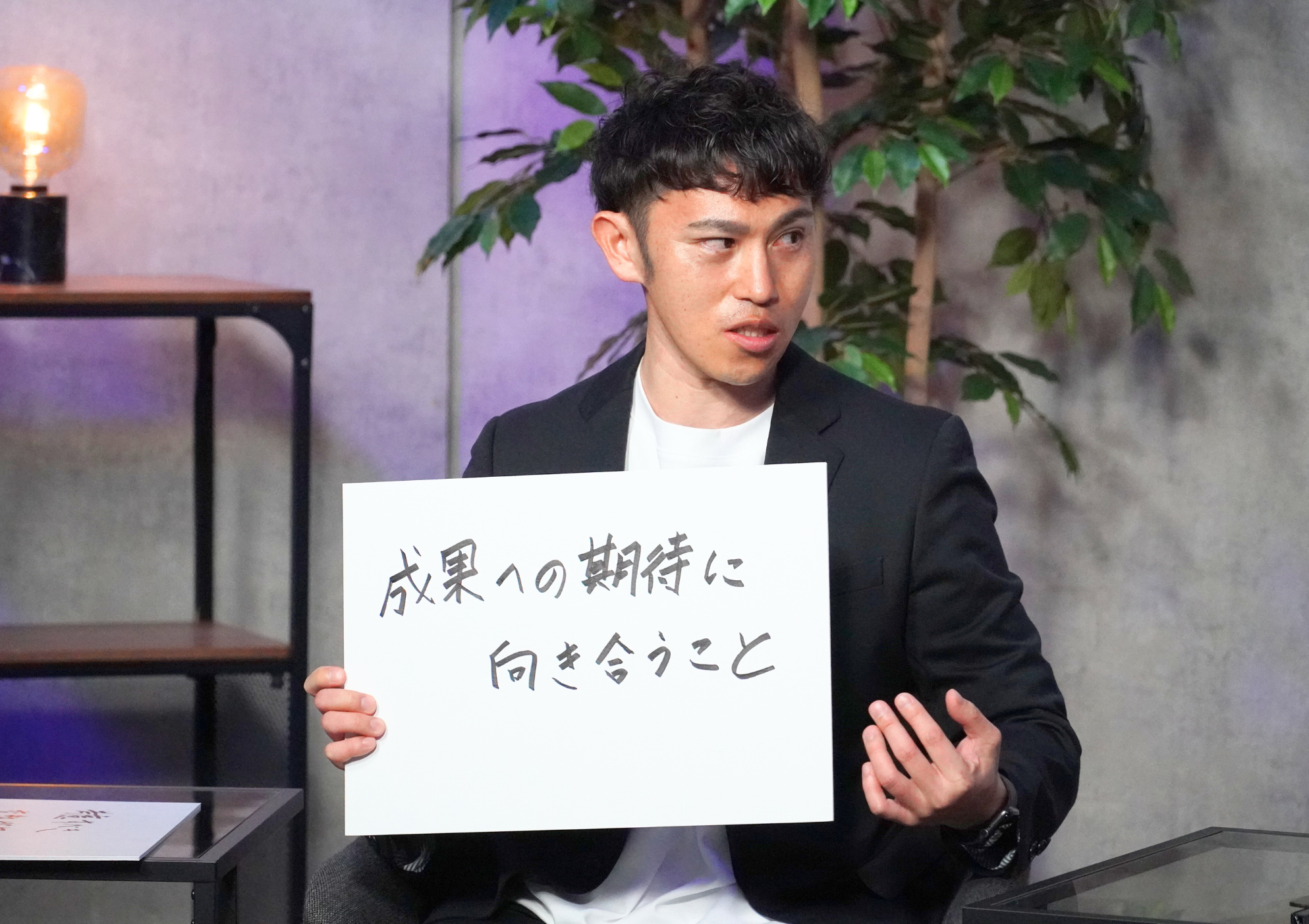
原:
私は「成果への期待に向き合うこと」と書きました。これは変化というよりも、私たちBPO事業者側が持つべきマインドだと言えます。
お客様にご発注いただいたということは、私たちの提案に納得いただいたということ。だからこそ、どのようなフェーズのプロジェクトであれ成果と向き合っていく姿勢が大事ではないでしょうか。
向井:
私は原さんとも何度かお仕事でご一緒してきましたが、どんなときも成果に向き合っていた印象です。その姿勢があるからこそ、セールスリクエスト社は順調にビジネスを成長させているのでしょう。
そんな原さんがあえてこう発言するということに、業界に対する警告が含まれていると感じました。
原:
弊社への問い合わせで圧倒的に多いのが「リプレイス」です。残念ながら、数字報告だけに留まり、お客様の成果に向けたコミュニケーションを取っていないBPO事業者は、一定数存在します。その事実から、私はこの言葉を書きました。
向井:
なるほど。冨田さんも原さんと同様に、「成果」にフォーカスした言葉をフリップに書いているんですよね。ここでいう成果とは、何を指すのでしょうか?

冨田:
成果とは売上です。
BPO事業者にお問い合わせいただくお客様はさまざまなニーズをお持ちで、プロジェクトによって成果の基準は異なると思います。しかし、最終的に目指すべきはお客様の売上への貢献で、そこを直視することをBPO事業者は忘れてはいけないと思っています。
原:
私も、成果を語る上で売上に直結するかどうかは非常に重要な視点だと思います。
向井:
BPO事業者は、売上という期待に対してどのようなコミュニケーションやビジネスプランニングをするかで議論すべきだと。お客様と商談数やアポイント数といった、局所的な議論を重ねるのは、そもそも考え方としてズレているということですね。
冨田:
綺麗事のように聞こえるかもしれませんが、私たちが目指すものとして「売上」はずらしたくはないと考えています。この言葉には、そんな情熱や熱意といった意味合いを込めました。
阿部:
弊社でも、こちらから積極的にお客様と売上の話をするようにしています。BPOに取り組み始めた頃は商談創出にフォーカスしていましたが、お客様の売上につながらず、解約されてしまうという苦い経験をしました。
これはお客様だけでなく、プロジェクトを頑張ってくれたメンバーにとっても辛いことです。だからこそ、プロジェクト初期の段階で売上について話し合い、その施策に意味があるのかを議論しています。
向井:
展示会でたくさんの名刺を集めて、当日ないしは翌日からBPO事業者に名刺データを渡して、アポイントを獲得してもらう。これはBPOのビジネスモデルのひとつだと思います。
こうした活動のなかで、皆さんが大切にしている「売上に貢献する」という視点でのビジネス設計がないと、悲劇が起こってしまうんですよね。数百万円の予算を使い展示会に出展して見込み顧客を集めたのに、絨毯爆撃のようなコミュニケーションを取った結果、ひとりもお客様を得られないといったように。
冨田:
それを防ぐために、私たち自身もお客様が出展する展示会に参加しています。お客様の社内メンバーの一人として名刺交換をして、見込み顧客の管理をしつつその後の活動につなげていくのです。
単純にリソースを補完するのではなく、より包括的にインサイドセールス活動をデザインすることを大切にしています。
営業領域全体を最適化できる専門家であれ

阿部:
私はフリップに「営業領域における専門性」と書きましたが、インサイドセールスのBPO事業者は営業領域全体の専門性が必要だと最近感じています。
マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス。これらを包括的に捉えて売上を最大化していくという視点を持っていないと、点と点の活動にとどまり売上に貢献できません。
自戒を込めて、BPO事業者は営業利益全体の専門性を高めていくということに、しっかり向き合うべきです。
向井:
THE MODELの考え方のもと、営業の各組織がそれぞれの数字を追いかける状況が是として組織運営が行われてきました。
しかし、アポイント数を担保するためのコールの結果、負の感情が生まれるコミュニケーションが横行しています。結果、フィールドセールスが頼まれてもいない提案書を作成し、アポイントに臨むという矛盾も生じています。
新興国のように急成長している国ならまだしも、労働生産人口が減り企業の絶対数も減るであろう日本において、現状のコミュニケーションは負の要素しかありません。多くの事業者が、アポイント獲得率を1.5%から2%に引き上げるための議論を重ねています。しかし、そもそも98.5%のお客様に嫌われているという事実に目を向けないといけません。
この状況を打開するためにも、BPO事業者側が売上に重心を置いてコミュニケーションを取るべきという認識を、業界全体に広げていきたいですね。
阿部:
向井さんの言うとおり、98%のお客様とのコミュニケーションを資産につなげるアプローチができなければ、業界全体が疲弊してしまうと思います。
向井:
この流れで、山梨さんの意見もぜひ聞かせてください。
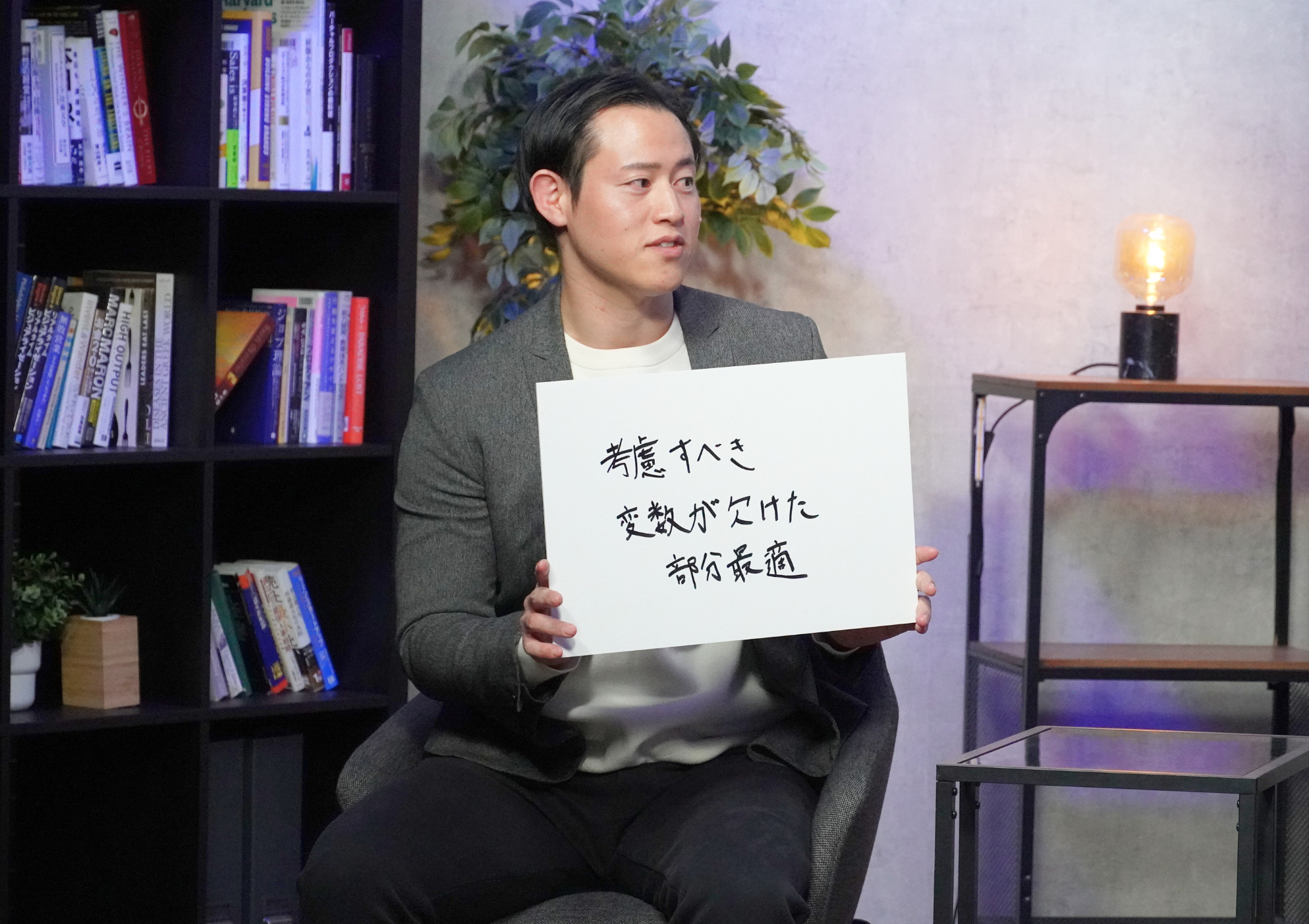
山梨:
私が提言したいのは「考慮すべき変数が欠けた部分最適をやめる」です。
阿部さんと同様に、レベニュープロセスを見て全体最適で考えていくことがBPO事業者には必要だと思います。
事業成長や顧客の売上拡大を起点に、ボトルネックと成長のドライバーを明確に見極めてリソースを投下する。BPO事業者側は、この領域を一定数コントロールできる存在であるべきだと思います。
「展示会で手に入った名刺にコールしてほしい」という依頼を受けたとき、それが受注につながるかのかをお客様と協議できる。
施策を否定するのではなく、どこにリソースを投じれば成果が出るのかも提案できる。
こうしたアクションを取れることが、BPOの介在価値になるのではないでしょうか。
冨田:
とはいえ、BPO事業者にどこまで相談・依頼していいかわからないお客様は多いと思うんです。どのように、リソースの配分などについて話し合うタイミングを設けていますか?
山梨:
私たちの場合、お問い合わせいただいたタイミングや最初の接点でお伝えしています。それに、弊社のお客様はBPO事業者といろいろ話し合うマインドをお持ちの方が多いです。
なぜかというと、弊社から対外的な情報発信を定期的にしっかり行っているからだと思います。
私はX(旧Twitter)やnoteを通じて、過去のプロジェクトで得られた成功体験やノウハウ・方法論などを発信しています。その内容に共感してくださったお客様が、「Marooに一度相談してみようかな」と考えてくださるんです。
結果、HowではなくWhyを起点にした会話がしやすくなります。
向井:
発信を通じて会社に対する期待値を高めているのですね。
阿部:
私たちも、営業資料を用いて提案・説明する段階で「私たちは戦略を付加価値にしています」と伝えています。なるべく早いタイミングで、期待値を整えておくことは非常に重要だと思っています。
そもそも、「何件のアポイントを獲得できる」と数字の成果で競おうとしても、BPO事業者に大差はありません。数字ベースのカタログスペックに差がない以上、ビジョンや思想、カルチャーを通じて提案することが重要です。担当者を紹介するときも、「〇〇のバックグラウンドを持つため、お客様にきっとマッチします」と案内をします。
冨田:
仲人のような存在ですね。
阿部:
まさしく仲人ですね。最終的な運用を担うのはメンバーですから。
向井:
4人の話は、今後のBPO業界に求められる変化であると感じました。同時に、発注者の方々はBPO事業者に対して、アウトバウンドコール以外も頼る機会を持ってほしいと思います。
テクノロジーで業務のブラックボックスを解き明かしていく
向井:
最後のテーマは、「今後、ビジネスプロセスの領域に必要な変革とは何か」です。最後のパートということで、一斉にフリップを上げてもらおうと思います。準備はいいですか?
それでは、せーの、じゃじゃん!!

向井:
冨田さん、「※BPR→融合」とは具体的にどういうことなんでしょうか?
※BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)
企業活動を見直して利益を最大化する活動のこと。
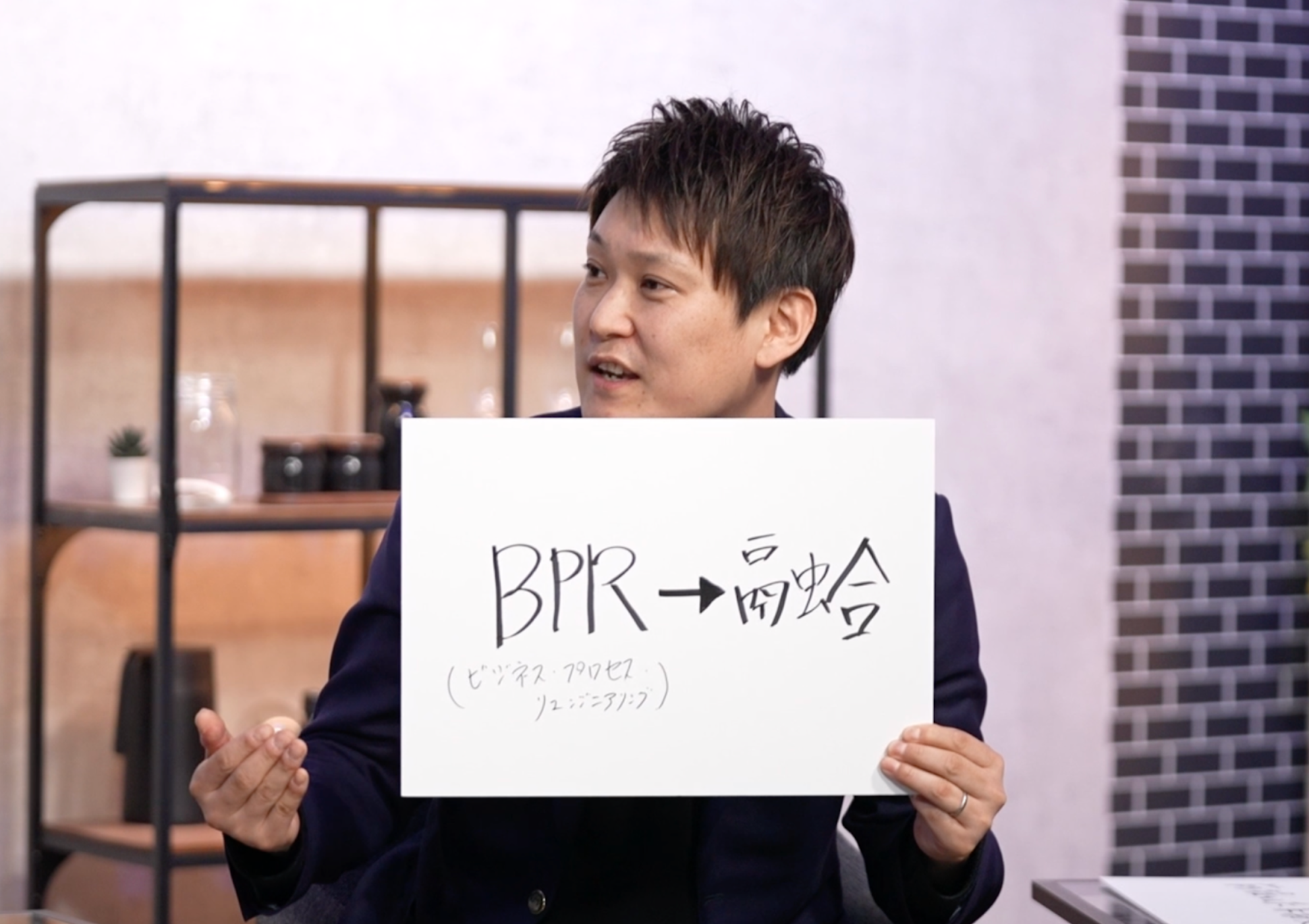
冨田:
BPOでは社内に不足している能力を見極めて、実行力を補完することが必要です。
そして、自社に不足している能力を理解するには、BPRを通じて業務プロセスや人材、能力、データなどの要素を分解することが重要です。非常に大変な作業ではありますが、BPO事業者はBPRの視点を持って提案・実行すべきだと思います。
現在、多くの企業はTHE MODELに基づいて分業体制や縦割りの組織運営を行っています。その結果、それぞれの組織が何をしているのか、どのような思想を持っているのかがわからないブラックボックス化が進んでいます。
その状態を解消するために、BPO事業者は組織の中枢に入り、業務プロセスの分解を適切に行う必要がある。それを私は「融合」と表現しました。
向井:
ビジネスプロセスを外部に依頼する場合、委託業務の成果の最大化など局所的な話題になりがちです。そうではなく、業務全体を可視化することから改善すべき業務や戦略、数字の設計が必要だということですね。
ちなみに、原さんもフリップで「脱ブラックボックス」と書かれていますね。
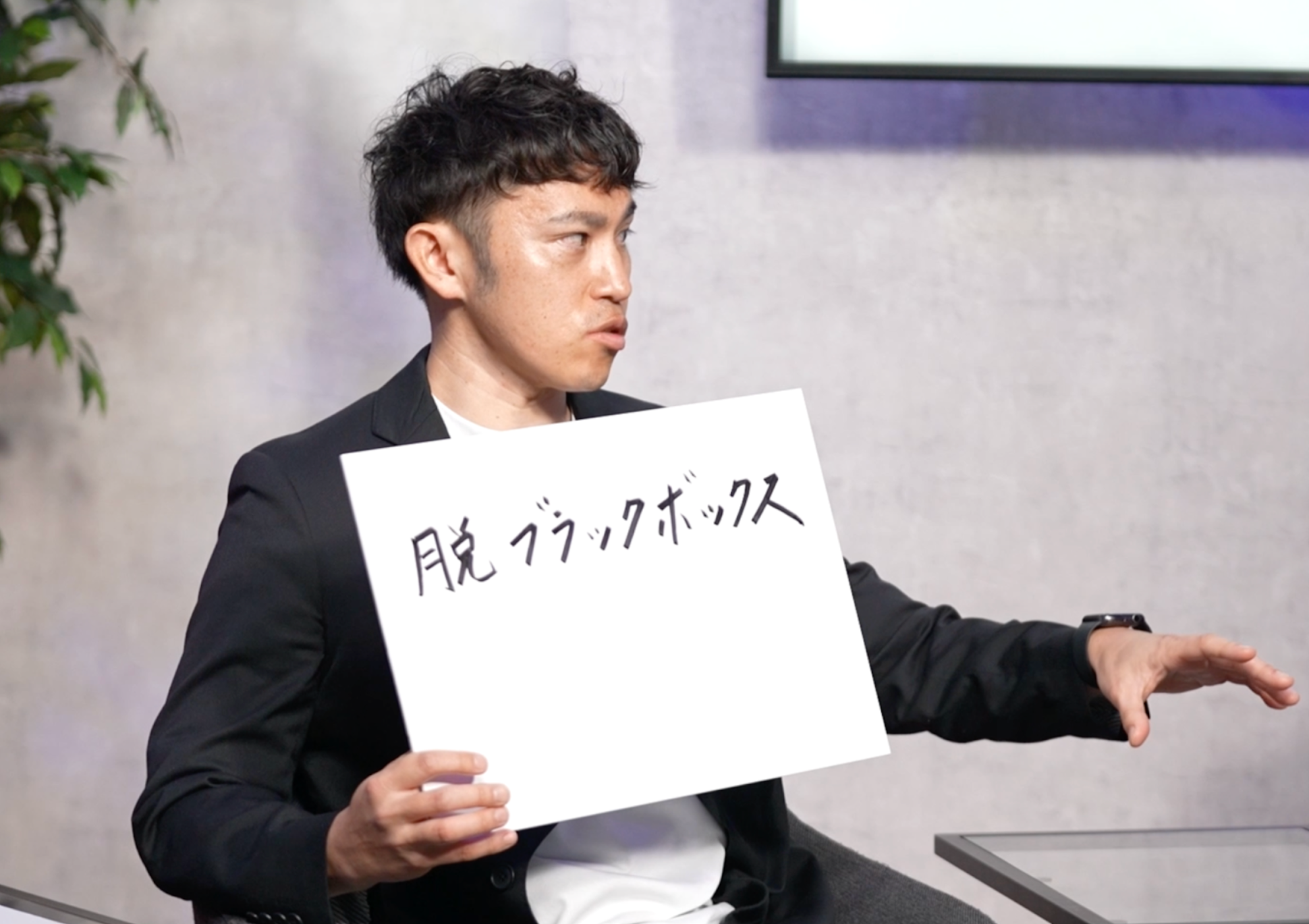
原:
テクノロジーの発達で、コールやメール、商談など各業務の可視化は低コストで実現できるようになってきました。しかし、一方でバリューチェーン全体を見渡すと、何をやっているのかがわからないブラックボックスが多く存在しています。
脱ブラックボックスにしっかり取り組むことは、ビジネスプロセス領域の変革の第一歩だと思います。
向井:
脱ブラックボックスの第一歩として、取り組むべきことは何でしょうか?
原:
まずはテクノロジーを活用して、自分たちの業務や人目につかなかったプロセスを可視化していくことが大事ではないでしょうか。
向井:
なるほど。山梨さんもテクノロジーについてフリップに書いていますね。「メソドロジー✕テクノロジー」とは、どのような意味でしょうか?
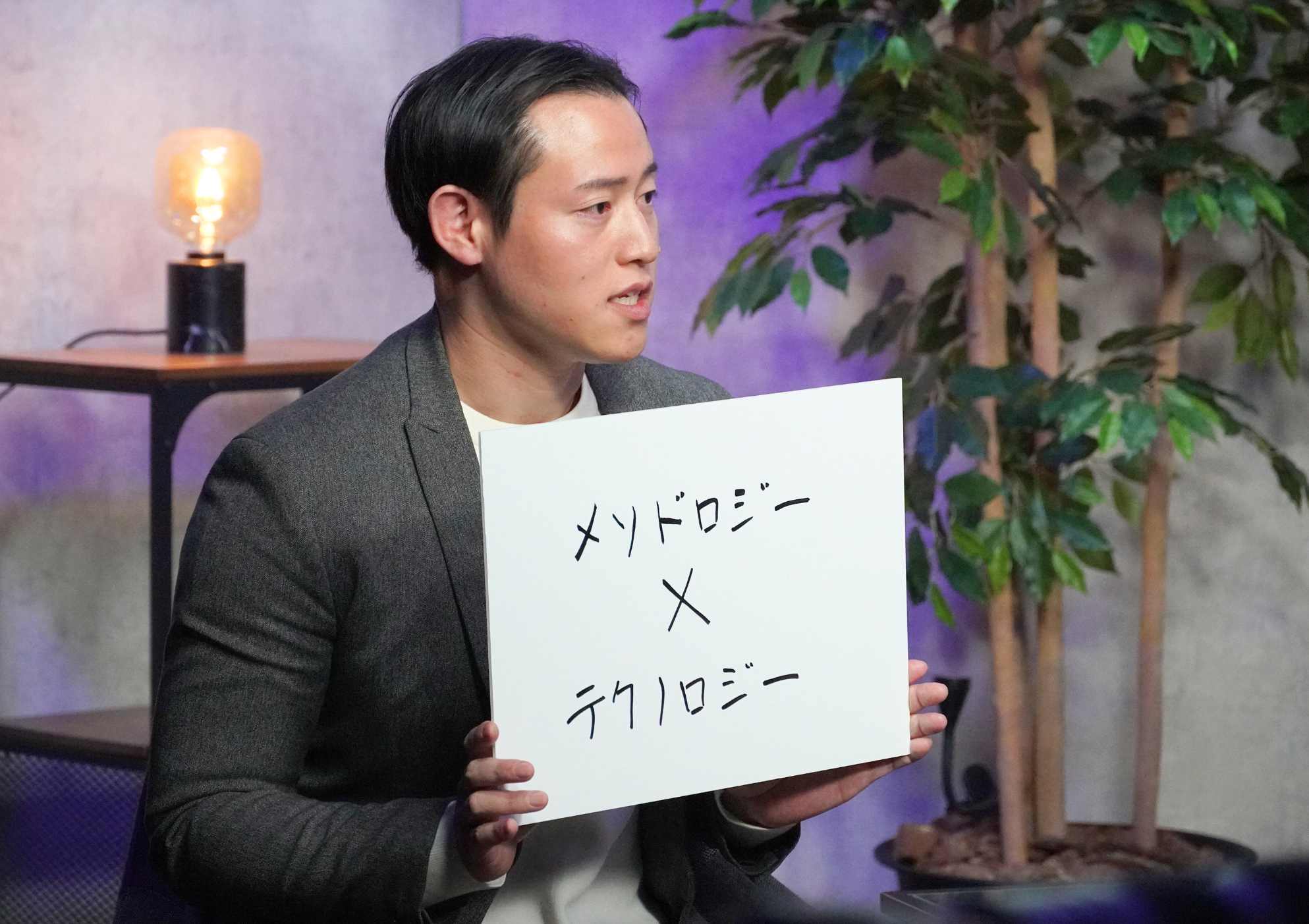
山梨:
日本語で表現するなら、「方法論と再現性」になるでしょうか。この2つが、これからのビジネスプロセスの変革には必要だと思っています。
私が個人的に大切にしているのは、成果が出る領域にリソースを投入すること(メソドロジー=方法論)。確固たる方法論がなければ、営業活動の選択を間違ってしまうでしょう。
そして、方法論の実行部分を助けるのがテクノロジー(再現性)です。この部分が属人的になっている企業は少なくありません。一部のトッププレイヤーに頼ったBPOの体制では、お客様に提供できる価値が大きく限定されてしまいます。メンバー全員が、トッププレイヤーと同等のパフォーマンスを発揮できるテクノロジー活用の基盤を築くことが重要だと思います。
向井:
デジタル活用は多くの企業が注目するテーマである一方、デジタルツールを扱う土台となる方法論は顧客ごとに異なります。もしかしたら、その企業はデジタルチャネルではなく紙媒体(手紙など)のほうが、お客様にアプローチしやすいかもしれません。
阿部さんも、テクノロジー活用について触れていますね。
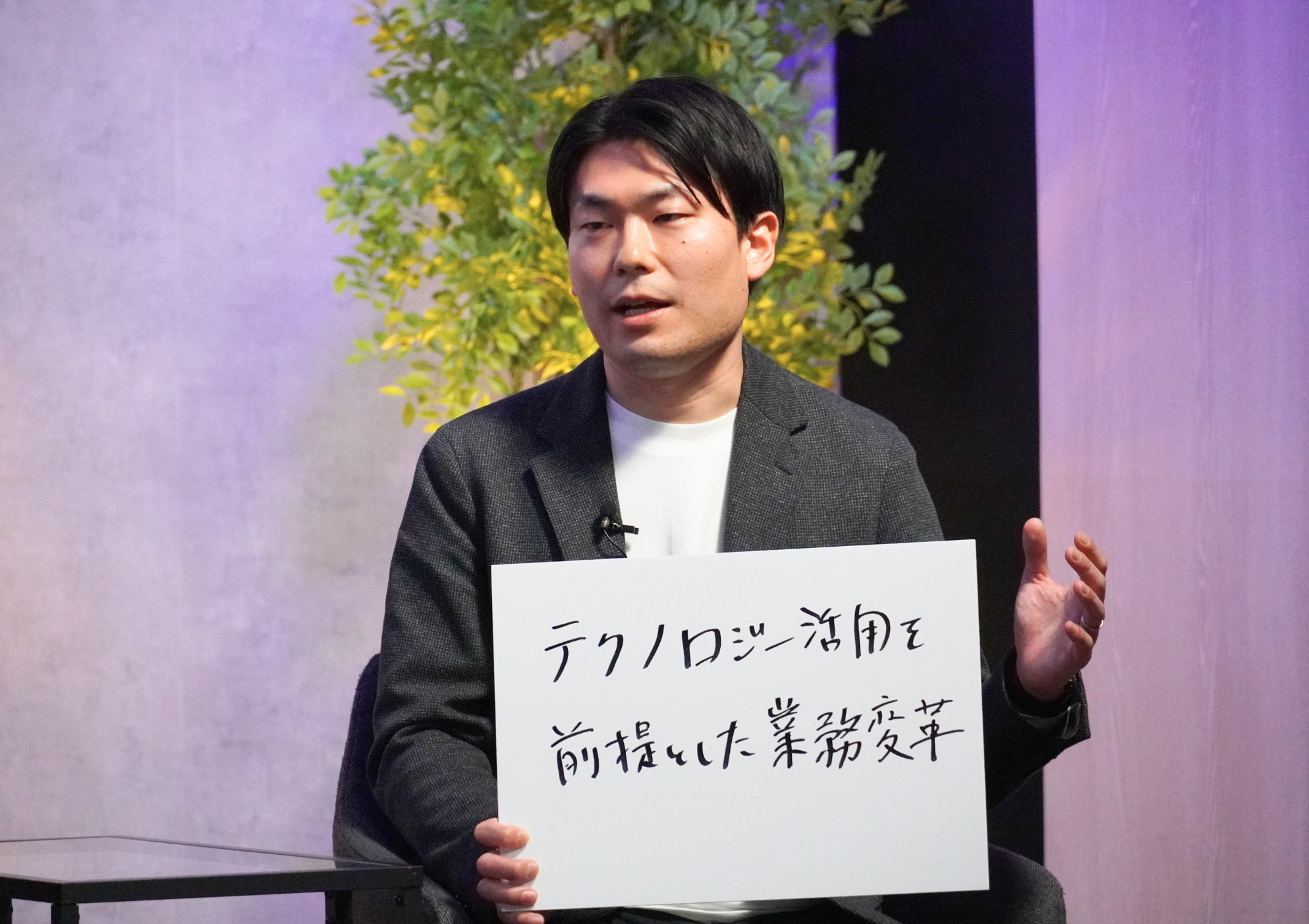
阿部:
私は「テクノロジー活用を前提とした業務変革」が大切だと書きました。
BPOにおいて、エンドユーザーに最適な体験を提供するうえでマンパワーは欠かせません。しかし、その手前の業務を行っていく過程において、AIをはじめとしたテクノロジーの活用を大前提に考えなければ、成果の最大化はできないでしょう。
例えば、スマートキャンプではCRM、データ、AIという3つのキーワードで、デジタル活用を進めているんです。
CRMではセールスエンゲージメントツール「BALES CLOUD(ベイルズクラウド」を通じて、業務自動化を進めています。お客様との電話内容の要約とフィードバックでは、AIを積極的に活用しています。さらに、AIを通じてお客様の企業情報、提供サービス、経営層の考え方などのデータを効率的に収集して、アプローチできるようにしています。
ビジネスプロセスにおいてはテクノロジーを最大限取り入れて、効率化を図る。そこで生まれたリソースを、営業活動の質の向上やお客様のコミュニケーション体験の向上に投下することに、日々取り組んでいます。
向井:
多くの企業のビジネスを支援してきた皆さんだからこそ、テクノロジー活用による業務変革も支援できるというのがよくわかるお話でした。AIをはじめとしたテクノロジーの扱いに悩んでいる発注者は、その悩みをぜひBPO事業者に打ち明けてほしいと思います。
最後に、BPO導入を検討している方々へ、皆さんから一言ずつメッセージをお願いします。
阿部:
BPOを依頼する際は、BPO事業者との付き合いを通じて、自社をどう変革していきたいのかを考えてみていただければと思います。アポイント獲得だけでなく、生成AI活用のように、社内のDXを推進することも不可能ではありません。
自分たちが何を求めていて、どのような会社と取引したいのかという視点から、BPO事業者を選択してみてください。
原:
今日集まったBPO事業者はインサイドセールスを専門としていますが、私たちはバリューチェーン全体の最大化という観点を持っています。BPOで売上最大化を目指したい方々は、ぜひお声がけください。
山梨:
BPO事業者の選別は、社内の人材採用と同じだと思っています。自社の事業戦略・組織戦略に不足しているピースをカバーしてくれる企業(人材)を探すわけですから。どのBPO事業者に依頼すれば、もっとも自社の成長に貢献してくれるのかを高い解像度で捉えて業者を探すことで、間違いない選択ができるはずです。
冨田:
BPO事業者にさらなる期待を寄せていただくのと同時に、私たち自身もさらに進化していくべきだ。そんな考えから、この特別企画を考えました。
より深い部分でお客様のビジネスに貢献するためには、お客様に向き合う時間をもっと増やしていくことが、BPO事業者には必要だと思っています。これを機に、「BPO事業者にもっと多くのことを期待してもいいんだ」と感じていただけたら、とても嬉しいです。
向井:
以上、4名に「“BPOの現在地”再現性はどこにあるのか。これからのパートナーシップの在りかた」をテーマにお話をお伺いしました。
皆様、本日はありがとうございました!
一同:
ありがとうございました!

特別編【前編】是非を問う。4人のリーダーが語る”BPOの現在地”#THELEADERS特別編 もあわせてご覧ください。
YouTubeで特別対談の様子も公開しています。
【4社共同制作】インサイドセールスBPO 提案依頼書テンプレート
業界全体の信頼性向上とインサイドセールスBPOのさらなる成果創出を目指し、SALES ROBOTICS、スマートキャンプ、セールスリクエスト、Marooの4社で、BPOの提案を依頼する際に必要な、自社の要件や条件をまとめた資料(提案依頼書=RFP)のテンプレートを共同制作し、公開しました。
どなたでも無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
ダウンロードはこちらから
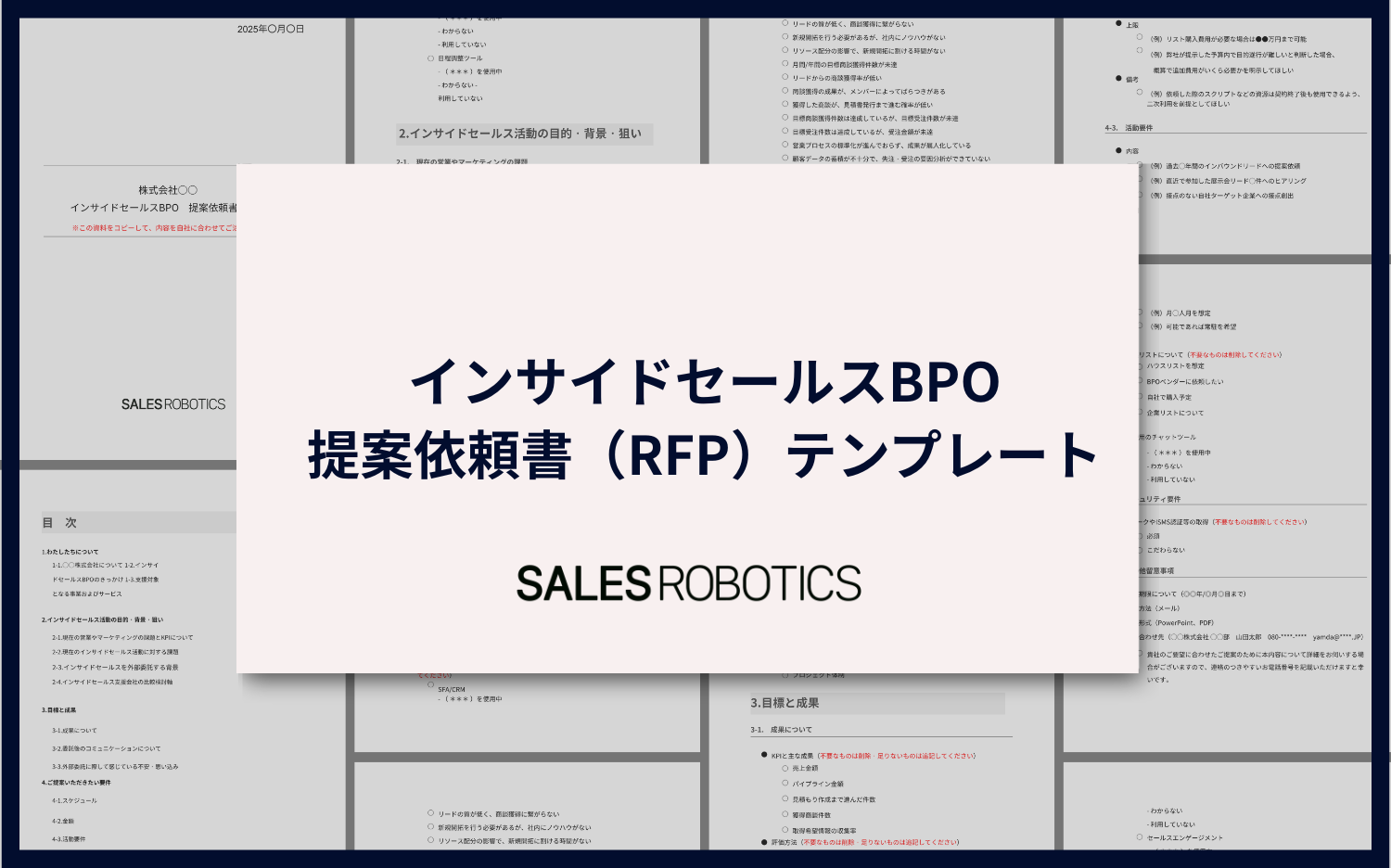
<インサイドセールスBPO 提案依頼書 目次>
1. 会社・サービス概要(自社)
自社の基本情報、事業内容、インサイドセールス導入の背景などを記載します。
2. インサイドセールス活動の目的・背景・狙い
なぜBPOを利用するのか、どのような課題を解決したいのかを明確にします。
3.目標と成果
具体的なKPI(例: 商談獲得数、商談化率など)や期待する成果レベルを設定します。
4.希望する提案内容
業務範囲、体制、報告形式、セキュリティ要件など、具体的な要望を記載します。
※予算感、契約期間、選定スケジュールなども必要に応じて項目を追加・修正可能です。
今回の「THE LEADERS」特別編は、お楽しみいただけましたか?本シリーズでは、今後も各業界で活躍するインサイドセールスのリーダーをお招きして対談を行います。次回もぜひ、ご覧ください。
過去のインタビュー記事はこちらから
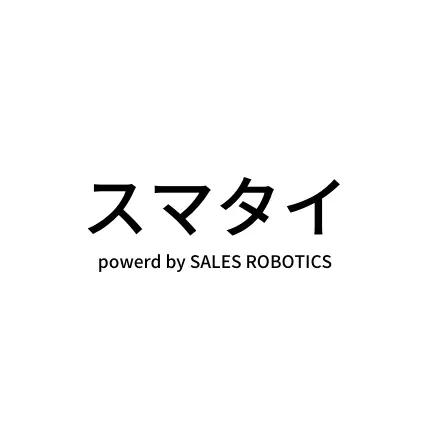
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る