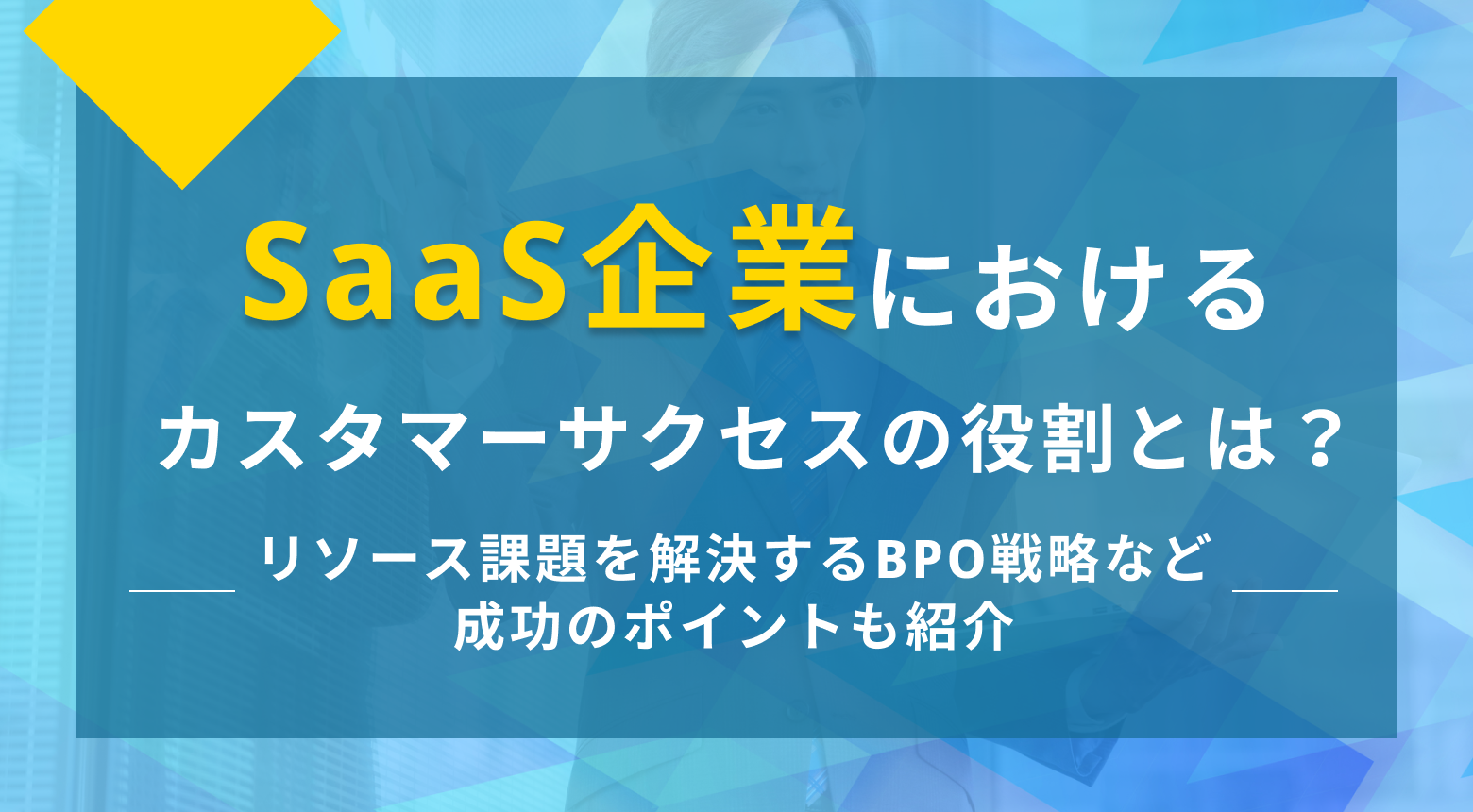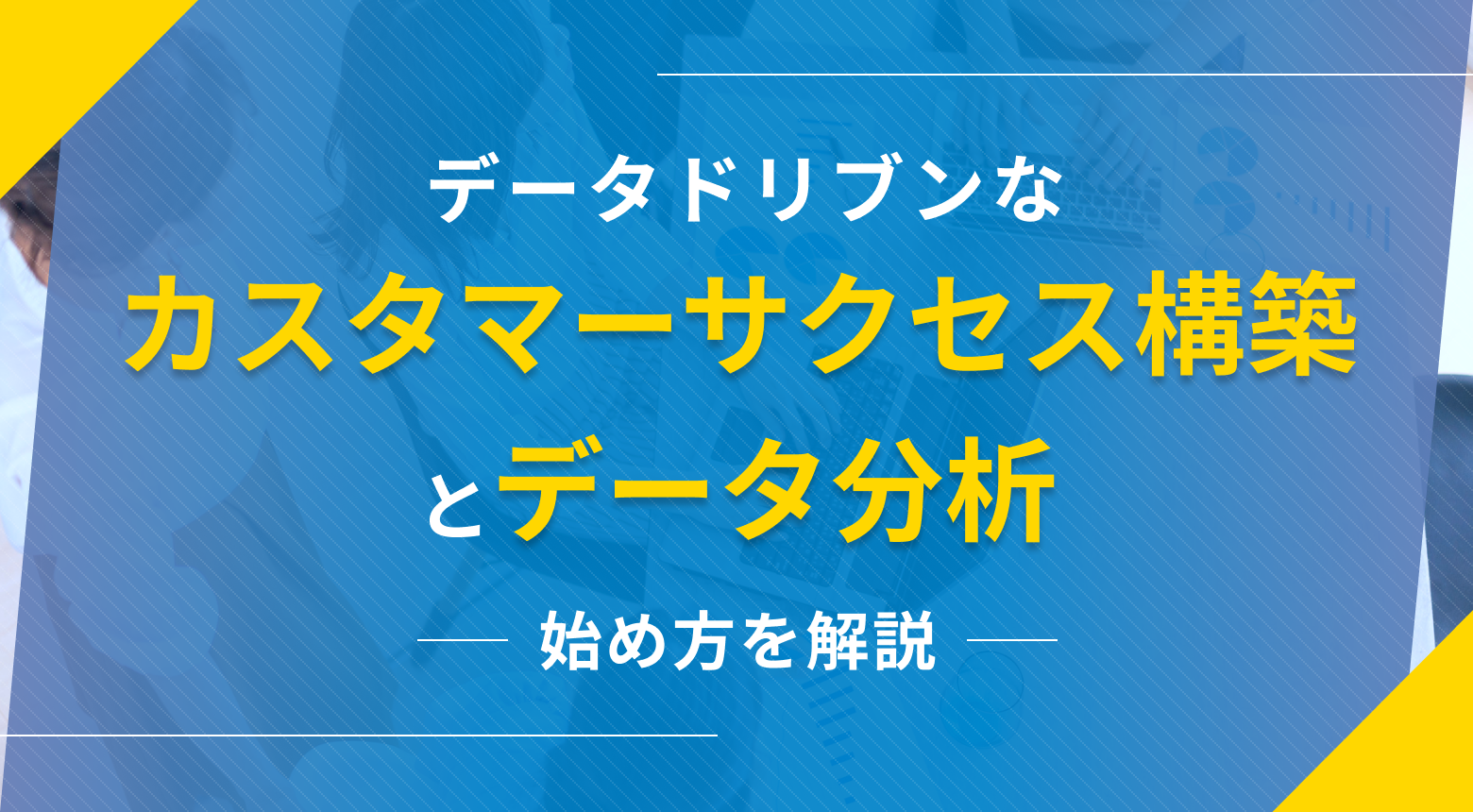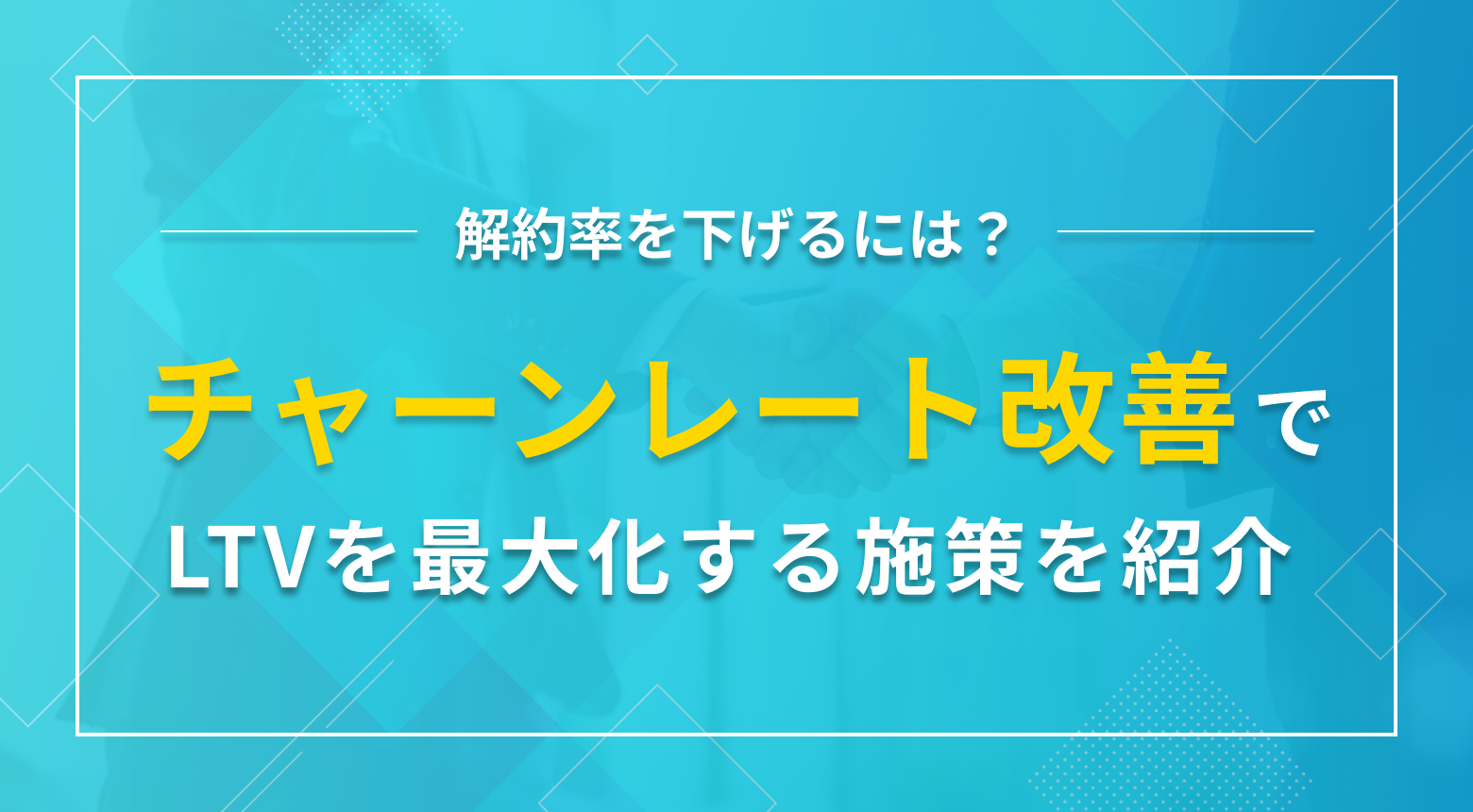NPSとはどんな指標?顧客満足度との違いや測定方法を解説
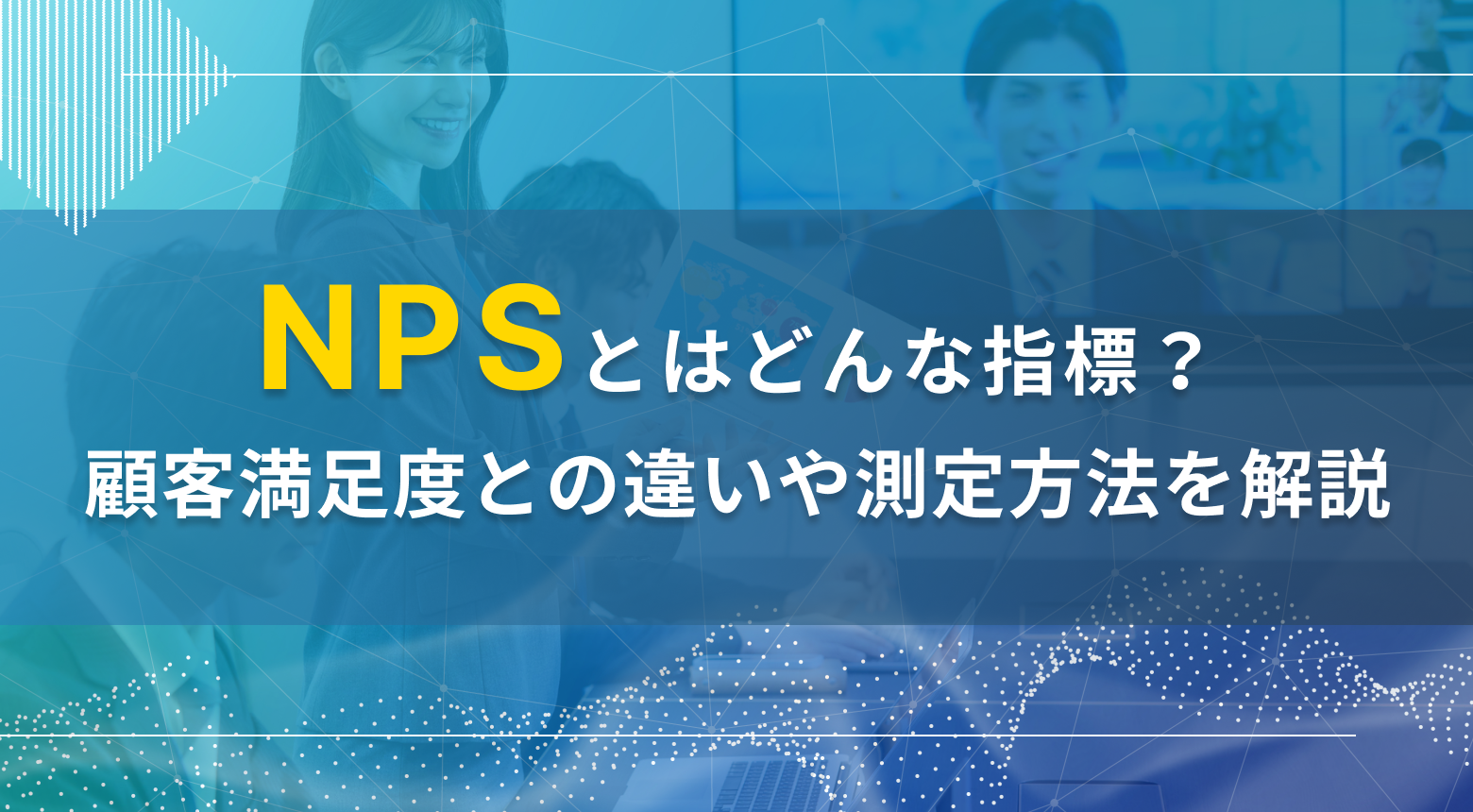
NPS(ネット・プロモーター・スコア)とはNet Promoter Scoreの略で、顧客ロイヤルティを測る指標のことです。NPSが高い場合、製品やサービスの推奨者が多いということになり、ポジティブなクチコミから企業の売上向上につながる可能性が高まります。
当記事では、NPSの概要や顧客満足度との違いなどを解説します。NPSの測定方法や導入のメリット・デメリットも説明するので、顧客との関係性強化に活用してください。
NPSとは顧客ロイヤルティを測る指標
NPSは「Net Promoter Score」の略で、顧客が企業や製品、サービスに対してどれくらいの信頼や愛着を持っているかを数値化する指標です。統計的な理由から0から10までの11段階のスケールで評価され、顧客に「この製品(サービス)を友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」という質問をすることでスコアを算出します。
NPSが高い企業は、製品やサービスの推奨者が多いことを意味します。推奨者が増えることで、ポジティブな口コミが広がり、企業の売上向上につながりやすくなります。実際、NPSを開発したベイン・アンド・カンパニーでも以下のように報告されています。
業績成長との相関が最も強く観測された指標が「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」なのです。
NPS®(ネット・プロモーター・スコア®)とは? | Bain & Company
また、NPSには顧客向けだけでなく、従業員向けの指標として「eNPS(employee Net Promoter Score)」も存在します。「eNPS」は、従業員が自分の職場に対してどれくらいの信頼や愛着を持っているかを測るもので、企業の従業員満足度やエンゲージメントを把握する上で役立ちます。
NPSは顧客ロイヤルティを可視化し、企業の成長に貢献する重要な指標として幅広い業種で活用されています。なかでも、個々の顧客体験がNPSに影響するBtoC企業や、継続利用が収益の鍵となるSaaS企業などのサブスクリプション型ビジネスで活用される傾向があります。
NPSと顧客満足度との違い
NPSと顧客満足度は、どちらも顧客の感情を測る指標ですが、最も大きな違いは、事業の収益に結びつくかどうかという点です。顧客満足度が「過去の体験に対する感情的な評価」を問うのに対し、NPSは「未来の推奨意向という行動」を問う点に本質的な違いがあります。
NPSは、顧客が製品やサービスを他者に推奨する意向を測るものであり、企業の収益性との強い相関が認められています。推奨意向が高い顧客は実際にポジティブなクチコミを広げ、それが新規顧客獲得や売上向上に直結する可能性が高いためです。
一方、顧客満足度の高さは重要ですが、企業の売上増加に直接的につながるものではありません。顧客満足度は、製品やサービスに対する主観的な満足度を測るものであり、調査時点での評価に留まる傾向がみられます。顧客満足度が高くても友人や同僚に積極的に推奨するほどではない、というケースも見られます。
近年、インターネット上の口コミが消費者の購買行動に大きな影響を与えるようになったこともあり、多くの企業が単なる満足度だけでなく、推奨行動を促すNPSを重視し、導入する傾向が強まっています。NPSを導入することで、企業の真の成長につながる顧客ロイヤルティをより正確に把握し、戦略に活かせるでしょう。
NPSで用いられる評価
NPSで用いられる評価は、『推奨者』と『批判者』の比率の差をスコアとして算出します。主に3つのステップでスコアを算出します。
【NPSの測定方法】
- 顧客に「製品やサービスを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」の質問に0~10点で回答してもらう
- 顧客の回答を3つのセグメントに分類する
- 推奨者の割合から批判者の割合を引いて算出する
まず、顧客に対し「この製品やサービスを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問をし、顧客は質問に対して0点から10点の11段階で回答します。
次に、顧客の回答を以下の3つのセグメントに分類します。
| 回答の点数 | セグメントの分類 | セグメントの詳細 |
|---|---|---|
| 10~9点 | 推奨者(Promoter) | ・製品やサービスに非常に満足している ・積極的に他者に推奨してくれる可能性が高いロイヤルな顧客 |
| 8~7点 | 中立者(Passive) | ・製品やサービスに不満はないものの、熱心な推奨者でもない ・競合他社に乗り換える可能性がある |
| 6~0点 | 批判者(Detractor) | ・製品やサービスに不満を持っており、ネガティブな口コミを広めるリスクがある ・企業にとっては早急な改善が必要な対象 |
| NPS=「推奨者の割合」ー「批判者の割合」 |
中立者の割合はNPSの計算には含めませんが、顧客ロイヤルティ全体を把握する上で重要な要素となります。このようにして算出されたNPSは、-100から+100までの範囲で示され、企業が顧客からどの程度支持されているかを客観的に示す指標となります。
NPSに用いられる調査方法
NPS調査には、主に「リレーショナル調査」と「トランザクショナル調査」の2種類があります。これらを適切に使い分けることで、顧客ロイヤルティの全体像と具体的な課題の両方を効果的に把握できます。
リレーショナル調査は、顧客がブランド全体に対して抱く推奨度を測るものです。企業と顧客の長期的な関係性や、ブランドイメージ全体がNPSにどう影響しているかを把握するのに適しています。
一方、トランザクショナル調査は、購入時・カスタマーサポート利用後など顧客が経験した特定のタッチポイントにおける推奨度を測るものです。個別の体験がNPSに与える影響を詳細に分析し、具体的な改善点を見つけるのに役立ちます。
両方の調査を組み合わせることで、企業は顧客ロイヤルティの全体像を把握しつつ、具体的な顧客体験における課題を特定できますが、常に両方を行う必要はありません。まずはリレーショナル調査でNPSに大きな影響を与えている全体的な要因やポイントを特定し、その後に特定された課題に関連するトランザクショナル調査を実施すると、より効率的に改善サイクルを回せるでしょう。
リレーショナル調査
リレーショナル調査は、顧客と企業やブランドとの長期的な関係性や全体的な体験について評価を尋ねる手法です。年に一度顧客全体に対してNPSを測るようなケースが該当します。
| 調査対象 | 企業やブランド全体の利用経験がある顧客 |
|---|---|
| 調査目的 | ・顧客ロイヤルティの全体像の把握 ・自社の強み・弱みの特定 ・長期的な顧客関係の変化のモニタリング |
| 質問内容 | 「あなたは私たちのブランド(または製品)を友人や同僚にどの程度勧めたいと思いますか?」など ※企業やブランド全体に対する推奨度を尋ねる質問が中心 |
| 実施頻度 | 年に1回~数回程度の定期的な実施が多い |
| 分析 | ・顧客全体のロイヤルティレベルを把握し、長期的な変化を追跡 ・顧客属性別の分析も行われる |
リレーショナル調査は、顧客との関係性を長期的な視点で捉え、企業全体のロイヤルティ向上に向けた戦略を立てる上で重要な役割を果たす手法といえるでしょう。
トランザクショナル調査
トランザクショナル調査は、購入後・カスタマーサポート/サービス利用後など、顧客が特定の取引やインタラクションを行った直後に実施されるNPS調査のことです。ウェブサイトでの購入完了直後に表示されるアンケートなどが該当します。
顧客の記憶が鮮明なうちに意見を収集できるため、より具体的で正確なデータが得られやすい手法です。
| 調査対象 | 特定の顧客体験(購入、利用、問い合わせ等)直後の顧客 ※体験ごとに意見を収集 |
| 調査目的 | ・ロイヤルティ向上 ・個別体験の評価を把握し、顧客接点の課題特定と改善につなげる |
| 質問内容 | 「この体験を親しい人にどれくらい勧めたいですか?(0~10点)」など ※理由や改善点も聴取 |
| 実施頻度 | ・各顧客体験の直後、または一定期間内に実施 ※継続的なデータ収集が重要 |
| 分析 | ・推奨度分布、推奨理由の分類、顧客セグメント別評価、時系列変化の把握 ・改善効果の測定 |
トランザクショナル調査の特徴は、特定のタイミングでアンケートを送信し、顧客体験のどの部分がロイヤルティに影響を与えているのかを詳細に分析できる点です。個々の顧客体験を把握し、具体的なタッチポイントにおける顧客ロイヤルティを測定・改善するために行われます。
NPS導入のメリット
NPS導入のメリットはおもに以下の3点です。
【NPS導入のメリット】
- 顧客体験を指標化できる
- 製品やサービスの改善につなげられる
- 同業他社と比較できる
これらのメリットは、いずれも企業の収益向上に関わる重要な要素です。顧客との関係強化や、将来の収益予想などに活用できます。
顧客体験を指標化できる
NPSは、顧客体験を0から10の11段階で数値化します。 これにより、これまで曖昧だった顧客の感情や満足度を明確に把握し、定量的な評価が可能になります。
カスタマーサクセス部門では、NPSを定期的に測定することで、顧客のヘルススコアとして活用できます。これにより、解約リスクのある顧客を早期に特定し、プロアクティブなアプローチを行うことで、顧客離反の防止やLTVの向上につなげることが可能です。
顧客体験を数値として指標化することで、自社のサービスレベルを客観的に把握でき、課題や改善点を見つけやすくなります。競合他社と比較したり、業界平均と照らし合わせたりすることで、自社の強みや弱みを浮き彫りにできるのです。
また、NPSという共通の指標を持つことで、組織全体の顧客体験に対する意識改革を促し、部門間の連携を強化することも可能です。
さらに、NPSを具体的な数値目標として設定することで、顧客体験向上のための具体的な取り組みを計画しやすくなります。施策実施の前後でNPSを比較すれば、その効果を定量的に評価できるため、PDCAサイクルを効果的に回せるでしょう。
製品やサービスの改善につなげられる
NPSは、製品やサービスの具体的な改善点を見つけ出すためのツールとなります。NPS調査を行う際に、顧客に製品やサービスを友人や同僚に勧める可能性を尋ねるだけでなく、評価の具体的な理由を問い、把握するようにしましょう。評価の理由を通して「顧客が何に価値を感じているのか」「何に不満を抱いているのか」を明確にできるのです。
たとえば、推奨者がとくに評価している機能の強化に注力することで、製品の強みをさらに伸ばせます。批判的な意見からは、顧客体験における課題点やボトルネックを特定し、改善策を講じることが可能です。
さらに、NPS調査で得られた顧客の生の声は、カスタマーサポートの質向上や、顧客ニーズに合致したメッセージの発信、ターゲット層の明確化といったマーケティング戦略の見直しにもつながります。顧客が本当に求めているものを理解することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
NPS調査は、単なる数値測定に留まらず、顧客の声に基づいた具体的なアクションにつなげることで、持続的な成長と顧客ロイヤルティの向上に役立てられます。顧客からのフィードバックを積極的に活用し、サービス改善のサイクルを回すようにしましょう。
同業他社と比較できる
NPSは、業界内での自社の立ち位置を客観的に把握するのに有効な指標です。業界や企業規模を問わず広く採用されているため、競合他社や業界平均との比較を通じて、具体的な戦略立案につなげることができます。
同業他社との比較を通じて、自社の強みや弱みが明確になります。さらに、業界平均や競合他社のトップ企業のスコアを参考にしながら、より現実的かつ具体的な目標を設定することが可能になります。
また、高いNPSを誇る競合他社がどのような取り組みをしているかを分析することで、自社の顧客体験改善策を検討する上での貴重なヒントを得られる場合もあります。成功事例から学び、自社のサービスや製品に活かすことで、顧客ロイヤルティの向上につながる具体的な施策を打ち出すことができるでしょう。
ただし同業他社のNPSを鵜呑みにせず、自社の状況を十分に踏まえた上で、多角的な視点から分析を行う必要があります。調査方法や対象顧客層などNPSの測定方法は同業他社と一致しない場合があるため、他社のNPSはあくまで参考情報として活用するようにしましょう。
NPS導入のデメリット
NPS導入のデメリットはおもに以下の3点です。
【NPS導入のデメリット】
- 日本では国民性が影響する場合がある
- 数字別の評価が見えない
- 質問の手法やタイミングによって回答が変わる
それぞれの対策も併せて紹介するので、参考にしてください。
日本では国民性が影響する場合がある
NPSを日本市場で活用する際、国民性が影響してスコアがマイナスになる傾向があります。日本の消費者は、製品やサービスに対する評価において、極端な高評価や低評価を避け、中間付近の評価を選択する傾向があるからです。
NPSは、0から10の11段階評価で行いますが、日本人は「5」や「6」といった中立的な点数をつけやすく、全体的なスコアが低く出やすいのです。この傾向を踏まえると、単純にスコアが低いからといって悲観する必要はありません。
ただし、文化差を考慮した質問設計を行うことや、業界や顧客層が近いグローバルな基準との比較検討を行うことで、より正確な分析が可能になります。質問文に日本の文化に合わせたニュアンスを取り入れたり、日本独自のベンチマークを設定したりすることで、スコアの解釈をより適切に行える可能性が高まります。
具体的な対処法としては、過去の自社スコアとの時系列比較や、業界平均や競合との相対比較によって自社の立ち位置を客観的に評価する方法があります。これにより、単一のスコアに囚われず、自社の改善点や強みをより明確に把握できるようになります。
NPSは元来グローバルな指標ですが、導入にあたっては日本の消費者の傾向や文化的な背景などを理解し、適切な調整を行う必要があります。
数字別の評価が見えない
NPSのデメリットとして、数字だけでは顧客の具体的な評価が見えにくい点も挙げられます。NPSでは0から6点を批判者、7点と8点を中立者、9点と10点を推奨者と分類します。0点と6点のどちらも「批判者」として扱われるため、顧客が抱いている不満の深刻さや、その度合いが把握しにくくなるのです。
さらに、NPSのスコアだけでは、顧客がその数字を選んだ具体的な理由を知ることはできません。質問の回答が「0点」だった場合、何が不満でその評価に至ったのかが不明瞭なため、改善策を検討するのが困難になります。顧客の不満の程度がわかりづらい点は、企業にとってサービス改善の優先順位付けを難しくする要因となります。
数字別の評価を把握するためには、定性的な情報を収集できる自由記述欄の設置が有効です。
【自由記述欄の例】
- 「このサービスを友人や同僚に勧めるとしたら、特にどのような点について勧めたいですか?」
- 「今回、0点と評価された具体的な理由は何ですか?改善すべき点があれば教えてください」
- 「もしこのサービスを継続して利用する上で、最も期待することは何ですか?」
自由記載欄から収集したテキストデータをテキストマイニングによって分析することで、評価の背景にある顧客の真のニーズや不満、魅力の源泉などが明確になります。加えて、満足度と相関の強い要因(ドライバー)を特定するドライバー分析といった手法を用いることで、評価の背景にある具体的な課題を特定できます。
NPSスコアだけでなく、推奨度と理由を組み合わせた分析を取り入れることで、顧客体験をより深く理解し、具体的な改善策につなげられます。
質問の手法やタイミングによって回答が変わる
NPSは、質問の手法やタイミングによって回答が大きく変動する点もデメリットです。質問の手法や顧客の状況に応じて回答が変わるため、安易な比較や解釈は誤った意思決定につながりかねません。
たとえば、インターネット上で実施するアンケートと、店頭で直接尋ねる調査では、顧客の回答に対する心理的ハードルや回答の精度が異なることがあります。また、製品やサービスを購入した直後の顧客と、長期間利用している既存顧客とでは、ロイヤルティの評価基準や感情が異なるため、同じ質問でも異なるNPSスコアが出ることが想定されます。
NPSを測定する際は、常に同じ質問形式、同じ回答スケール、同じタイミングでデータを収集するように努めましょう。さらに、継続的なデータ収集を行い、スコアの変動を時系列で把握することも重要です。
単発で行った調査のスコアに一喜一憂することなく、季節性やプロモーションなどの外部要因による変動を考慮し、NPSの真の傾向を捉えられるようにしましょう。
NPS運用のポイント
NPS運用のポイントは、主に以下の3点です。
【NPS運用のポイント】
- 改善につながる質問を設計する
- 顧客の声を多角的に収集・共有する
- 調査結果を共有し顧客分類を活かして改善を行う
さらに、NPSに限らずアンケートは回答数が多いほど実際の数値に近づきます。できるだけ多くの回答を集められるようにしましょう。
改善につながる質問を設計する
NPSの運用において、効果的なフィードバックを得るためには質問の設定を工夫することが重要です。回答者によって設問内容の受け取り方にズレが生じる可能性を考慮し、まずは質問の設定を工夫することから始めましょう。
たとえば、「このサービスを友人に勧めますか?」に対して、回答者がサービス全体を評価するのか、特定の機能について評価するのか、意図が伝わりにくければ回答のブレにつながります。
質問を工夫することで、回答者が商品やサービスを薦めたくなる場面を具体的にイメージしやすくなります。「どのような状況で、このサービスを友人に勧めたいと思いますか?」など、具体的なシチュエーションを想起させる問いかけにすることで、より詳細で質の高いフィードバックを引き出せます。結果的に回答の精度が高まり、得られたデータからより良い分析結果や改善点を見つけられるようになります。
さらに、基本質問に加え、「その評価をつけた理由は何ですか?」という自由記述、そして「顧客体験のどの部分(例:価格、機能、サポート)がNPSに影響しているか」を探るドライバー質問を追記しましょう。これらの質問は、NPSの具体的な要因を深掘りし、より実用的な改善点を見つけ出すことを可能にします。
また、対象者を誰にするのか慎重に検討することも重要です。NPSは顧客ロイヤルティを測る指標であり、得られた数値は企業の戦略や施策に直接影響します。そのため、誰からの意見を求めるのか、その対象者が企業の収益や成長にどのように関わるのかを考慮し、適切な顧客層に質問を投げかける必要があります。
回答率を向上させ、未回答が増えることを防ぐためには、5分前後の短時間で回答できるように設問を絞り込むようにしましょう。質問数が多すぎると、回答者の負担が大きくなり、途中で離脱してしまう可能性が高まります。シンプルで明確な質問に絞り込むことで、回答者のストレスを減らし、正確なデータを効率的に収集することが可能になります。
顧客の声を多角的に収集・共有する
NPS運用において、ソーシャルリスニングの活用は有効な手段となります。ソーシャルリスニングを活用すれば、NPS調査に回答しない「サイレントマジョリティー」の声を捉えられるからです。
NPS調査は顧客ロイヤルティを測る上で有効ですが、回答しないサイレントマジョリティーの存在はスコアの偏りを生じさせ、正確な現状把握を難しくする可能性があります。 そのため、その声を補完する手法としてソーシャルリスニングが有効です。
ソーシャルリスニングは、SNSやレビューサイト、掲示板など、顧客が自発的に意見を発信するプラットフォームを監視・分析することで、NPS調査だけでは捉えきれない声を間接的に拾い上げることが可能になります。これは、顧客の声(VOC)を多角的に収集する一環として位置付けられます。
顧客の声(VOC)の収集・分析手法について、より詳しく知りたい方は、「VOC分析を導入するべき企業の特徴や収集方法を解説」もご覧ください。
| 洞察 | 詳細 |
|---|---|
| ポジティブな意見の潜在的な広がり | ・NPS調査で中立者(8~7点)に分類される層や、回答しない層が、実際には好意的な意見を広めている可能性を把握できる |
| 潜在的な不満の早期発見 | ・NPS調査で顕在化していない不満や課題が、ソーシャルメディア上で散見されることがある ・早期に発見し対応することで、デトラクター化を防げる |
| 顧客ニーズの深掘り | ・NPS調査の回答理由だけでは見えにくい、より具体的な顧客のニーズや要望を把握できる |
| 競合との比較 | ・競合他社に対する顧客の声も分析することで、自社の強み・弱みを相対的に理解できる |
ただし、ソーシャルリスニングで得られる情報にはノイズが含まれる可能性もあり、NPS調査の結果と組み合わせて多角的な分析が重要です。サイレントマジョリティーの潜在的な声に耳を傾け、NPSの改善や顧客体験の向上につなげることは、企業の持続的な成長に貢献します。
調査結果を共有し顧客分類を活かして改善を行う
NPSは、単なる顧客満足度を測るだけでなく、事業改善の具体的なヒントを得るための強力なツールです。その効果を最大限に引き出すためには、調査結果を社内で共有し、顧客を適切に分類して分析することが必要です。
NPSの調査結果を全社で共有することは、各部署が顧客の声を直接認識し、自社の製品やサービスの改善点を把握する上で重要です。例えば、「配送が遅い」という声が多ければ物流部門が改善策を検討するなど、具体的なアクションへとつながり、PDCAサイクルの基盤となります。
調査結果を共有する際は、単にスコアだけでなく、評価ポイントや具体的な改善点を提示することで、「なぜこのスコアなのか」「どこを改善すべきか」を明確に理解できます。ポジティブなフィードバックは成功事例として共有しモチベーション向上に、ネガティブなフィードバックは具体的な課題として建設的な議論の場を設けることで、部署横断的な改善へとつながるでしょう。
また、NPSの回答を「推奨者」「中立者」「批判者」の3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特性に応じた改善活動を行うことも重要です。批判者に対しては、アンケートの自由記述や個別のヒアリングを通じて問題点を具体的に洗い出し、不満や期待外れだった点を深く掘り下げます。中立者に対しては、推奨者になってもらうための「あと一押し」の要素を探ります。
さらに、製品やサービスだけでなく、カスタマーサクセスの活動を見直すことも有効です。オンボーディングの改善、FAQの充実、問い合わせ対応の迅速化など、顧客が困った時に信頼できる存在であることを示すことで、NPSの向上が期待できます。
NPS向上の鍵となるのは、分析結果を具体的な改善アクションにつなげ、その結果を顧客にフィードバックする「クローズドループ」を回すことです。特に、批判的な意見が寄せられた顧客に対する個別対応や問題解決の実施は、ロイヤリティ向上に寄与します。
まとめ
NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは、顧客ロイヤルティを測る指標であり、顧客が製品やサービスに対してどれくらいの信頼や愛着を持っているかを数値化するものです。NPSが高い場合、製品やサービスの推奨者が多いということになり、ポジティブなクチコミから企業の売上向上につながる可能性が高まります。
NPSを測定するには、顧客に「この製品(サービス)を友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」という質問をし、0から10までの11段階で回答してもらいます。顧客の回答を推奨者、中立者、批判者の3つのセグメントに分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いてスコアを算出します。
NPSの導入を検討する場合は、まず自社の課題や目標を明確にし、適している調査方法を検討しましょう。調査後のデータ分析や改善策実行までを見据えた計画を立てることが重要です。NPS調査を効果的に活用し、顧客ロイヤルティ向上と事業成長につなげてください。
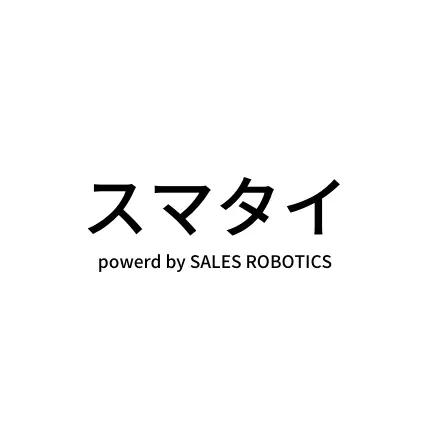
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
現在受付中のセミナー・イベントはありません。
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る