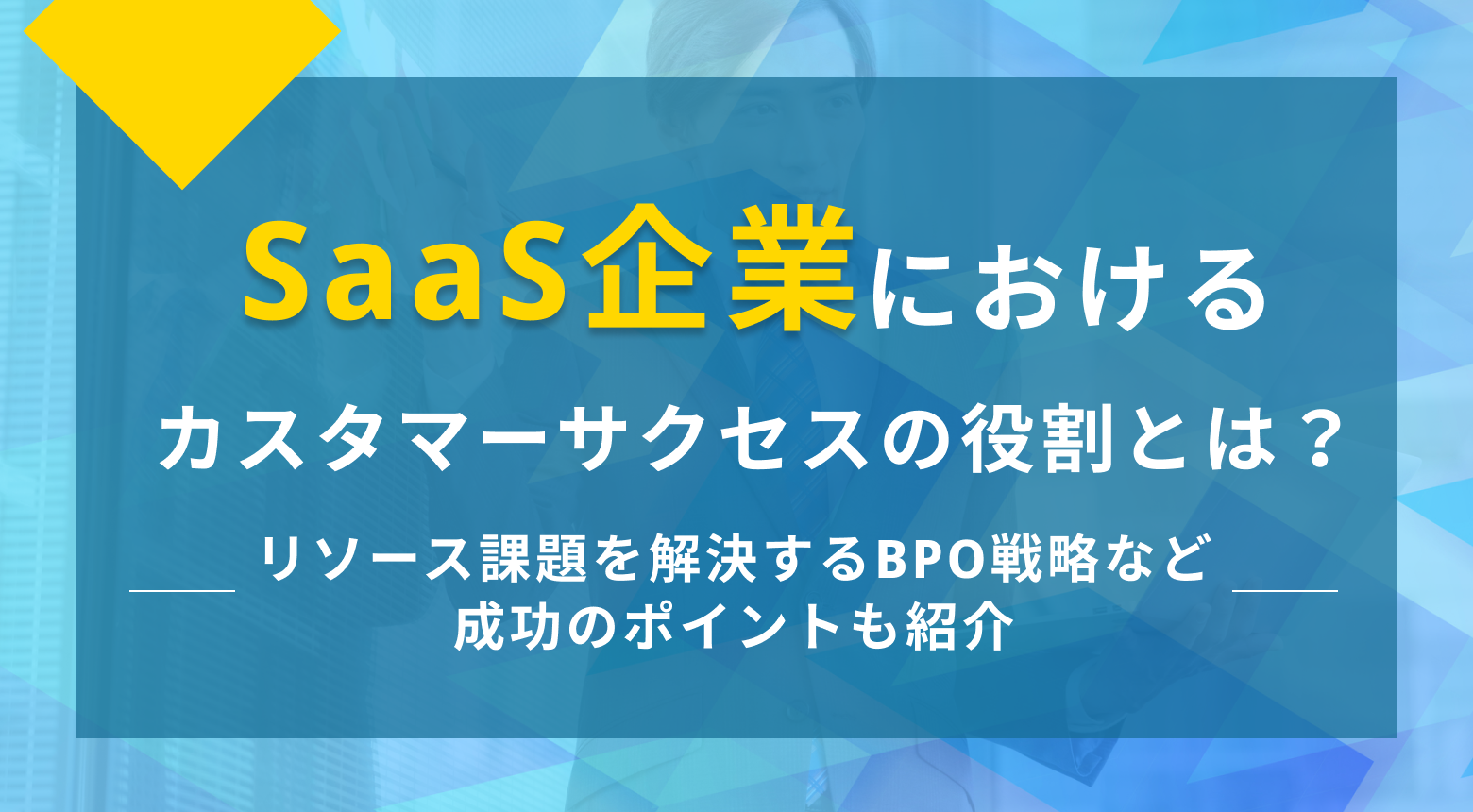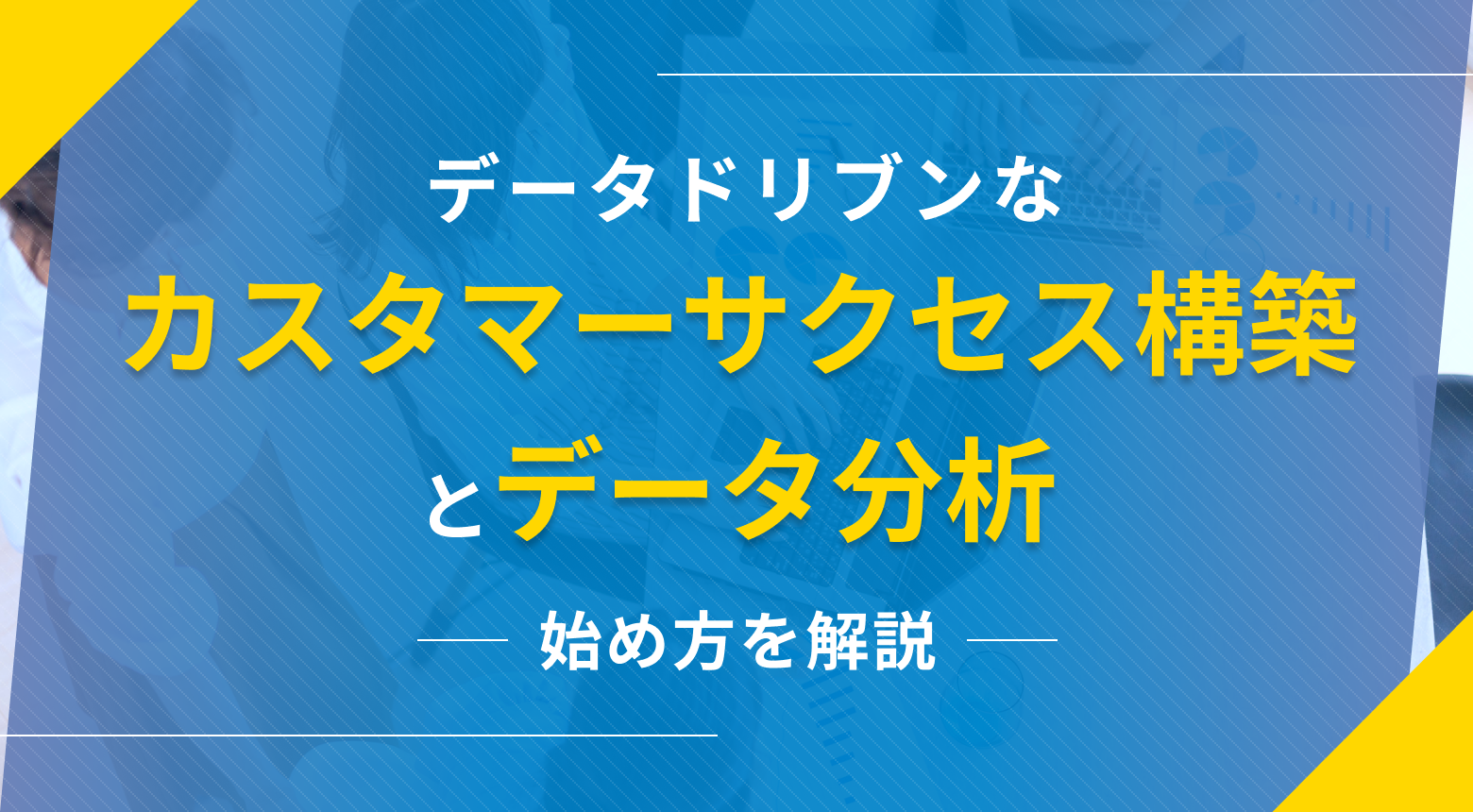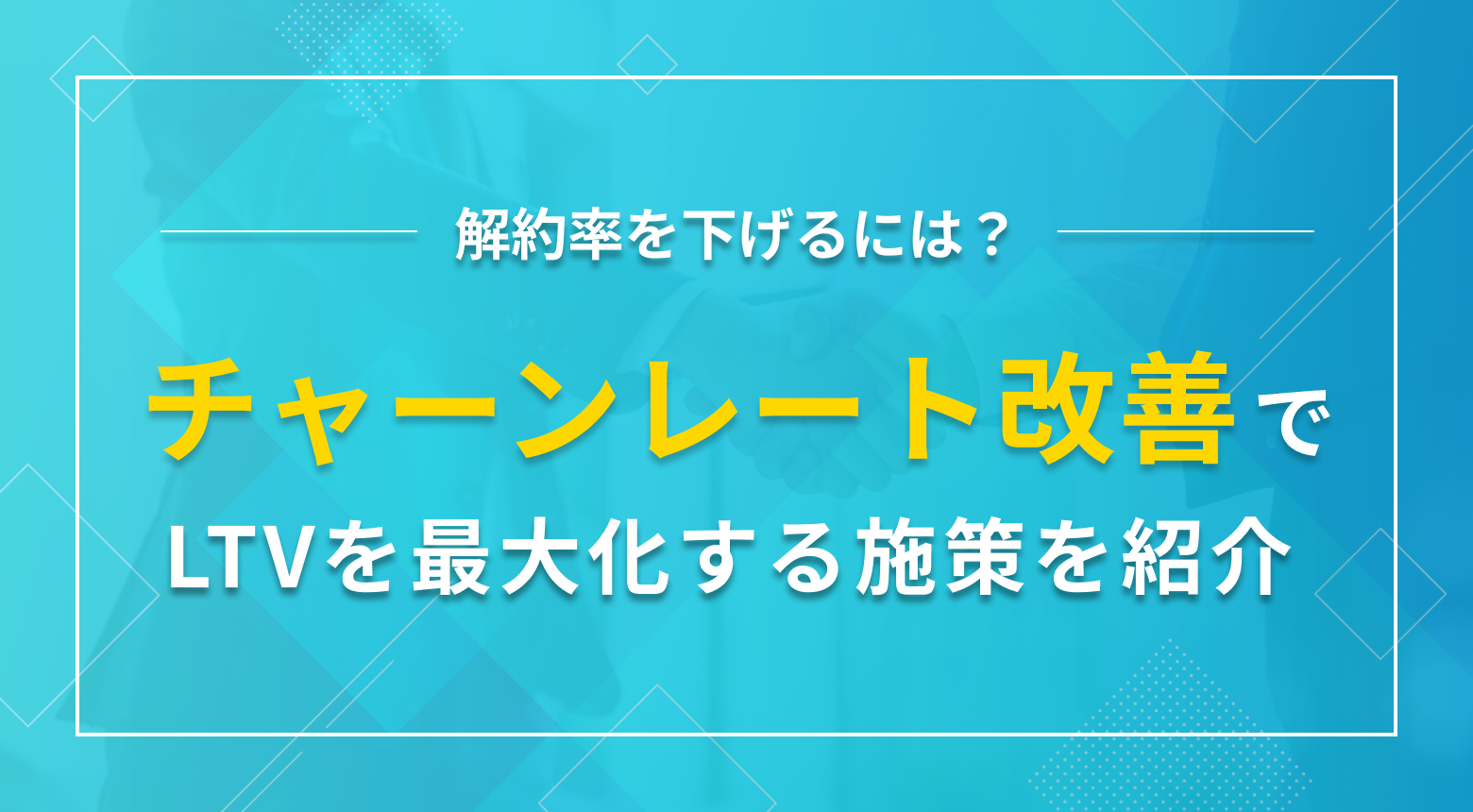カスタマーサクセスに活用するヘルススコアとは?重要性や導入ステップを解説
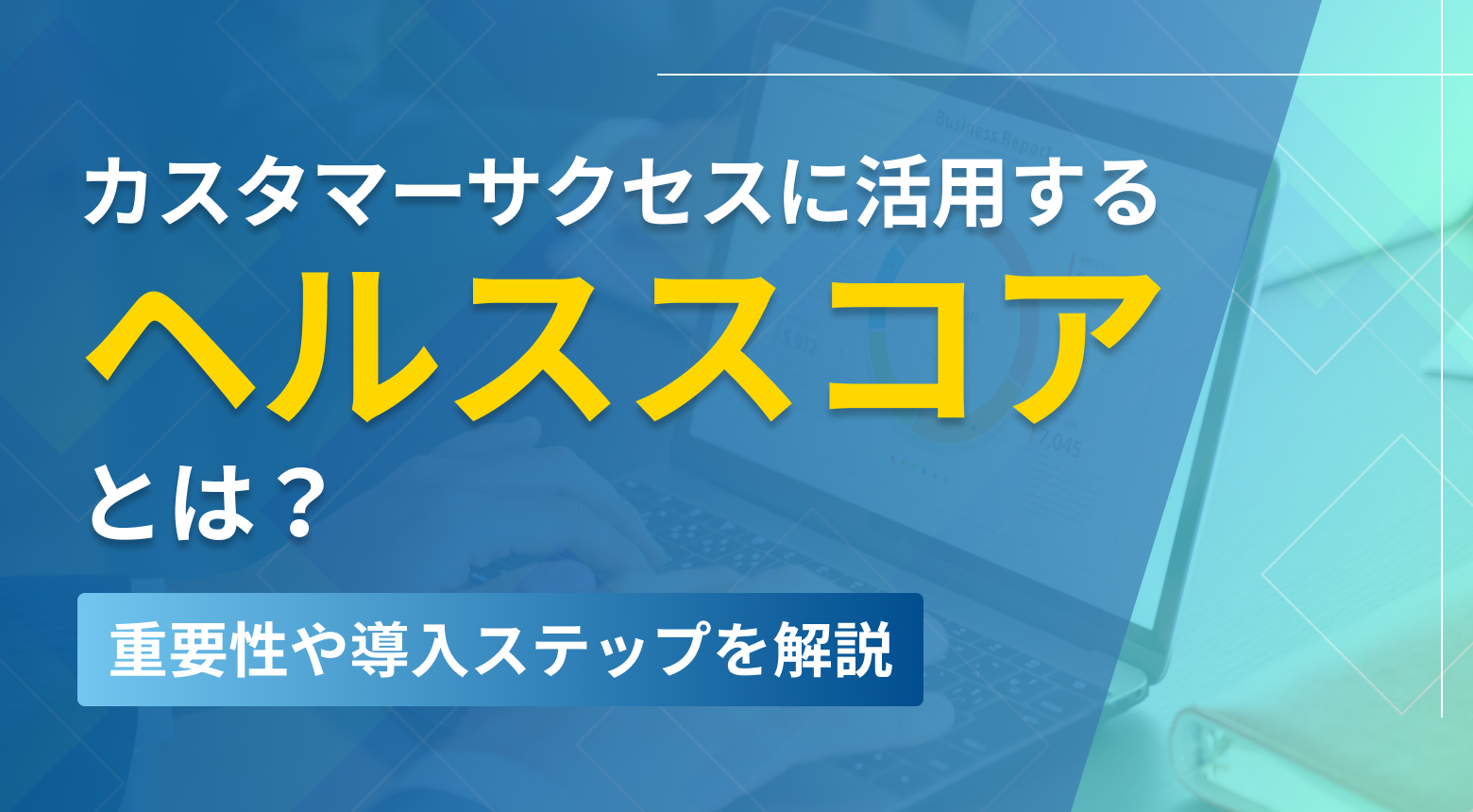
ヘルススコアとはカスタマーサクセスの指標のひとつで、顧客の活用レベルを数値化したものです。本記事では、ヘルススコアの重要性を解説します。
ヘルススコアの導入ステップも含めて詳細に解説します。導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
ヘルススコアとはカスタマーサクセスの指標のひとつ
ヘルススコアとはカスタマーサクセスの指標のひとつで、顧客の活用レベルを数値化したものです。これは、製品やサービス活用の定量的な把握により解約の兆候を早期に発見し、適切なサポートを提供するために重要です。
たとえば、ログイン頻度、利用機能数、特定機能の利用深度、サポートへの問い合わせ履歴などを点数化し、合計点が高いほど「健康な」顧客、低いほど「不健康な」顧客と判断します。
ヘルススコアのモニタリングにより、活用度が低い顧客へ積極的にオンボーディング支援を行うなど、先手を打ったアプローチが可能となります。
ヘルススコアの導入は、結果的に顧客満足度の向上と解約率の低減につながるといえるでしょう。
ヘルススコアに活用できるデータの例
ヘルススコアに活用されるデータは次の通りです。
| データ | 詳細 |
|---|---|
| サービス利用状況 | ・アカウント数 ・アクティブユーザー率 ・主な機能の利用状況 ・ログイン回数・頻度・時間 |
プロダクト活用状況 | ・サポート窓口の利用状況(問い合わせ件数・頻度) ・企業担当者との打ち合わせ件数・頻度 ・利活用セミナーなどの利用率、支援ツール(ユーザーガイド・FAQなど)の利用率 |
| 顧客満足度・ロイヤリティ | ・NPS®、CSAT(顧客満足度)、CES(顧客努力指標)、GCR(目標達成率) ・顧客コミュニティへの参加率、企業からのお知らせに対する反応率 |
ヘルススコアには、サービスやプロダクトの利用状況、サポートへの接触、顧客満足度、ロイヤリティといった多角的なデータが活用される傾向があるといえるでしょう。
なお、NPS®について確認したい方は「NPSとはどんな指標?顧客満足度との違いや測定方法を解説」を参考にしてください。
ヘルススコアに用いられる指標「DEAR」
ヘルススコアに用いられる指標としてGainsight社が提唱する「DEAR」モデルが挙げられます。「DEAR」モデルとは以下の頭文字を取ったヘルススコアのフレームワークです。
【DEARモデル】
- Deployment(導入):ユーザーは正しく利用開始できているか
- Engagement(関係性):ステークホルダーとエンゲージできているか
- Adoption(活用):製品を広く/深く活用してくれているか
- ROI(価値):製品の価値を感じているか
「DEAR」では、導入・関係性・活用・価値の4つの観点から顧客の健全性を網羅的に評価します。これにより、的確なサクセス活動につなげられるでしょう。
ヘルススコアが重要視される理由
ヘルススコアが重視される理由は以下の3点です。
【ヘルススコアが重要視される理由】
- 顧客の状況を定量的に把握できる
- 顧客の状況に応じた適切な対応ができる
- 効率的にカスタマーサクセス活動を行える
顧客の状況を定量的に把握できる
ヘルススコアが重要視される理由のひとつとして、顧客の状況を定量的に把握できる点が挙げられます。ヘルススコアで利用状況を数値化することで、顧客の課題やニーズを客観的に把握し、データに基づいた効果的な対応が可能になるからです。
たとえば、顧客がどの機能をどれくらい利用しているか、利用頻度や利用時間帯はどうかといったサービスの利用実態を数値で明確に把握できます。「サービスの利用率が低下している」といった曖昧な感覚ではなく、「特定機能の利用率が〇〇%低下している」という具体的なデータに基づいた顧客理解が可能になります。
また、ログイン頻度、特定の機能の利用深度、サポートへの問い合わせ頻度など、顧客がサービスに対してどの程度積極的に関わっているかを数値として評価できるのも大きな利点です。これらの数値は、顧客のエンゲージメント度合いを客観的に示す指標となるでしょう。
ヘルススコアを導入することで、データに基づいた顧客理解を深められ、より効果的な顧客サポートや、顧客満足度向上に向けた施策の立案・実行が可能になります。結果として、顧客一人ひとりの状況に合わせた最適なアプローチを導き出し、顧客ロイヤルティの向上につなげられるでしょう。
顧客の状況に応じた適切な対応ができる
ヘルススコアを導入すると、顧客の状況を的確に把握し、それぞれに応じた適切な対応ができるようになります。とくに、顧客の状況を可視化することで、より効果的な顧客体験を提供できるのです。
ヘルススコアは、顧客の製品利用状況、エンゲージメント、サポート利用履歴など、さまざまなデータを総合的に分析して数値化するものです。これにより、顧客が抱えている課題、製品やサービスを効果的に活用できているか、あるいは離反のリスクがあるかなどを客観的に判断できるようになります。
顧客がすでに製品やサービスから高い価値を得ている場合、さらに満足度を高める施策が有効です。ヘルススコアが高い顧客には、新機能の紹介やアップセル提案など、さらなる価値提供の機会を見つけられるでしょう。
一方で、ヘルススコアが低い顧客に対しては、早期に課題解決のためのサポートを提供したり、活用促進のための個別トレーニングを提案したりと、プロアクティブなアプローチが可能です。これにより、顧客の不満が大きくなる前に手を差し伸べ、離反を防ぐことができます。
このように、ヘルススコアを導入することで、企業は顧客一人ひとりの状態に合わせたパーソナライズされたアプローチを展開できます。結果的に顧客満足度の向上とLTVの最大化につながるでしょう。
なお、LTVを向上させるための施策について確認したい方は「LTVを向上させるための施策と成功に導くポイントを解説」を参考にしてください。
効率的にカスタマーサクセス活動を行える
ヘルススコアの活用により、カスタマーサクセス活動の効率化に大きく貢献します。限られたリソースを、どの顧客に、どのタイミングで投下すべきか、優先順位を判断するための客観的な指標となるからです。
例えば、前のセクションで述べたようなアプローチが必要な顧客をヘルススコアを基に特定できれば、全顧客に均一なアプローチをするのではなく、解約リスクの高い顧客のフォローや、アップセルの見込みがある優良顧客へのアプローチに活動を集中させることも可能になります。このように、ヘルススコアはカスタマーサクセス担当者の時間と労力を最適に配分し、活動全体の生産性を高めるための重要なツールとなるでしょう。
ヘルススコアの導入ステップ
ヘルススコアの導入ステップは以下の通りです。
【ヘルススコアの導入ステップ】
- 顧客の「健康な状態」を定義する
- 決定要素を決める
- 算出方法を決める
- スコアに応じて適したアクションを実行する
1.顧客の「健康な状態」を定義する
ヘルススコア導入の最初のステップは、顧客の「健康な状態」を明確に定義することです。
顧客の「健康な状態」は、顧客がサービスを深く活用し、その価値を実感している具体的な根拠となります。さらに、顧客のエンゲージメントを正確に把握し、効果的なカスタマーサクセス活動へとつなげるための揺るぎない基盤となります。
この「健康な状態」を定義するに先立ち、いくつか重要な準備があります。まず、顧客ライフサイクルの定義とカスタマージャーニーマップの作成が必要です。顧客が製品やサービスを導入してから解約に至るまでの道のりを明確にし、各フェーズで顧客がどのような体験をしているかを可視化することで、「健康な状態」の指標となる行動や状態を特定しやすくなります。
カスタマージャーニーマップの作り方を確認したい方は「カスタマージャーニーとは?マップの作り方や注意点を解説」を参考にしてください。
次に、解約原因の分析と成功シナリオの策定も重要です。過去の解約事例から、顧客がサービスを離れる主な理由を把握しましょう。一方で、サービスを継続的に利用し成功している顧客がどのような道のりを辿るのかを明確なシナリオとして描くことで、「健康な状態」の定義がより現実的で効果的なものになります。
最後に、ヘルススコア導入の目的とゴールの設定も重要です。ヘルススコアを導入することで何を達成したいのか、どのような課題を解決したいのかを明確にし、「健康な状態」の定義がその目的に合致したものとなります。たとえば、解約率の改善が目的なら、解約につながる兆候を捉えるための指標を「健康な状態」に含めるなど、目的に応じた調整が可能になります。
これらの準備を経て、「健康な状態」を定義するためには、顧客が製品やサービスをどのように活用し、どのような成果を得ているのかを詳細に言語化します。たとえば、SaaS企業の場合、単にログイン回数だけでなく、「特定の機能を週に3回以上利用している」「成功事例として他社への紹介に積極的に協力してくれる」といった具体的な行動を「健康な状態」として定義できます。
「健康な状態」の定義が明確であればあるほど、算出されるヘルススコアの精度は飛躍的に高まります。その結果、顧客の成功に直結する具体的なアクションを特定し、タイムリーに実行できるようになるでしょう。この初期段階の定義が、後のカスタマーサクセス活動全体の効果を大きく左右します。
2.決定要素を決める
次に、定義した「健康な状態」を測るための決定要素を決めることです。この要素を明確にすることで、ヘルススコアが客観的かつ測定可能な指標となり、顧客の状態を正確に把握できるようになります。
【決定要素の例】
- 特定の機能の利用時間/頻度
- ログイン頻度
- サポートへの問い合わせ回数
- 契約プランの利用状況
- アンケート回答率 など
たとえば、「特定の機能を週に3回以上利用している」ことを「健康な状態」と定義するなら、「機能の利用頻度」が重要な決定要素となります。
これらの決定要素は、顧客の活動状況や満足度を多角的に示すものであり、要素が多ければ多いほど、顧客の全体像をより正確に捉えることができるでしょう。決定要素を決めることで、データに基づいたより適切な顧客へのアプローチが可能になります。
3.算出方法を決める
ヘルススコア導入の3つ目のステップは、顧客の状態を正確に数値化するための算出方法を決定することです。決定要素に対して適切な算出方法を適用することで、顧客に対する具体的なアクションへとつながる、より意味のある指標となります。
たとえば、「ログイン頻度」「利用機能数」「サポート問い合わせ回数」といった決定要素がある場合、単純に各要素に点数を割り振って合計するだけでなく、それぞれの要素の重要度に応じて「加重平均」を採用するのが効果的です。「特定機能の利用」が顧客の成功に必要であれば、その要素の配点を高く設定することで、その重要性をスコアに反映させることができます。
また、解約リスクが非常に高い短期間での「複数回のクレーム」のように、ヘルススコアを大幅に減点する「トリガー」を設定することも有効です。これにより、緊急性の高い状況を迅速に察知し、対応を促すことができます。
このように、ビジネスの実態に合わせて算出方法を決定することで、ヘルススコアはより信頼性の高い指標となり、効果的なカスタマーサクセス戦略立案の強力な基盤となります。自社のビジネスにとって、最も適切で実用的な算出方法を検討することが、ヘルススコアを成功させる鍵となるでしょう。
4.スコアに応じて適したアクションを実行する
ヘルススコア導入の4つ目のステップは、算出されたスコアに基づき顧客をセグメント化し、それぞれに適したアクションプランを実行することです。これにより、顧客の状態に合わせた戦略的なアプローチを展開し、カスタマーサクセス活動の効果を最大化できます。
たとえば、ヘルススコアが低い顧客は解約リスクが高いと判断できるため、早急にリスクを特定し、より手厚いサポートや詳細なヒアリングを実施する必要があるでしょう。彼らの課題を深く理解し、解決策を提供することで、解約を防ぎ顧客満足度を向上させられます。
このスコアに基づいたセグメント化は、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチといったアプローチにつながります。
カスタマーサクセスのタッチモデルについて確認したい方は、「カスタマーサクセスのタッチモデルとは?4つの分類とアプローチ方法を解説」を参考にしてください。
ハイタッチは、ヘルススコアが特に低い、あるいは非常に重要な大口顧客に対して行われる、個別の手厚いサポートです。専任のカスタマーサクセスマネージャーがつき、定期的なミーティングや個別相談を通じて、顧客の課題解決に深くコミットします。これは、解約リスクの高い顧客を救済したり、トップティアの顧客の満足度をさらに高めたりするために効果的です。
ロータッチは、中程度のヘルススコアを持つ顧客や、ある程度の顧客数を抱える場合に採用されるアプローチです。個別対応に加えて、ウェビナーの開催、特定機能の活用ガイドの提供、ターゲットを絞ったメールキャンペーンなどを活用し、効率的に多くの顧客をサポートします。
テックタッチは、ヘルススコアが高い多数の顧客や、セルフサービスで解決できる課題が多い顧客に対して行われる、テクノロジーを活用した自動化されたアプローチです。FAQページの充実、チュートリアル動画の提供、インプロダクトメッセージ(製品内のメッセージ)などを用いて、顧客が自力で問題を解決できるよう支援します。これにより、カスタマーサクセスチームはより手厚い対応が必要なハイタッチやロータッチの顧客に注力できます。
一方で、ヘルススコアが高い顧客は、製品やサービスを順調に活用し、高い満足度を得ていると考えられます。こうした顧客に対しては、アップセルやクロスセルの提案を行うことで、さらなる価値提供と収益拡大につなげられます。また、彼らに成功事例の発信を依頼することで、新たな顧客獲得のための強力な証言を得ることも可能です。
このように、ヘルススコアによって明確になった顧客の状態に応じて適切なアクションを実行します。設定した閾値を活用してその効果を検証し、継続的に改善していくようにしましょう。
ヘルススコアを運用する際の注意点
顧客の状況を定量的に把握し、適切なカスタマーサクセス活動を効率的に行う上で、ヘルススコアは有効です。しかしながら、その効果を引き出すためには、以下の点に留意して運用する必要があります。
【ヘルススコア運用の注意点】
- 精度と信頼性の担保
- 運用の効率化
- 継続的な改善
ヘルススコアの精度と信頼性に関する注意点
ヘルススコアの精度と信頼性に関する注意点は以下の2点です。
- スコアの妥当性の判断の難しさ
- 決定要素の明確化と多角的な評価
これらの注意点から、ヘルススコアの精度と信頼性を確保するには、客観的で多角的な指標設定が必要であり、その妥当性を継続的に評価する仕組みが重要であるといえるでしょう。
スコアの妥当性の判断の難しさ
ヘルススコアの算出基準や運用方法が不明確な場合、同じ顧客であっても担当者によってスコアが異なったり、スコアの変動理由が曖昧になったりする可能性があります。ヘルススコアは、顧客の活動状況を数値化する指標ですが、全ての要素を定量的に測定できない場合や、データ量が不足している場合、担当者が過去の経験や感覚に基づいてスコアを調整してしまうことがあるからです。
たとえば、特定の顧客に対して個人的な感情が入ってしまい、実際よりも良く評価したり、逆に厳しく評価したりすることもあるかもしれません。また、担当者によっては「頻繁にミーティングに参加してくれるから、エンゲージメントが高い顧客だ」と判断し、データからは読み取れない高めのスコアをつけてしまうケースも考えられます。
主観的な判断が積み重なると、ヘルススコア全体の信頼性が低下し、本来の目的である「効率的かつ客観的な顧客状態の把握」が困難になり、データに基づいた適切なアクションが行われず、カスタマーサクセス活動の効果が薄れてしまう可能性があります。
ヘルススコアの客観性と信頼性を確保するためにも、算出方法の明確化と定期的な見直しを行うようにしましょう。
決定要素の明確化と多角的な評価
ヘルススコアの精度と信頼性を高めるためには、導入ステップの初期段階で定義した顧客の「健康な状態」を構成する決定要素を明確にすることが必要です。単に感覚的な評価に頼るのではなく、具体的な数値や行動に基づいた指標を設定することで、顧客の状態をより正確に把握できるようになります。
たとえば、ログイン頻度、特定の機能の利用率、サポートへの問い合わせ回数、アップセル・クロスセル率、NPS(ネットプロモーター スコア)など、多角的な視点からデータを収集しましょう。それぞれの指標がヘルススコアに与える影響度を適切に評価することが重要です。
一方向からの情報だけでなく、様々な側面から顧客の「健康な状態」を総合的に判断できるようになり、ヘルススコアの信頼性が飛躍的に向上するでしょう。
ヘルススコア運用の効率性に関する注意点
ヘルススコア運用の効率性に関する注意点に関する注意点は以下の2点です。
- スコア更新に要する時間とリソース
- 自動化の必要性とツールの活用
ヘルススコアを効果的に運用するためには、その効率性にも注意を払う必要があります。特に、リソースが限定的な企業においては、すべての指標を完璧に追うことは現実的ではありません。限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、優先順位をつけ、スマートなアプローチを選択することが重要であるといえるでしょう。
ヘルススコアでは見えにくい顧客の深層的なニーズや課題を把握する上で貴重な手がかりとなります。
スコア更新に要する時間とリソース
ヘルススコアを運用する上で、スコアの管理が手動になる可能性があることに留意しましょう。ヘルススコアを完全に自動化できない場合、その算出と更新には手作業が伴い、時間と労力がかかります。
ヘルススコアの決定要素には、ログイン頻度や利用機能などシステムデータから自動取得できるものと、顧客との商談内容や感情的なフィードバック、アンケートの自由記述欄など、人の介在が必要なデータがあります。特に人の介在が必要な定性的な情報は、システム連携が難しい場合が多く、手動での入力や更新が必要となるため、運用負荷がかかることが想定されます。
たとえば、顧客のサービスへの満足度を測るために、営業担当者やカスタマーサクセス担当者が顧客との会話から得た印象や個別のフィードバックシートをヘルススコアに反映させたい場合、担当者が定期的にスコアシートを更新したり、個別のコメントを手動で追記したりする作業が発生します。
これにより、データ入力の手間に加え、入力漏れや更新忘れなどヒューマンエラーのリスクが生じ、スコアの鮮度や正確性が損なわれる可能性があります。結果としてデータ収集や入力作業が目的化してしまい、本来のカスタマーサクセス活動に割ける時間が減少してしまう可能性もあります。
ヘルススコアは、設計段階でどの要素が手動管理になるかを把握し、運用コストと得られるメリットを慎重に比較検討することが、持続可能なカスタマーサクセス運用に必要です。
【リソースが限られている場合のヘルススコア活用術】
まず、ログイン状況の把握は、最も基本的でありながら重要な指標です。ログイン頻度や最終ログイン日時を継続的にモニタリングすることで、顧客のエンゲージメント低下の兆候をいち早く察知できます。このシンプルな指標からでも、顧客がサービスから離れつつある可能性を推測し、早期のフォローアップにつなげることが可能です。
次に、スイッチングコストが高い機能の利用把握に注力しましょう。顧客が一度使い始めると他のサービスへの乗り換えが難しくなるような、大量のデータ蓄積が必要な機能、他社連携が複雑な機能など特定の重要機能の利用状況を優先して把握します。これらの機能が活用されていれば、顧客がサービスに定着している可能性が高く、ヘルススコアの重要な代替指標となります。
ヘルススコアが不完全であっても、オンボーディングプログラムの磨き上げは顧客の成功を最大化するために非常に有効です。導入初期の体験が顧客の継続利用に大きく影響するため、オンボーディングプログラムを継続的に改善し、その効果を測定することで、顧客がサービスから最大の価値を引き出せるよう支援します。初期段階での成功体験は、その後の良好な関係を築く上で重要です。
最後に、リソースが限られる中で、特にハイタッチ顧客への注力は効率的な戦略となります。LTV(顧客生涯価値)の高いハイタッチ顧客層に優先的にリソースを配分し、密なコミュニケーションを通じてヘルススコアの補完情報を得るアプローチです。個別の対話を通じて得られる定性的な情報は、定量的なヘルススコアでは見えにくい顧客の真相的なニーズや課題を把握する上で貴重な手がかりとなります。
自動化の必要性とツールの活用
ヘルススコアの運用を続けていくと、顧客数が増えるにつれてデータ収集や分析に膨大なリソースが必要となります。手作業で全ての顧客のヘルススコアを算出し、管理していくのは現実的ではないでしょう。そこで重要になるのが、自動化とカスタマーサクセスツールの活用です。
カスタマーサクセスツールを導入することで、ヘルススコアの算出に必要なデータの収集から分析までを自動化できます。これまでデータ作業に費やしていた時間を大幅に削減し、その分のリソースを実践的な顧客対応に充てられるようになるでしょう。たとえば、ヘルススコアが低い顧客へのフォローアップや、エンゲージメントの高い顧客へのアップセル・クロスセル提案など、より戦略的な活動に集中できるようになります。
ヘルススコアの運用においてツールの活用は、ヘルススコア運用の効率性を飛躍的に高め、カスタマーサクセス活動全体の質を向上させるために必要になります。
ツールの選び方を確認したい方は「【目的別】カスタマーサクセスツール19選を選び方とともに解説」を参考にしてください。
ヘルススコアの継続的改善に関する注意点
ヘルススコアは一度導入すれば終わりではありません。顧客の状態や市場の変化に合わせて、継続的に改善していく必要があります。ヘルススコアの継続的改善に関する注意点は以下の3点です。
- PDCAサイクルの重要性
- スコア基準のメンテナンスの必要性
- 重要指標との連動とスモールスタート
これらの注意点から、ヘルススコアの精度と信頼性を確保するには、継続的な改善と指標の最適化が重要であり、初期は主要指標に絞って小さく始めることが必要です。
PDCAサイクルの重要性
ヘルススコアの運用において、PDCAサイクルを継続的に回すことは重要です。
ヘルススコアの設計段階で立てた仮説(Plan)に基づき、実際にスコアを算出し、アクションを実行(Do)します。その後、そのアクションが顧客の状態やビジネス目標にどのような影響を与えたかを評価(Check)し、その結果をヘルススコアの設計や運用にフィードバックして改善(Action)につなげていくのです。
このサイクルを繰り返すことで、ヘルススコアの精度は高まり、より効果的なカスタマーサクセス活動を実現できるでしょう。
スコア基準のメンテナンスの必要性
ヘルススコアは、一度設定したら終わりではなく、顧客の状況やビジネスの変化に合わせて定期的に見直し、更新していくことも重要です。
顧客ニーズやビジネス環境の変化、さらに製品アップデートや新機能追加によって、製品やサービスの利用状況、そして顧客が求める価値は常に変化します。これに伴い、顧客の「健康な状態」や、それを測るため「決定要素」の重要度も変動します。ヘルススコアを固定してしまうと、変化を捉えきれず、現状にそぐわない指標となるリスクがあるからです。
たとえば、導入当初は「ログイン頻度」が重要な要素だったとしても、顧客が特定の機能を使いこなすことで、ログイン頻度以外の「機能利用率」がより重要な指標となる場合があります。また、競合の出現や市場トレンドの変化により、顧客がプロダクトに求める成果が変化し、「健康な状態」の定義自体を見直す必要が出てくるかもしれません。
古いスコア基準を使い続けると、リスクを抱えている顧客を見逃したり、逆に順調な顧客に不必要なアプローチをしてしまったりと、カスタマーサクセス活動が非効率になるだけでなく、顧客との関係性悪化にもつながりかねません。
定期的にヘルススコアの決定要素や算出方法を見直し、顧客の現状に即した形に調整することが不可欠といえるでしょう。
重要指標との連動とスモールスタート
ヘルススコアを運用する上で、効果を実感しやすいのが、チャーンレート(解約率)と顧客単価(MRR/ARR)という2つの重要指標との連動です。ヘルススコアの向上がこれらの結果指標の改善に直結するというロジックを確立することが非常に重要となります。
たとえば、ヘルススコアが高い顧客群のチャーンレートが低い、あるいは顧客単価が高いといった相関関係を明確にすることで、ヘルススコア運用の意義が社内外に示しやすくなります。
チャーンレートと顧客単価の関係性を明確にするためには、最初から完璧なヘルススコアを目指すのではなく、スモールスタートが良いでしょう。まずは主要な数値を基にシンプルなヘルススコアを設計し、運用しながらその効果を検証します。そこから得られたフィードバックを元に、徐々に指標の追加や重み付けの調整を行い、より精度と信頼性の高いヘルススコアへと改善していくのが効率的です。
重要指標との連動とスモールスタートにより、限られたリソースでも着実に成果を出し、ヘルススコア運用の成功体験を積み重ねることができるでしょう。
まとめ
ヘルススコアは、あくまでカスタマーサクセスを実現するための指標であり、数値を高めること自体が目的ではないという点を常に意識しながら運用することが重要です。ヘルススコアは、「DEARモデル」という指標を用い、顧客の導入状況、関係性、活用状況、価値の4つの観点から健全性を評価できます。
ヘルススコアの導入ステップは以下の通りです。
- 顧客の「健康な状態」を定義する
- 決定要素を決める
- 算出方法を決める
- スコアに応じて適したアクションを実行する
運用時の注意点は以下の通りです。
【ヘルススコア運用の注意点】
- 精度と信頼性の担保
- 運用の効率化
- 継続的な改善
このように、ヘルススコアは顧客の状況を定量的に把握し、適切なタイミングで効果的なアプローチを行うための強力な手段となります。その結果、顧客満足度の向上や解約率の低減につながり、カスタマーサクセス活動を効率的に行う上で不可欠な指標といえるでしょう。
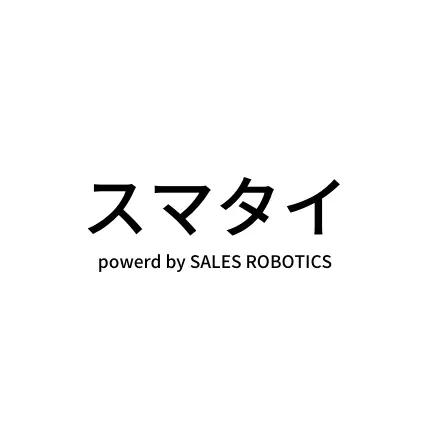
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
現在受付中のセミナー・イベントはありません。
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る