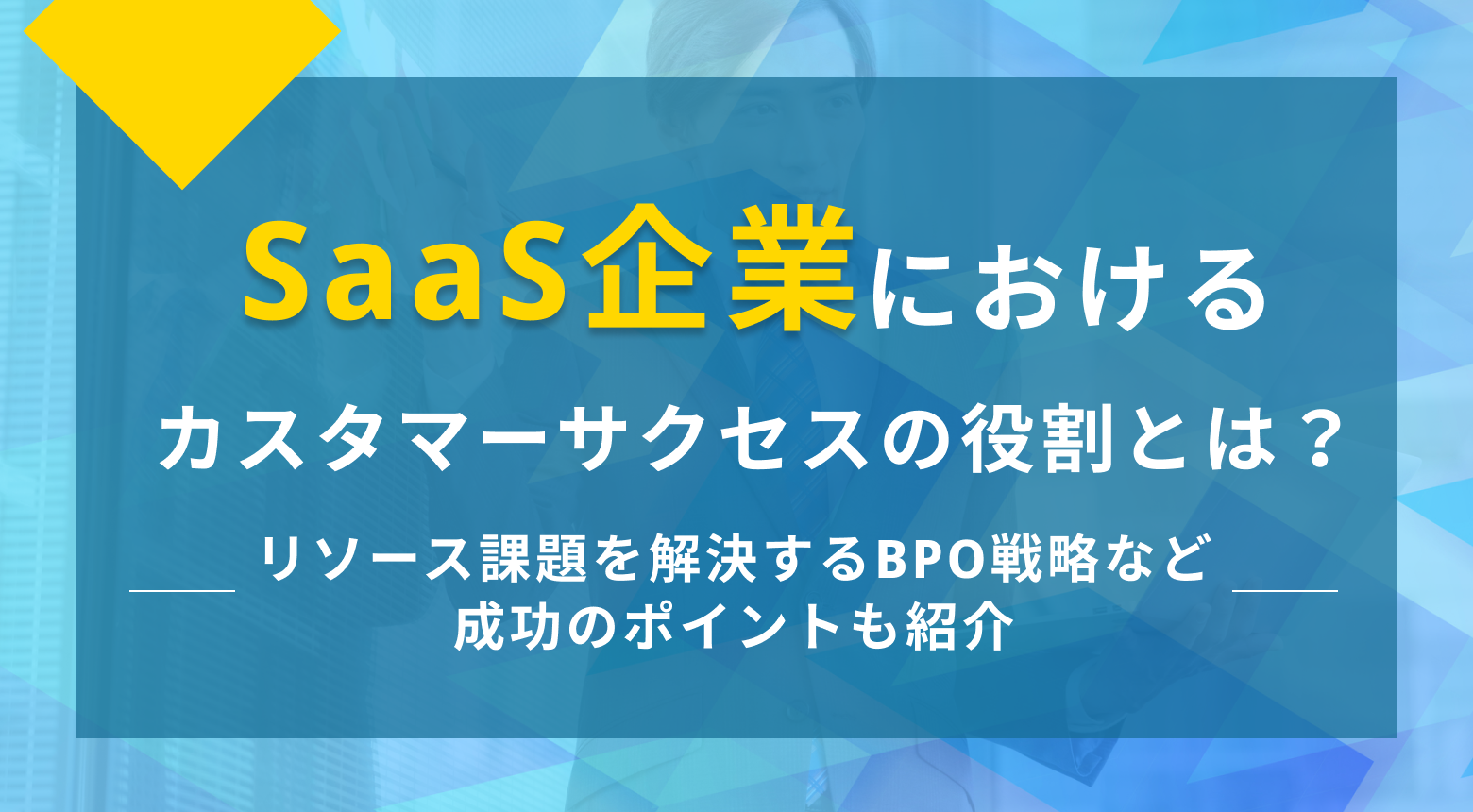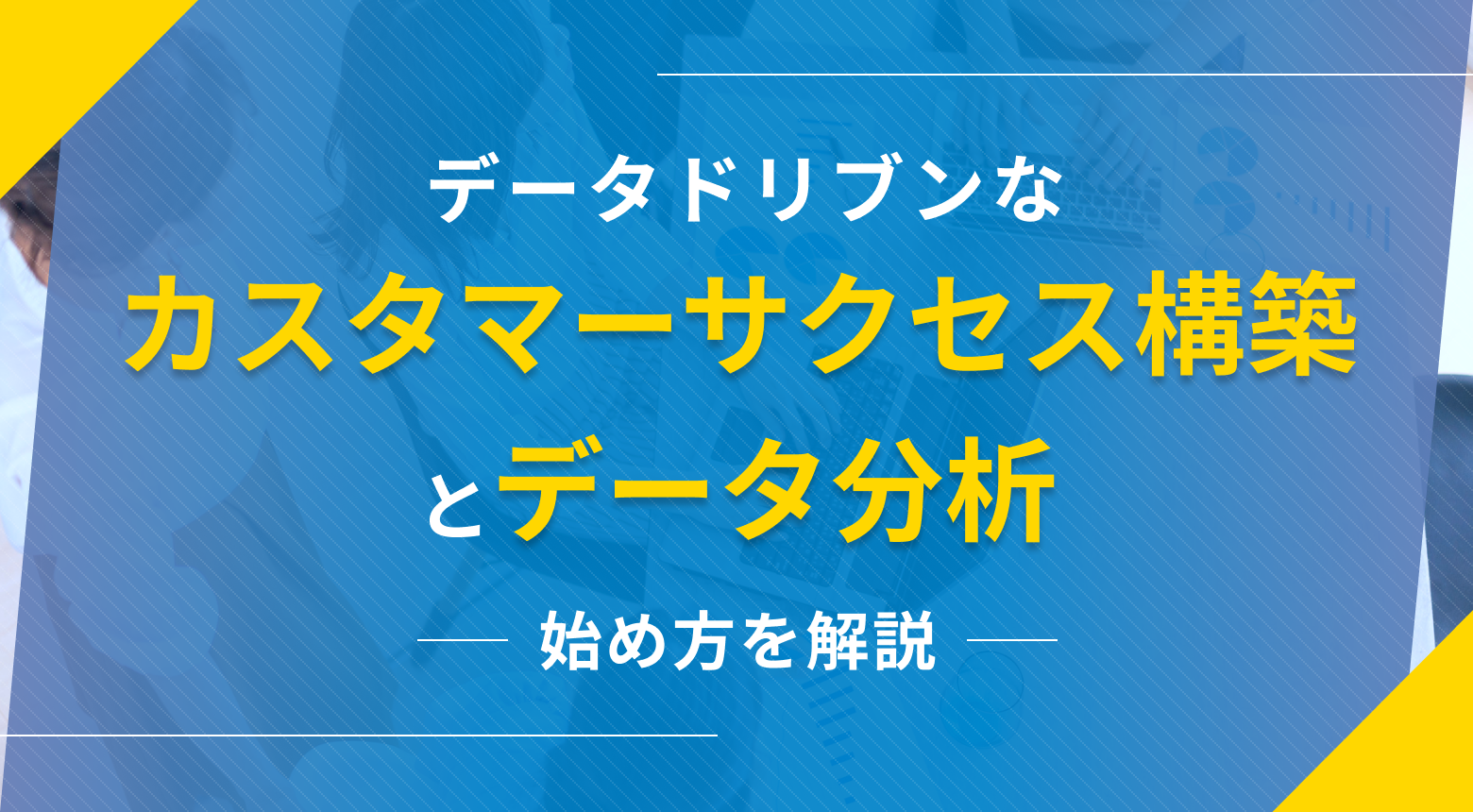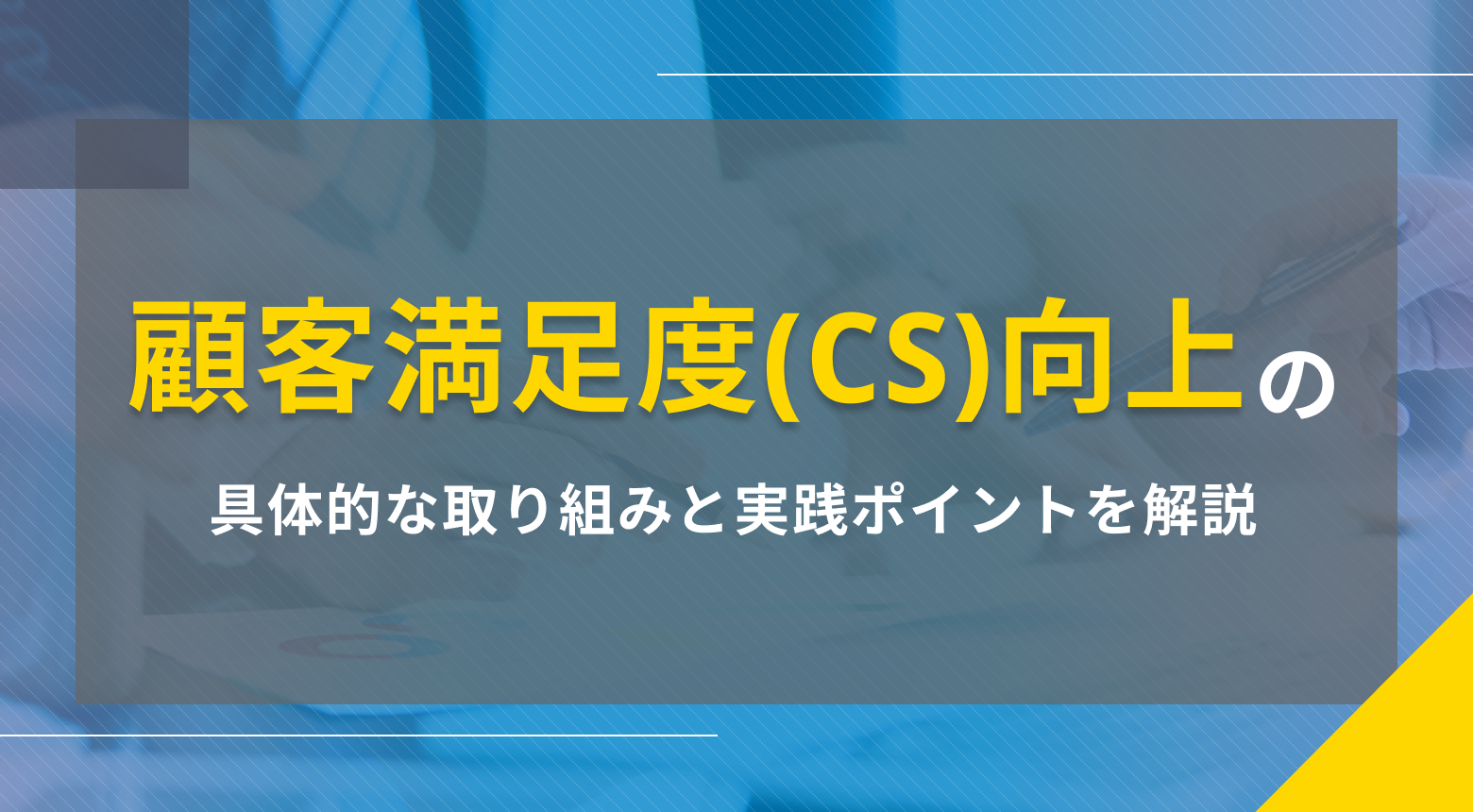解約率を下げるには?チャーンレート改善でLTVを最大化する施策を紹介
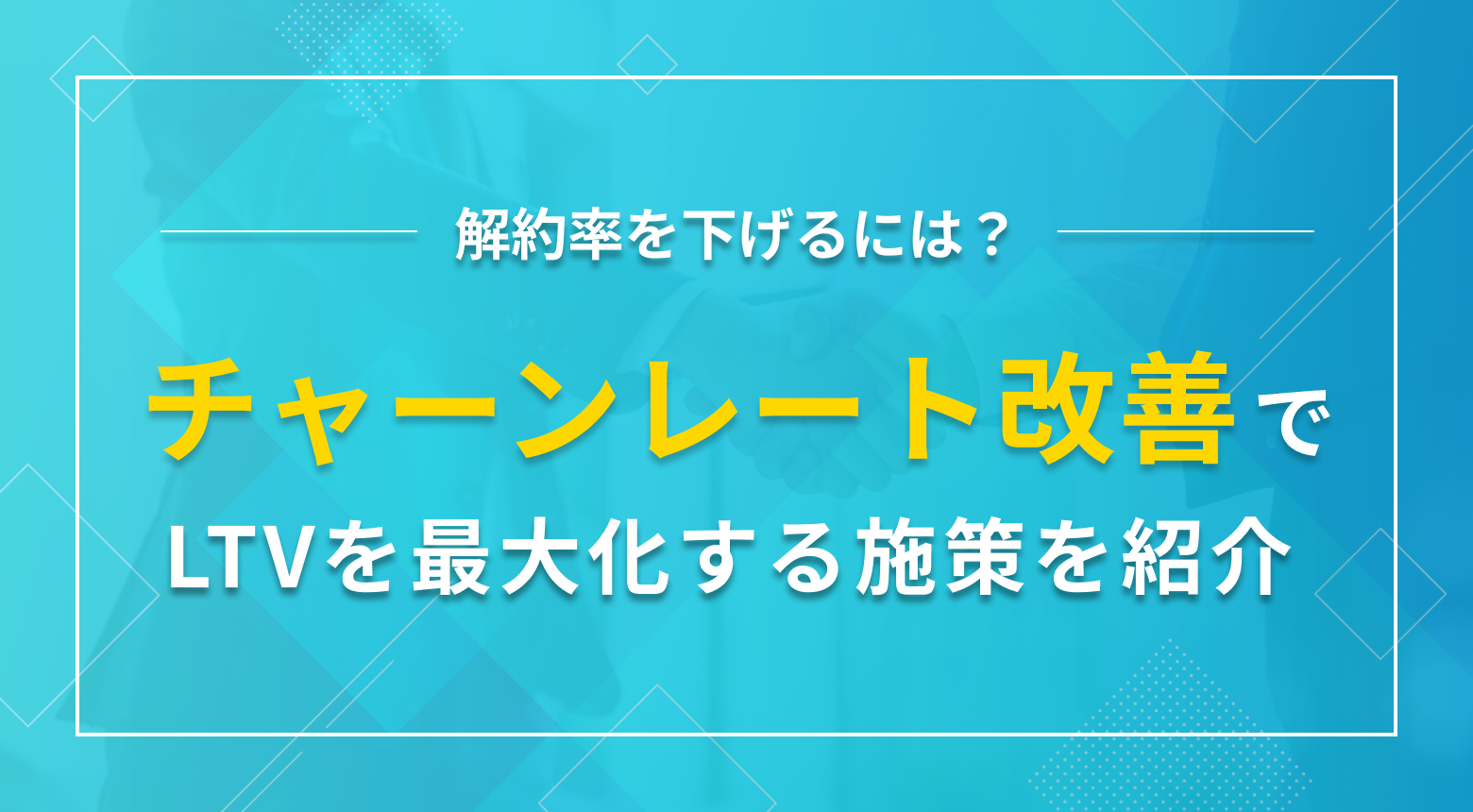
解約率(チャーンレート)は顧客維持の状況を評価し、ビジネスの健全性を判断する指標です。当記事では、顧客離反の原因が分からず、手詰まりを感じている企業に向け、解約率を下げるための具体的な改善策を解説します。
自社サービスの解約を下げ、結果的に事業全体の収益向上と安定的な成長につなげていきましょう。
解約率の定義と正しい計算方法
解約率(チャーンレート)は、一定期間内に製品やサービスの利用を解約した顧客の割合を示す指標です。解約率を正しく理解することで、顧客維持の状況を正確に把握し、事業成長に向けた具体的な改善策を検討できるようになります。
解約率の算出には、一般的に「カスタマーチャーンレート」という計算方法が用いられます。その計算式は以下の通りです。
| 解約率(%)=(期間中に解約した顧客数 ÷ 期間開始時点の顧客数)× 100 |
たとえば、あるサービスにおいて、月の初めに1,000人のユーザーがいて、同月に100人のユーザーがサービスを解約した場合を考えてみましょう。この場合の解約率は、(100人 ÷ 1,000人) × 100 = 10% となります。
ただし、新規顧客が急増している期間は、この計算式で見かけ上の解約率が低く見える場合がある点には注意が必要です。分母となる「期間開始時点の顧客数」が大幅に増えるため、実際の解約数に対して解約率が過小評価される可能性があります。
解約率を正しく把握することは、自社のサービスが顧客にどれだけ継続して利用されているかを測るバロメーターであり、顧客満足度の向上やサービス改善の出発点となるでしょう。
解約率が重要視される理由
解約率が重要視される理由として以下の4点が考えられます。
- サブスクリプション型ビジネスモデルの成功条件
- 新規顧客よりもコストが低い
- 市場での競合優位性
- LTVの向上に関わる
サブスクリプション型ビジネスモデルの成功条件
解約率の低減は、サブスクリプション型ビジネスモデルの成功において不可欠な条件です。サブスクリプション型ビジネスモデルは、顧客からの継続的な収益を前提としており、顧客の継続利用が事業成功に繋がるためです。
新規顧客の獲得には多大なコストがかかります。顧客が短期間で解約してしまえば、新規顧客獲得にかかった費用を回収できず、事業は赤字に陥ってしまいます。しかし、顧客に長く継続して利用してもらえれば、新規獲得費用を上回り、大きな利益を生み出すことが可能になります。
サブスクリプション型ビジネスモデルにおいて、解約率は単なる指標ではありません。顧客との長期的な関係を構築し、安定した収益を確保するためには、解約率を低く保つことが絶対条件といえるでしょう。
新規顧客よりもコストが低い
顧客の解約率を低く抑えることは、効率的に収益を確保し、企業の利益率を向上させることに直結します。一般的に、顧客獲得コスト(CAC)は、既存顧客を維持するためのコストよりも高くつく傾向があるからです。
既存顧客は、すでに自社のサービスやブランドを認知しており、ある程度の信頼関係が築かれている傾向があります。そのため、顧客との関係を維持するためのマーケティング費用や営業工数が少なくて済みます。実際に、新規顧客の獲得は、既存顧客維持の5倍のコストがかかるともいわれています。
解約率を低く抑えることは、新規顧客獲得に注力するよりも、はるかに経済的で効率的な成長戦略であるといえるでしょう。
市場での競合優位性
解約率が低いことは、市場における競合優位性を確立する上で重要です。解約率が低いということは、顧客が提供しているサービスに高い満足度を感じ、競合他社へ乗り換えることなく継続して利用していることを明確に示しているからです。
解約率が低いと、収益が安定するだけでなく、ブランドの信頼性や製品・サービスの質の高さを証明する強力なシグナルにもなります。特に競合他社が多い市場では、既存顧客をしっかりと囲い込み、高い顧客維持率を誇る企業は、新規顧客獲得の際にも「多くの顧客に選ばれ続けている」という信頼性を強くアピールできます。
低い解約率は、単なる顧客維持に留まらず、企業のブランド価値を高め、市場での確固たる地位を築く上で不可欠な要素といえるでしょう。
LTVの向上に関わる
解約率が低い状態を維持することは、顧客のLTV向上に直結します。 LTVの向上は、顧客獲得コスト(CAC)を効率的に回収し、さらにその顧客から長期的に利益を得ることに繋がります。
解約率が低いということは、顧客がサービスを長く継続して利用してくれることを意味します。顧客が長く留まるほど、その顧客から得られる総収益は増加し、結果としてLTVが向上します。
LTVが高ければ高いほど、企業は健全な経営状態を保ちやすくなります。たとえば、一人の顧客から得られる価値が大きければ、新規顧客獲得にかかる費用をより効率的に回収できます。さらに、回収した資金を新たな投資やサービス改善に回すことも可能になり、事業のさらなる成長を促進できるでしょう。
企業収益の最大化において重要なのが、「5:25の法則」です。「5:25の法則」は、顧客離れを5%改善することで、利益が25%以上改善される可能性があるという経験則です。新規顧客の獲得には多大なコストがかかりますが、既存顧客の維持は、はるかに少ないコストで済みます。この法則が示すように、解約率をわずかでも改善できれば、その経済的インパクトは非常に大きいのです。
解約率を下げてLTVを最大化することは、企業の持続的な成長において重要な要素となります。
LTVを向上させるための施策について確認したい方は、「LTVを向上させるための施策と成功に導くポイントを解説」を参考にしてください。
解約の根本原因を見つけ出す方法
解約の根本原因を見つけ出す方法はおもに以下の4つです。
- 顧客の声から解約理由を深掘りする
- 解約リスクの高い顧客を特定する
- 顧客の期待と提供サービスのギャップを測る
- コホート分析で解約パターンを掴む
顧客の声から解約理由を深掘りする
解約の根本原因を見つけ出すには、顧客の声(VOC)から解約理由の核心を把握する方法が有効です。顧客の声を収集し、分析することで、顧客がサービスに対して抱いている具体的な不満点を特定できるからです。
たとえば、機能が不足している、サポート体制に不満がある、料金設定が他社と比較して高すぎるといった、具体的な不満点が明らかになることがあります。これらの不満点は、アンケート調査、顧客へのヒアリング、SNS上のコメント分析など、さまざまなチャネルから収集できます。顧客がどのような点でつまずき、サービスから離れてしまったのかを詳細に理解することで、漠然とした課題ではなく、真のニーズを把握できます。
他にも、解約理由を深掘りする手法には、以下があります。これらの手法を組み合わせることで、解約に至る前の兆候や、具体的な原因を多角的に捉えることが可能になります。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| 離脱時アンケートの設置 | 解約直後の顧客から直接的な理由を収集する |
| NPS調査の定期実施 | 顧客ロイヤルティを測り、潜在的な不満を持つ顧客を特定する |
| カスタマーサポートの問い合わせログ分析 | 頻繁な問い合わせ内容から共通の課題や不満点を洗い出す |
顧客の声から解約理由を深掘りすることは、表面的な問題解決に留まらず、サービスの改善策を具体的に立案し、顧客満足度を向上させるための重要なステップとなります。
なお、顧客の声のVOCの具体的な収集方法を確認したい方は、「VOC分析を導入するべき企業の特徴や収集方法を解説」を参考にしてください。
解約リスクの高い顧客を特定する
解約率を下げるためには、解約の根本原因を見つけ出し、事前の対策を講じることが重要です。ほとんどの場合、顧客の解約は突然起こるのではなく、事前に何らかの予兆があるからです。
たとえば、サービスのログイン頻度が低下したり、特定の重要な機能が全く使用されなくなったりするといった行動は、解約の強い予兆となる可能性があります。 加えて、サポートへの問い合わせが急増したり、現在のプランからのダウングレードを検討し始めたりするといった兆候も、顧客がサービスへの不満を抱えているサインかもしれません。また、顧客の全体的な利用頻度やエンゲージメントの低下を見逃さないようにすることも有効です。
これらの予兆を捉えるためには、顧客行動データに基づいた分析が不可欠です。顧客がどのような行動パターンで解約に至るのかを把握し、リスクの高い顧客を早期に特定する仕組みを構築しましょう。顧客が完全に離れてしまう前に適切なアプローチを行うことで、解約を防ぐ可能性を高められるでしょう。
顧客の期待と提供サービスのギャップを測る
顧客の期待と実際に提供しているサービスの間にギャップがある場合、解約の原因となる可能性があります。顧客は、サービスを購入したり利用したりする際に、少なからず特定の期待を抱いています。その期待が満たされないと不満が生じ、結果として解約へとつながる傾向があるためです。
たとえば、サービスの機能に不具合が頻繁に発生したり、インターフェースが使いにくかったり、カスタマーサポートの対応が遅かったりといった具体的な問題が、顧客の期待と提供サービスのギャップとして挙げられます。
顧客の期待と提供サービスのギャップを特定し、改善するためには、定期的なフィードバックの収集とNPS調査が有効です。これらの活動を通じて顧客の生の声を聞き、期待と現実のずれを解消していくことが、解約率を下げるための重要な一歩となります。
なお、NPSの調査方法を確認したい方は、「NPSとはどんな指標?顧客満足度との違いや測定方法を解説」を参考にしてください。
コホート分析で解約パターンを掴む
解約の根本原因を探る手段として、「コホート分析」も有効です。「コホート分析」は、顧客を契約時期などの共通項でグループ分けし、その後の解約率の推移を追跡するデータ分析手法です。
全体の解約率だけを見るだけでは、新規顧客の増減に影響されて本当の課題が見えにくいことがあります。 しかし、この手法を用いれば、「いつ、どのような顧客が解約しやすいか」といった具体的なパターンを可視化できるのです。
この分析によって、初期オンボーディングの課題や特定の施策が解約に与えた影響を明確にできます。 また、費用対効果の低い集客チャネルなど、具体的な改善点もデータに基づき特定可能です。
このように、コホート分析は、データに基づいた的確な改善策の立案を可能にし、結果として効率的な解約率低下に貢献します。 顧客の行動パターンを深く理解することで、効果的なリテンション戦略を構築できるでしょう。
解約率を下げるための施策
解約率を下げるための具体的な施策として以下が挙げられます。
- 顧客を深く理解して最適なターゲットを定める
- 強力なオンボーディングで初期離脱を防ぐ
- カスタマーサクセスによる積極的な顧客支援
- 顧客の声に基づくプロダクト・サービスの継続的な改善
- 顧客エンゲージメントを高める施策
- 解約を検討している顧客に最終アプローチをする
このように、解約率を下げるための施策には複数の方法がありますが、効果的なのは、自社の解約における「根本原因」を特定し、それに対応する施策から優先的に実行することです。
たとえば、もし新規顧客の初期離脱が多いのであれば「強力なオンボーディング」に注力すると良いでしょう。既存顧客の不満が蓄積されているのであれば「顧客の声に基づくプロダクト・サービスの継続的な改善」や「カスタマーサクセスによる積極的な顧客支援」がより重要です。
まずは現状の解約パターンを分析し、最も影響の大きい課題から手をつけることで、効率的に解約率の改善を目指せるでしょう。
顧客を深く理解して最適なターゲットを定める
解約率を下げるためには、顧客を深く理解し、自社のサービスにとって最適なターゲット顧客を定めましょう。自社のサービスに合わない顧客は早期に解約する傾向が強く、結果的に解約率を上昇させる原因となるからです。
たとえば、年齢、性別、職業など「既存顧客の属性」やサービスの利用頻度、利用機能、購入履歴といった「行動パターン」を詳細に分析してみましょう。そうすることで、自社サービスに最も価値を見出し、長く使い続けてくれる可能性が高い層を特定できます。その層にマーケティングや営業のリソースを集中させることで、ミスマッチによる早期解約を防ぎ、顧客維持率を高めることができるでしょう。
このように、適切な顧客理解とターゲティングを行うことは、解約リスクを低減し、安定した顧客維持へとつなげるための最初の、そして最も重要なステップといえるでしょう。
強力なオンボーディングで初期離脱を防ぐ
強力なオンボーディングは、顧客がサービスを使いこなし、その価値を最大限に引き出すための土台となります。 顧客はサービス導入の初期段階で「使い方がわからない」「サービスの価値を実感できない」といった課題に直面しやすい傾向があります。そして、顧客が直面する課題は、不満や早期離脱に直結します。どんなに素晴らしいサービスでも、最初につまずいてしまうと顧客はすぐに離れていってしまうのです。
初期の課題を乗り越え、顧客にサービスの価値を実感してもらうためには、多角的なアプローチが有効です。 具体的には、サービスの利用方法を解説する「チュートリアル動画の提供」や、顧客を歓迎し、次にとるべきステップを示す「ウェルカムメール」の送信が挙げられます。 さらに、「インタラクティブな製品ツアーの導入」によって、顧客自身が能動的にサービスを体験できる機会を提供することも効果的です。専任担当者による手厚いサポートは、顧客の疑問や不安を解消し、スムーズな導入を促進します。
これらの丁寧な初期サポートを通じて、顧客を「サービスの成功体験」へと導くことが肝心です。 顧客がスムーズにサービスを利用開始でき、早い段階でメリットを感じられれば、顧客満足度は高まり、結果として長期的な利用へとつながっていくでしょう。
カスタマーサクセスによる積極的な顧客支援
カスタマーサクセスによる積極的な顧客支援も、解約率を下げる上で有効な施策です。カスタマーサクセス活動を通じて顧客がサービスを最大限に活用し、その価値を実感することで、顧客満足度が飛躍的に向上するからです。
オンボーディング支援によってサービス導入時の障壁を取り除き、活用定着のためのフォローアップでサービスの利用を習慣化させます。さらに、課題解決提案を通じて顧客の具体的な問題を解決に導きます。これらの取り組みが、顧客体験の最適化へとつながります。
カスタマーサクセスのアプローチは、顧客の規模や重要度に応じて「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」に分類されます。これらのアプローチを使い分けることで、すべての顧客層に対して適切なレベルのサポートを提供し、顧客満足度を高めることが可能になります。
| ハイタッチ | 特定の重要な顧客に対し、専任担当者がついて手厚い個別サポートを行うモデル |
| ロータッチ | セグメントされた顧客グループに対して、セミナーやワークショップなどを通じて支援するモデル |
| テックタッチ | FAQやチャットボット、チュートリアル動画など、テクノロジーを活用して多くの顧客に効率的に情報提供を行うモデル |
さらに、迅速かつ丁寧な個別対応は、顧客に「自分たちは大切にされている」という実感を抱かせ、結果として継続的なサービス利用へとつながります。カスタマーサクセスによる支援は、単なる問題解決にとどまらず、顧客との間に深い信頼関係を築き、顧客がサービスを長く継続利用する可能性を高めるでしょう。
なお、より詳細なタッチモデルにおける顧客のセグメント方法を確認したい方は「カスタマーサクセスのタッチモデルとは?4つの分類とアプローチ方法を解説」を参考にしてください。
顧客の声に基づくプロダクト・サービスの継続的な改善
解約率を下げるためには、顧客満足度の向上に直結するプロダクト・サービスの継続的な改善が不可欠です。顧客のニーズは常に変化し、競合サービスも日々進化しているため、現状維持では顧客の期待に応え続けることが難しいからです。
顧客に対して常に最新の価値を提供し続ける努力が求められます。具体的には、VOC(顧客の声)を積極的に収集し、それを基に新機能を追加したり、既存の使いづらい点を改善したりすることが挙げられます。
たとえば、多くの顧客から特定の機能に関する要望が上がっていれば、それを優先的に開発することで顧客満足度を高められます。また、利用中に頻繁に発生する不具合や操作性の問題点を改善することも、顧客の不満を解消し、解約を防ぐ上で非常に重要です。
サービスの継続的な進化は、顧客のエンゲージメントを深め、結果として長期的な利用へとつながります。顧客の声を反映し続けることで、顧客は「自分たちの意見がサービスに反映されている」と感じ、より強くサービスに愛着を持つようになるでしょう。
顧客エンゲージメントを高める施策
顧客エンゲージメントの向上は、解約防止の要となります。 顧客がサービスに深い愛着を持つことで、自然と継続利用へとつながるからです。
顧客エンゲージメントを高めるためには、顧客との接点を増やし、積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。たとえば、サービスの最新情報や役立つコンテンツを定期的に提供したり、ユーザーコミュニティを運営して顧客同士の交流を促したりする施策が効果的です。これにより、顧客はサービスに対してより強い帰属意識や愛着を感じるようになります。
積極的なコミュニケーションを通じて、顧客との信頼関係とロイヤルティを育むことで、顧客エンゲージメントは向上します。結果的に、顧客は単なる利用者ではなく、サービスのファンとして長く利用し続けてくれるようになるでしょう。
解約を検討している顧客に最終アプローチをする
解約を検討している顧客には最終アプローチをしましょう。顧客の解約理由を深く理解し、それに対して個別に対応することで、引き留められる可能性が残されているからです。
解約アンケートや直接のヒアリングを通じて、顧客がなぜ解約しようとしているのか、その根本的な理由を丁寧に聞き出します。その上で、顧客が抱える課題に対する具体的な解決策を提示したり、顧客のニーズに合わせた特別オファーを提案したりすることが効果的です。
最終的に解約に至ったとしても、誠実な対応は顧客に良い印象を与え、将来的な再契約につながる可能性や、ポジティブな口コミを生むことにもなり得ます。顧客との関係を最後まで大切にすることで、短期的な解約阻止だけでなく、長期的な企業価値向上にも貢献するでしょう。
解約率改善に取り組む上での注意点
解約率改善に取り組む上での注意点はおもに以下の2つです。
- 無理な引き止めは避ける
- 解約率だけでなく総合的な事業指標で判断する
解約率改善に取り組む上で、無理な引き止めは避けましょう。顧客が既に解約の意思を固めている場合、強引な引き止めは顧客満足度をさらに低下させ、企業のブランドイメージを損なう可能性があるためです。顧客の本質的な課題解決に焦点を当て、長期的な信頼関係の構築を目指す際に特に留意しましょう。
また、解約率だけでなく総合的な事業指標で判断することも重要です。解約率だけを追うと、低収益の顧客を無理に維持するなど、結果的に事業全体の収益性悪化を招く恐れがあるからです。
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
無理な引き止めは避ける
解約率を改善しようとする際に、無理な引き止めは避けるようにしましょう。無理な引き止めは顧客満足度を低下させ、ひいては企業ブランドを損ねる可能性があるからです。
顧客が解約を検討する際には必ず何らかの理由があります。その根本的な理由を無視して一方的に引き止めようとすることは、顧客に不信感を抱かせるだけです。
無理な引き止めによって一時的に解約を回避できたとしても、顧客は不満を抱えたままサービスを使い続けることになります。結果として、早期に再解約するだけでなく、企業に対してネガティブな口コミを広める恐れも出てきます。
目先の解約を防ぐことだけを考えるのではなく、顧客の本質的な課題解決に焦点を当て、長期的な信頼関係の構築を目指すことが重要です。顧客が自らの意思で「このサービスを使い続けたい」と思えるような関係性を築くことが、真の意味での解約率改善につながるでしょう。
解約率だけでなく総合的な事業指標で判断する
解約率だけで事業全体を判断するのは避けましょう。解約率だけを追いかけると、無理な顧客維持策を講じてしまい、結果的に収益性の悪化や顧客体験の低下を招く恐れがあるからです。
たとえば、低収益の顧客が解約することは、全体の利益率を改善させるケースもあります。顧客生涯価値(LTV)や顧客獲得コスト(CAC)とのバランスを考慮することが不可欠です。
健全な事業成長を目指すためには、顧客生涯価値(LTV)、顧客獲得コスト(CAC)、ユーザーあたりの平均収益(ARPU)など、複数の指標を総合的に見て判断するようにしましょう。複数の指標を確認することで、解約率の改善が本当に事業全体のプラスに貢献しているのかを正確に把握し、持続可能な成長戦略を立てられるでしょう。
まとめ
解約率は、顧客が一定期間内にサービス利用を解約した割合を示す指標であり、その正確な把握は事業成長において不可欠です。
解約率が重要視される理由として以下が挙げられます。
- サブスクリプション型ビジネスモデルの成功条件である
- 新規顧客獲得よりも既存顧客維持の方がコストが低い
- 市場での競合優位性を確立できる
- 顧客生涯価値(LTV)の向上に直結する
特にサブスクリプションビジネスにおいては、顧客の継続利用が収益の安定と拡大に直結するため、解約率の低減は最重要課題と言えます。
解約の根本原因を見つけ出すためには、顧客の声の深掘り、解約リスクの高い顧客の特定、顧客の期待と提供サービスのギャップの把握、そしてコホート分析による解約パターンの可視化が有効です。これらのアプローチにより、顧客がなぜサービスを離れてしまうのか、その真の理由を突き止められます。
解約率を下げるための具体的な施策として以下が挙げられます。
- 顧客を深く理解して最適なターゲットを定める
- 強力なオンボーディングで初期離脱を防ぐ
- カスタマーサクセスによる積極的な顧客支援
- 顧客の声に基づくプロダクト・サービスの継続的な改善
- 顧客エンゲージメントを高める施策
- 解約を検討している顧客に最終アプローチをする
これらの施策は、自社の解約の「根本原因」に合わせた優先順位で実行することが成功の鍵となります。
解約率の改善は、単に数値を下げるだけでなく、無理な引き止めを避け、解約率だけでなくLTVやCACなどの総合的な事業指標で判断することが重要です。顧客との長期的な信頼関係を築き、持続可能な事業成長を目指しましょう。
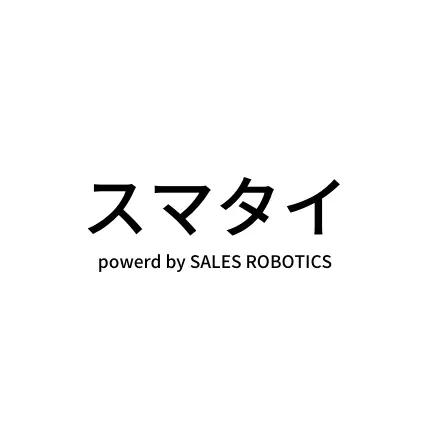
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
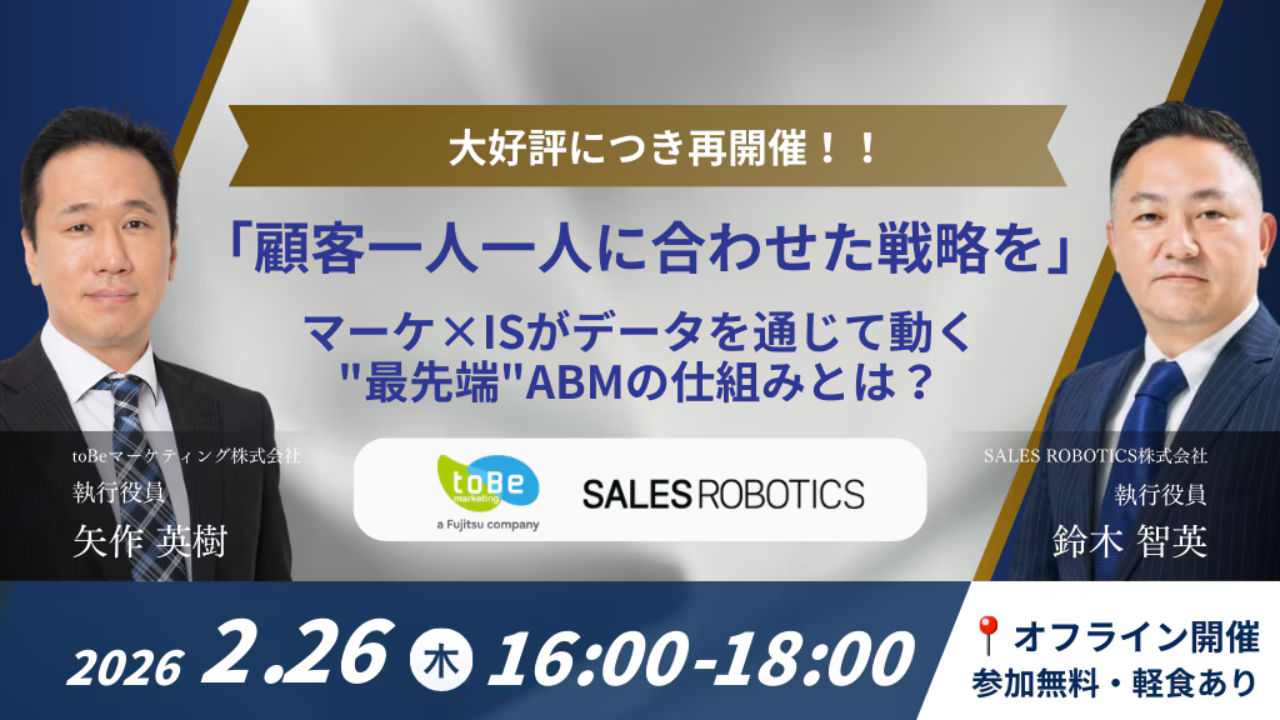
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る