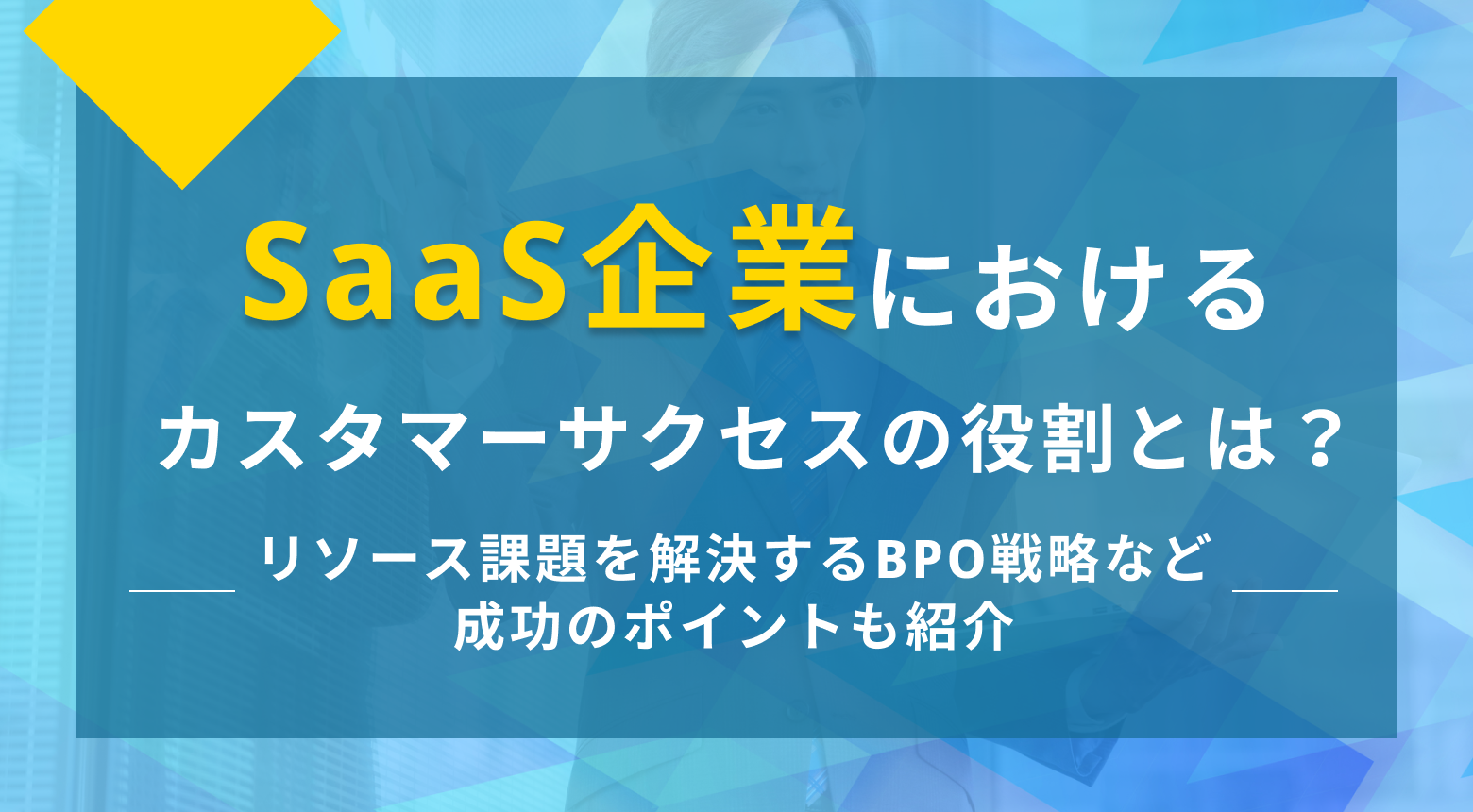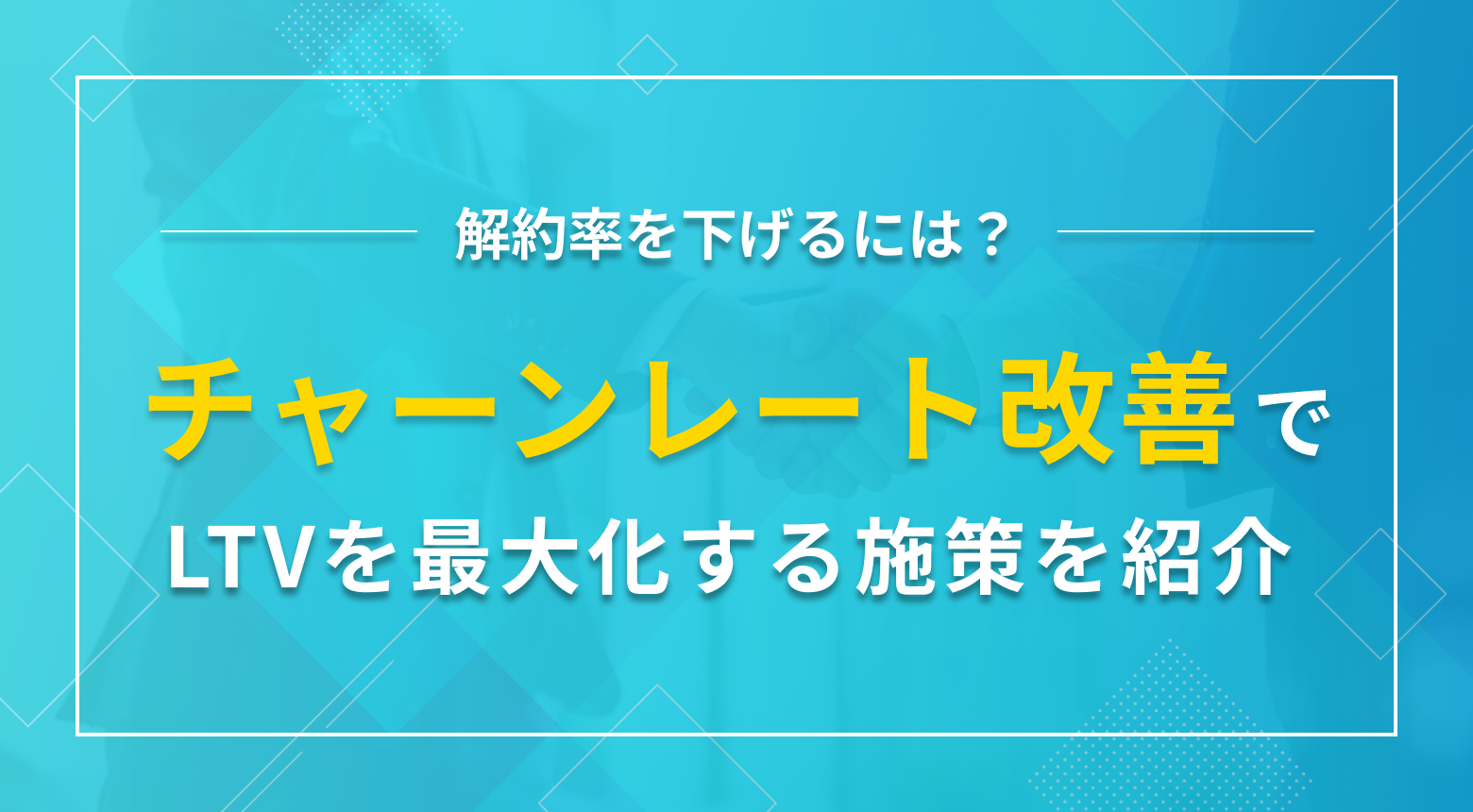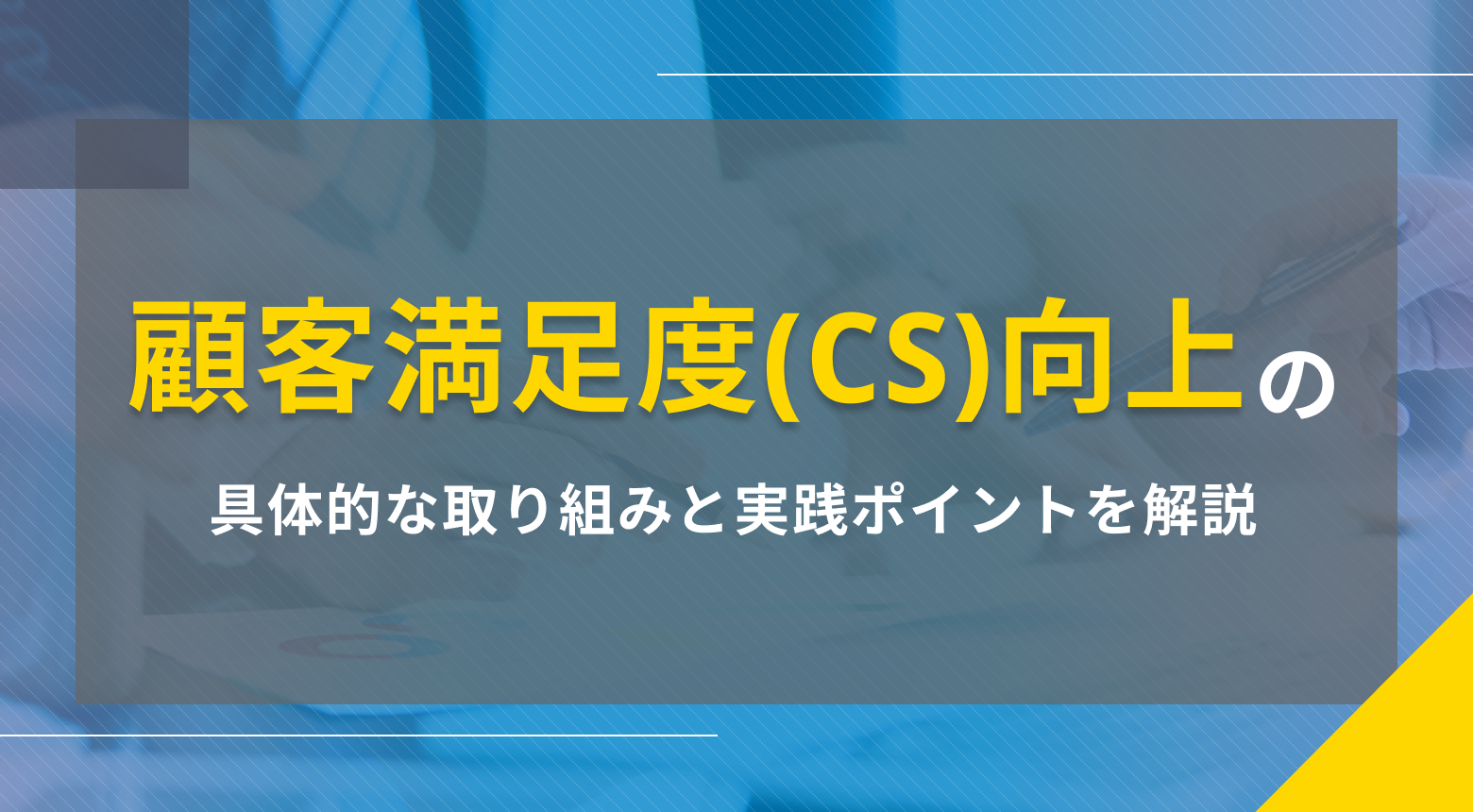データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するポイントとデータ分析の始め方を解説
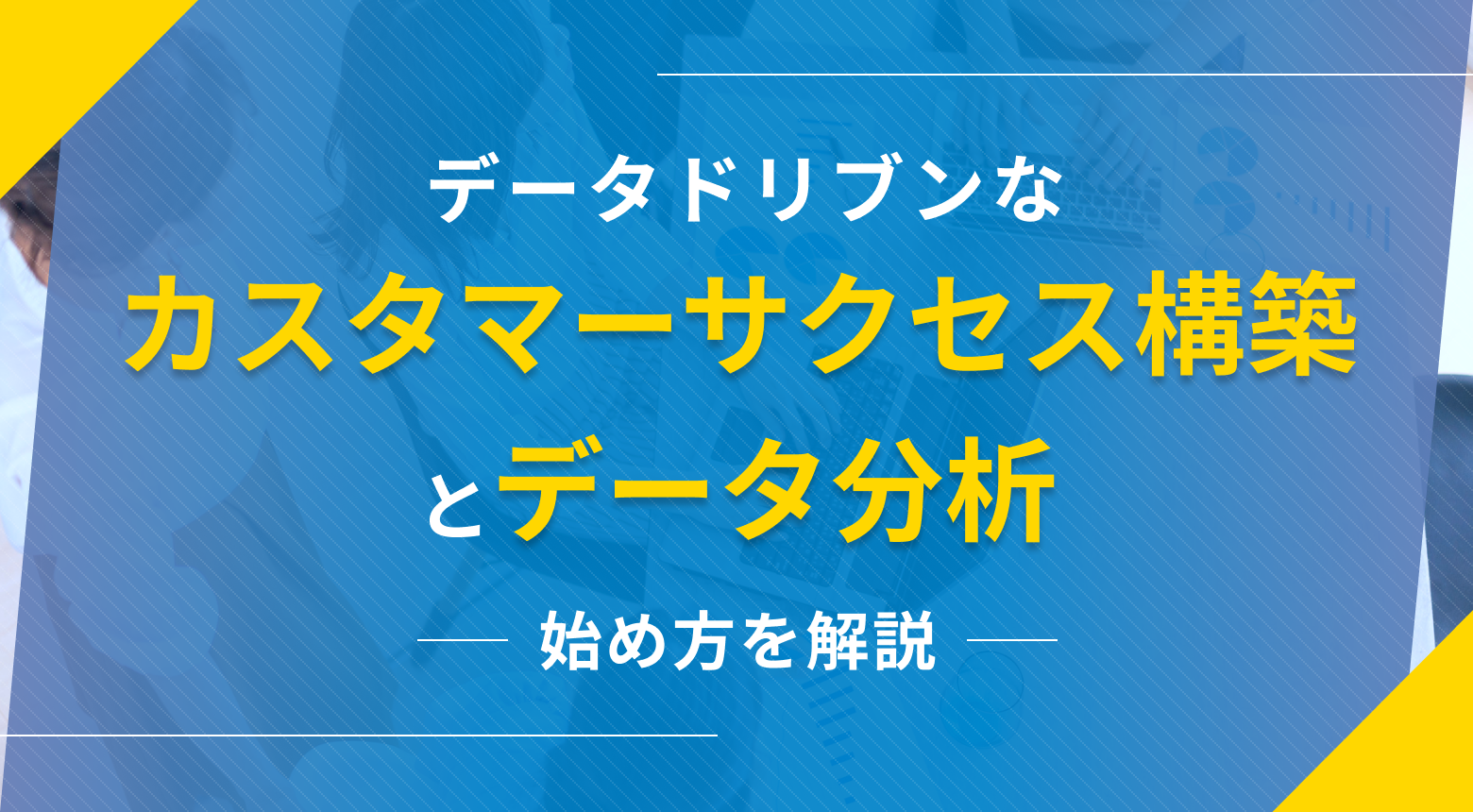
顧客の成功を支援するカスタマーサクセスにおいて、顧客中心のビジネス戦略を強化するためにはデータ分析が重要です。しかし、データ分析の重要性や必要性を感じていながらも「具体的に何から始めればいいのか分からない」と悩む企業も少なくありません。
当記事では、データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するポイントとデータ分析の始め方を解説します。顧客の価値提供を最適化するための基盤を構築し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指したい人は是非参考にしてみてください。
カスタマーサクセスにおけるデータ分析の重要性
カスタマーサクセスにおけるデータ分析の目的は、顧客との関係を深め、ビジネス成長に貢献するための多角的なアプローチを実現することです。顧客の行動、利用状況、満足度などのデータから傾向やパターンを読み解きながら顧客の課題やニーズを深く理解し、データに基づいた戦略的な意思決定を行います。
これにより、解約の兆候を早期に察知して対策を講じたり、自然な流れでアップセルやクロスセルを提案したり、顧客体験向上に繋がるパーソナライズされた施策の立案が可能になります。
このようなデータに基づく意思決定を「データドリブン」といいます。データドリブンなビジネスアプローチは顧客理解の深化、業務効率化、リスク管理などの様々なメリットをもたらし、競争優位性を確立するものとして多くの企業で活用が進んでいます。
データ分析は様々な数字の羅列から意味のある洞察を引き出し、意思決定に役立ててこそ意味があります。漠然としたデータ分析は期待する成果が得られないばかりか時間とコストの浪費に繋がる可能性もあるからです。
特にカスタマーサクセス部門は他部門に比べてデータ分析の結果がLTV(顧客生涯価値)に直結します。顧客満足度の向上や解約防止に直接的に貢献する活動であることを意識してデータドリブンなカスタマーサクセス組織の構築に取り組みましょう。
データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するポイント
データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するためには、行動、意識、プロセスに関するポイントを実践することが大切です。そうすることで組織構造やスキルに伴う課題を解消し、従来の場当たり的な活動を効果検証に基づいた戦略的な活動に転換できます。
データドリブンな意思決定が実現すると、勘や経験だけでなくデータに基づく客観的な根拠を組み合わせた多角的な判断が可能になります。これにより主観性を排除し、実態に即した再現性の高いカスタマーサクセス活動が実現します。
【データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するポイント】
- トップダウンで組織を変革する
- リソースを最適化し組織体制を整備する
- 全社員のデータリテラシーを高める
- データのサイロ化を解消し民主化を推進する
- 意思決定のフレームワークを活用する
トップダウンで組織を変革する
データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するためにはトップダウンで進めるのが理想です。組織全体の変革は強力なリーダーシップが不可欠であり、明確な方向性を持って推進していくことで正確性と実現性が高まるからです。
特に従来の属人的なアプローチや経験則に頼りがちな組織にとっては大きな変革が必要です。データドリブン戦略はツールを導入するだけでは実現できないため、まずは経営層がデータ活用の必要性と組織文化の重要性を理解し、コミットメントを示すことが大切です。
具体的には、データドリブンな組織文化を醸成するためのビジョンを共有し、その推進体制を整備します。それから適切なリソースを投入し、既存の業務プロセスや組織構造をデータドリブンなアプローチに適合させるべく、その役割と責任を再定義します。
さらに、必要に応じて新たなスキルセットの習得や適切な評価指標の導入などもトップ主導で実行していきます。このようなトップダウンのアプローチは全社的なデータ活用を促進し、顧客中心の意思決定を組織に根付かせやすくします。
ただし、トップダウンのアプローチが理想とされる一方で、状況によってはボトムアップを組み合わせたほうが良い場合もあります。現場の従業員からの知見やフィードバックを吸い上げるボトムアップはデータドリブンな組織をより実用的なものにできるからです。
また、全社的な組織変革が難しい場合は部門ごとに小規模からスタートし、適用範囲を徐々に拡大していくアプローチが現実的です。トップダウンを基本としながらボトムアップで補完するなど、自社の状況に合わせてデータドリブンな組織構築を進めていきましょう。
リソースを最適化し組織体制を整備する
データドリブンなカスタマーサクセスを実現するには、リソースを最適化し、組織体制を整備する必要があります。データを活用できる環境を整えることで、効率的に目標達成を目指せるからです。
リソースには、プロジェクトに必要な人材やツール、予算などが含まれます。現状のリソースを正確に把握した上で、目標や優先順位に合わせて最適なリソース配分を検討しましょう。たとえば、LTV(顧客生涯価値)の高い顧客に多くのリソースを割り当てることで、さらなるLTV向上につながります。
定型業務を自動化ツールやAIに任せることで、限られたリソースをより戦略的な業務に集中させることが可能です。また、データサイエンティストやデータアナリストといった専門家と連携すれば、さらに複雑な課題にも取り組めます。
近年、CS Ops(Customer Success Operations)という役割も注目されています。CS Opsは、カスタマーサクセスチームがデータを活用しやすいよう、ツール導入や業務プロセスの構築、データ分析などをサポートします。
組織体制の整備においては、データに基づいた意思決定ができるよう、明確な役割分担と責任範囲を設定することが重要です。カスタマーサクセスチームだけでなく、営業やマーケティング、プロダクト開発など関連部署との連携も強化しましょう。
たとえば、以下のような連携が考えられます。
- 営業部門との連携
CSが分析した解約の予兆が見られる顧客リストを共有し、営業担当者が先回りしてフォローアップを行うことで、チャーン(解約)を未然に防ぐ。
- プロダクト部門との連携
顧客からの問い合わせや要望データを分析・集約し、プロダクト改善の優先順位付けに活用する。
- マーケティング部門との連携
顧客の利用状況からアップセルやクロスセルの機会が見込める顧客セグメントを特定し、ターゲットを絞ったキャンペーンの実施を依頼する。
部門間の壁を取り払い、フィードバックを迅速に共有できる体制を構築することで、顧客満足度の向上や解約率の低下に貢献できます。
全社員のデータリテラシーを高める
全社員のデータリテラシーを高めることはカスタマーサクセス組織を正しく運用していく上でも効果的です。データリテラシーはデータを読み解き、分析し、そこから獲得したビジネス上のインサイトを行動に繋げる一連の能力を指します。
カスタマーサクセスは特定の部署だけでなく、営業、マーケティング、プロダクト開発、サポートなど、顧客と接する全ての部署が連携して実現するものです。各々が顧客データを理解し、共通の認識を持つことで顧客の課題やニーズを正確に把握でき、一貫性のあるサービス提供が可能になります。
この点を踏まえると、データリテラシーを向上させる取り組みとして全社的な研修プログラムを導入することが効果的です。データ分析ツールや各システムの基本操作から顧客データやフィードバックの解釈・活用方法といった実践的な内容までをカリキュラムとして段階的に組み、OJTでのスキルアップ研修なども活用すると良いでしょう。
そして、日常的にデータドリブンな意思決定を奨励する取り組みも積極的に進めます。日々の業務においてデータを常に参照し、そのデータから導き出された根拠について議論することで感覚や経験だけでなくデータに基づいて行動する習慣が根付くようになります。
たとえば、定期的なデータ分析結果の共有会を開催したり、データ活用事例を評価したりすることで社員のモチベーションを高めることができます。これらの取り組みを通じて全社員のデータリテラシーを向上させ、ストレスなくデータを活用できる環境を整備しましょう。
データのサイロ化を解消し民主化を推進する
データドリブンなカスタマーサクセス組織を構築するにはデータのサイロ化を解消することが重要です。データのサイロ化とは顧客に関するデータが複数の部署に散在し、それぞれが独立して管理されている状態のことです。
これに対し、顧客データを一元管理し、必要な担当者がいつでもアクセスできるようにすることをデータの民主化といいます。データドリブンなカスタマーサクセス活動においては、サイロ化の解消と民主化の推進を両輪で進めることで顧客体験全体を包括的に把握します。
データのサイロ化解消の具体的な方法としては、全社的なデータ統合プラットフォームであるCDP(顧客データ基盤)を導入します。CRM(顧客関係管理)システム、サポート履歴、製品利用データ、マーケティングデータなど、あらゆる顧客接点から得られるデータを一元的に集約し、各部門がリアルタイムで最新の顧客情報にアクセスできる環境を構築することで部門間連携を円滑化します。
そして、データの民主化に向けて実際に現場の担当者がデータを容易に活用できる環境を整備するため、直感的に操作できるダッシュボードやレポーティングツールの導入、データ分析に関するトレーニングの実施などを行います。データが特定の部署や個人のものとして囲い込まれるのではなく、カスタマーサクセスに関わる全員がデータに基づいて意思決定を行えるようになることで組織全体の顧客対応力が向上します。
データのサイロ化解消と民主化の推進は、カスタマーサクセス組織がプロアクティブなアプローチを実現するための基盤となります。また、顧客からのフィードバックや問い合わせ履歴を分析することでプロダクトの改善やサービス向上に向けた具体的なアクションを導き出すこともできるため、まずは自社のデータ環境を見直すことから始めてみましょう。
意思決定のフレームワークを活用する
意思決定のフレームワークを活用すると、データ分析の結果を具体的なアクションに繋げやすくなります。フレームワークはデータの分析過程で得られた情報をどのように解釈し、次に何をすべきかを明確にする橋渡しとしての役割があるためです。データに基づいた客観的な意思決定を促進することで経験や直感によるバイアスを減らす効果が期待できます。
また、意思決定のフレームワークはチームや組織が一貫した基準でデータを評価するのに役立ちます。分析結果からデータの有用性や活用方法を示唆することで具体的なアクションプランの策定へとスムーズに移行し、データ分析・意思決定・実行までの一連の流れを定着させることで組織全体にデータドリブンな文化を醸成します。
ここでは意思決定の代表的なフレームワークである「DEAR」「PDCAサイクル」「OODAループ」の3つを説明します。
| 区分 | DEAR (Deployment-Engagement-Adoption-ROI) | PDCAサイクル (Plan-Do-Check-Act) | OODAループ (Observe-Orient-Decide-Act) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 現状把握と課題・機会の特定 | 中長期的な改善活動の継続 | 変化への迅速な対応 |
| 実行速度 | 比較的遅い(数ヶ月〜年単位) | 中程度(数週間〜数ヶ月) | 非常に迅速(数秒〜数分で回す場合もある) |
| 注意点 | ・分析に時間がかかる ・結果が出るまでに時間がかかる | ・計画に固執しすぎると変化に対応しづらい ・状況が変わった場合、計画の見直しが必要になる | ・計画性がないと場当たり的になる ・熟練者の経験や直感が重要になる場合がある |
DEARは顧客の健全性を総合的に評価するためのフレームワークです。導入(Deployment)・関係性(Engagement)・活用(Adoption)・価値(ROI)の4つの観点から顧客がプロダクトをどれだけ効果的に利用し、価値を享受しているかを長期的な視点で分析します。
PDCAサイクルは、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Act)の4つのステップを繰り返すことで業務やプロセスの継続的な改善を促します。ある程度の時間をかけてじっくりと課題解決に取り組む場合に適しています。
一方、OODAループは短期的な視点で迅速な意思決定と行動を促します。観察(Observe)・状況判断(Orient)・意思決定(Decide)・実行(Act)のサイクルを高速で回し、不確実性の高い環境下で即座に最適な行動を判断し、実行することに重点を置いています。
これらのフレームワークは異なる役割を担いながらも互いに補完し合う関係にあります。たとえば、DEARをPDCAサイクルに組み込むと、顧客データに基づいた根拠のある改善計画が立案でき、より客観的な評価が可能になります。
DEARをOODAループに組み込むと顧客の健全性という客観的な指標に基づいて変化を素早く捉えられ、迅速かつ的確な意思決定と行動に繋がります。さらに、PDCAサイクルの実行中にOODAループを発動した場合では、計画的かつ継続的な改善活動と状況に即した機動的な対応を両立することも可能です。
このように、フレームワークを有効活用することによってカスタマーサクセスにおけるデータ分析と意思決定をより強力に推進できます。状況に応じて使い分けたり、組み合わせたりしながら顧客の成功を最大化させるためのデータドリブンな組織を構築しましょう。
データ分析の始め方
データ分析の精度を高めるためには、データ活用の前提条件を確認し、事前準備を整えておくことが重要です。データ分析の基盤となるのは網羅性・正確性・粒度を兼ね備えたデータであり、それらのデータを正しく分析できるツールの導入と活用が不可欠なためです。
データ分析はいきなり始めるのではなく、その分析プロセスの一連の流れを事前に設計し、データを最大限に活用できる状態にしておくことで信頼性の高い結果を得られるようになります。
逆に準備を怠ると分析の途中で問題が発生する可能性を高めます。手戻りや時間のロスに繋がるだけでなく分析結果の信頼性を損なうリスクもあるため、しっかりと準備するようにしましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 前提条件 | ・有用なデータが蓄積されている ・データ分析に適したツールや手法が使いこなせる |
| 事前準備 | ①データ分析の全体像を設計する(現状の把握と整理) ②KPI(重要業績評価指標)を設定する(目標設定) ③ツールやテクノロジーを導入する(基盤構築) ④データ分析プロセスを理解する(計画策定) |
データ分析の前提条件は有用なデータが蓄積されていることです。有用なデータとは必要な情報が過不足なく含まれている「網羅性」、誤りや矛盾が少なく事実を反映している「正確性」、分析目的に対して適切な詳細さを持つ「粒度」を備えたデータのことです。
これらのデータから有益なインサイトを獲得するためにはデータ分析ツールを使いこなす必要があります。加えて、データの量や種類、分析の複雑性に応じて適切なツールを選定し、必要に応じて使い分けたり組み合わせたりするスキルが求められます。
データ活用の事前準備ではデータ分析の全体像を明確にするための全体設計が必要です。解決すべきビジネス課題や必要となるデータ、期待する分析結果、活用方法などを洗い出し、分析の目的と範囲を定めます。この段階で目標とするKPI(重要業績評価指標)を設定しておくと具体性の高いデータを収集でき、より効率的かつ効果的な分析計画が立てられます。
全体設計が完了したら、それに従ってデータ分析基盤を構築します。これはデータを効果的に活用するための土台となるもので、全体設計で特定した必要なデータを適切な形で収集し、複数のシステムや部署に散らばっているデータを一箇所に蓄積させることでデータウェアハウス(DWH)などを構築していきます。
なお、データ分析の精度を高めるためにはデータを加工する作業が不可欠です。データクレンジングとしてフォーマットの統一、重複データの削除、欠損値の補完といった工程を実施します。そうして統合・加工されたデータをグラフやダッシュボードなどを用いて誰にでも分かりやすく可視化することで分析結果の解釈を容易にします。
データ分析プロセスを理解する
データ分析を効率的に進めるには、事前にプロセスを理解しておくことが重要です。適切な手順で進めることで分析結果の信頼性が高まり、意味のある洞察を得られます。
データ分析を成功に導くためのフレームワークにCRISP-DM(Cross-Industry Standard Process for Data Mining)があります。これは「ビジネス理解」「データ理解」「データ準備」「モデリング」「評価」「展開」の6つのフェーズで構成され、前のフェーズに戻りながら分析の精度を高めていけるのが特徴です。
| プロセス | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|
| ビジネス理解 (Business Understanding) | 解決すべきビジネス課題や目標を明確にする | プロジェクトの目的や成功基準を定義し、ビジネスの背景や制約を理解する |
| データ理解 (Data Understanding) | 必要なデータを収集し、その品質や特性を評価する | データの探索的分析(EDA)を行い、データの構造、品質、潜在的な問題(欠損値、外れ値など)を把握する |
| データ準備 (Data Preparation) | 収集したデータを分析に適した形に整形する | データクレンジング、欠損値の補完、特徴量エンジニアリング、データの統合などを行う |
| モデリング (Modeling) | 課題解決に適したアルゴリズムやモデルを構築する | 複数のモデルを試行し、パラメーターを調整して最適なモデルを見つける |
| 評価 (Evaluation) | 構築したモデルがビジネス課題に対してどれだけ有効かを評価する | 精度、再現率、F1スコアなどの評価指標を用いてモデルの性能を客観的に測定する |
| 展開 (Deployment) | 構築したモデルを実際のビジネス環境に導入し、運用する | モデルを本番環境にデプロイし、パフォーマンスの監視や定期的な再学習の計画を立てる |
このプロセスで特に時間を要するのが、データクレンジングや加工といった「データ準備」の工程です。分析に適した形にデータを整形することで、より精度の高い分析が可能になります。
また、分析を進める際は、「比較(異なるグループを比較する)」「時系列(データの時間的変化を追う)」「要因理解(特定の事象の原因を探る)」という3つの原則を意識することで、分析の質をさらに高められます。
たとえば、顧客の解約率を下げたい場合、「比較」の視点で解約顧客と継続顧客のデータを見比べ、「時系列」で利用状況の変化を追うことで解約の兆候を把握できます。さらに「要因理解」の視点でアンケートなどを実施すれば、データだけでは見えない根本的な原因を発見できます。
体系的なフレームワークと3つの原則を組み合わせることで、客観的で再現性の高い意思決定が可能になります。
現状を把握し課題と目的を整理する
カスタマーサクセスにおけるデータ分析は、全体設計の段階で現状把握・課題発見・目的設定を実行します。その後で具体的なデータ分析に進むことで、より効果的かつ効率的な成果が得られるようになります。
| 目的 | 詳細 |
|---|---|
| 方向性を定める | どのデータをどのような手法で分析すれば良いのかを明確にする |
| 無駄な分析を避ける | 漠然としたデータ分析によって無関係なデータに時間を割いたり、意味のない洞察に繋がったりするのを防ぐ |
| 具体的なアクションに繋げる | 課題と目的が明確であれば、分析結果から具体的な改善策や施策を導き出しやすくなる |
| ステークホルダーとの共通認識を持つ | 事前に要点を明確にしておくことで、関係者間の目的や期待値のずれを防ぐ |
全体設計の具体的な進め方は現状を俯瞰することから始めます。現在のカスタマーサクセスにおけるKPI(チャーンレート、NPS®、利用頻度など)や顧客の行動データ、サポート履歴などを収集し、それらのデータに基づいて現状の課題を特定します。
そして、現状把握で得られた情報からチャーンレートが高い理由や特定機能の利用率が低い要因などを仮説として想定し、具体的な課題に設定します。この段階では漠然とした課題でも良いですが、ある程度の方向性を持つことが重要です。
その上で、課題を解決するためにはデータ分析を通じて何を達成すべきかを明確にしていきます。ここで大切なのは、データ分析は目的達成のための手段であり、目的そのものではないという認識です。また、目的は後続のプロセスの道筋となるため、具体的で測定可能な形で評価指標を定義し、KPIを設定するようにしましょう。
目的に適したKPIを設定する
目的に適したKPI(重要業績評価指標)を設定すると目標達成までの道筋が明確になります。KPIはKGI(最終目標)を達成するための「中間指標」として進捗状況を可視化し、リアルタイムで把握することで計画の修正や改善を迅速に行えるからです。
カスタマーサクセスにおいてKPIは顧客との関係性の深さや健全性を評価する重要な指標です。顧客がプロダクトにどれだけ満足し、長期的に利用し続けてくれるかを評価することに重点を置き、顧客の視点に立った具体的で測定可能なKPIを設定しましょう。
| KPIの例 | 詳細 |
|---|---|
| CSAT(顧客満足度) | 顧客がプロダクトにどの程度満足しているかを測定する指標 [満足した顧客の数 ÷ 全体の回答数 × 100] |
| NPS®(顧客推奨度) | 顧客がプロダクトを他者に推奨する可能性を測定する指標 [推奨者の割合 - 批判者の割合] |
| 解約率(チャーンレート) | 一定期間内にプロダクトの利用を停止(解約)した顧客の割合を測定する指標 [特定期間中の解約顧客数 ÷ 期首または平均顧客数 × 100] |
| 顧客維持率(リテンションレート) | 一定期間内にサービスを継続利用する顧客の割合を示す指標 [(期間終了時の顧客数 - 期間中に獲得した顧客数)÷ 期間開始時の顧客数 × 100] |
| LTV(顧客生涯価値) | 個々の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益 [購入単価 × 粗利率 × 購入頻度 × 取引期間 - 顧客獲得費用 - 維持費用] |
カスタマーサクセスにおける一般的なKPIの設定手順として、最初に確認するのがCSAT(顧客満足度)です。これは顧客が特定のサポート対応や製品の機能利用といった個々の体験にどれだけ満足したかを測る指標です。CSATが低ければ顧客とのタッチポイントに何らかの問題があることを示し、早急な改善が必要と判断できます。
次に、NPS®(顧客推奨度)を確認し、CSATがプロダクト全体のロイヤルティにどう繋がっているかを把握します。NPS®は顧客がそのサービスを他者に推奨したいと思うかという視点でロイヤルティを測ります。NPS®が高い顧客は長期的な関係が期待でき、低い顧客は解約リスクの高い顧客として注視する対象となります。NPS®については、「NPSとはどんな指標?顧客満足度との違いや測定方法を解説」をご確認ください。
そして、CSATとNPSで把握した顧客の感情が実際の行動にどう影響しているかを解約率(チャーンレート)と顧客維持率(リテンションレート)から測定します。これらのKPIは顧客が実際にサービスを継続利用しているかを測る直接的な指標です。
LTV(顧客生涯価値)を測定するとこれまでの顧客の動向が結果として事業収益にどう貢献したのかを評価できます。LTVは顧客がプロダクト利用を通じて生涯にもたらす総収益であり、顧客の満足度、ロイヤルティ、維持率といった全ての要素が総合的に反映されるため、どの顧客セグメントに注力すべきか判断するのに役立ちます。
さらに、これらのKPIにヘルススコアを併用すると顧客の全体的な状態を把握できます。ヘルススコアは「兆候」や「状態」を示すため、低下傾向にあるスコアを特定することでKPIだけでは見えにくい顧客のマイナスの兆候を早期に捉えられ、先手を打ったアプローチを実現します。ヘルススコアの活用については「カスタマーサクセスに活用するヘルススコアとは?重要性や導入ステップを解説」で解説しています。
なお、これらのKPIはあくまで一般的な例であり、事業の特性や目標に応じて最適な指標は異なります。カスタマーサクセスの主要なKPIは「カスタマーサクセスで重視される12のKPIと設定の手順を解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
ツールやテクノロジーを導入する
データ分析ではツールやテクノロジーの導入が不可欠です。ITインフラを整備して正しく活用することが顧客データから価値ある洞察を引き出す鍵となるためです。
データ分析の初期段階や小規模な組織においてはExcelや汎用的なITツールで事足りる場合もありますが、顧客数の増加やデータの複雑化が顕著な場合は現実的ではありません。そのため、組織の成長に伴ってデータ分析の専門性や効率性を高めたい場合は専用ツールの導入を検討する必要があります。
さらに、AIや機械学習といった最先端の技術を組み合わせることでデータ分析の精度が高まります。これにより、将来の需要予測や顧客の行動予測などがより正確に把握でき、戦略的な意思決定が可能になります。
| 分類 | ツール | 詳細 |
|---|---|---|
| データ収集・管理 | Excel・スプレッドシート | 小規模なデータ管理や手動での集計、簡単な分析に使用される |
| CRM(顧客関係管理) | 顧客情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを一元管理し、顧客との関係構築を支援する | |
| SFA(営業支援システム) | 営業活動のプロセスや進捗を可視化し、効率化や生産性向上に繋げる | |
| MA(マーケティングオートメーション) | メール配信やWebサイトの行動履歴など、見込み顧客のデータを収集し、マーケティング活動を自動化する | |
| DMP(データマネジメントプラットフォーム) | 広告配信やマーケティング活動のために、Cookie情報などを活用した大規模なユーザーデータを管理する | |
| データ分析・可視化 | BIツール(Business Intelligence Tool) | 複数のデータを統合し、グラフやダッシュボードで分かりやすく可視化することで、意思決定を支援する |
| Google Analytics | Webサイトへのアクセス数、ユーザーの行動、コンバージョン率などを分析する際に使用される | |
| カスタマーサクセスプラットフォーム | 顧客の利用状況や満足度を把握し、解約防止やLTV(顧客生涯価値)向上に繋げる | |
| データ処理・分析言語 | SQL (Structured Query Language) | データベースに蓄積されたデータを操作・抽出・集計するための言語 |
| Python | データ処理、統計解析、機械学習など、幅広い用途で利用される汎用性の高いプログラミング言語 | |
| R言語 | 主に研究や学術分野で利用されてきた統計解析やグラフ作成に特化した言語 |
データ分析では、データ活用の基盤を整えることで顧客データの活用が促進され、具体的なビジネス戦略を立案しやすくなります。たとえば、CRMやSFAなどのツールは顧客の購買履歴や問い合わせ内容などを一元管理でき、MAツールは顧客のWebサイト上での行動やメールの開封状況を分析することで顧客の興味関心に沿った個別のアプローチに貢献します。
蓄積された膨大なデータの分析・可視化には、BIツールが有効です。売上動向や顧客属性などをダッシュボードで分かりやすく確認できるため、どの商品がどの顧客層に人気があるのか、どの地域の売上が伸びているのかといった洞察を瞬時に得ることが可能です。
また、データ処理・分析言語であるPythonやR言語を用いれば、より複雑な統計分析や機械学習モデルの構築が実現できます。将来的な傾向や顧客離脱の兆候を早期に検知するといった高度な分析も可能で、より効果的な意思決定をサポートします。
さらに、これらのツールや言語と合わせて統計分析、機械学習、自然言語処理などの分析手法を活用するとより深い洞察を得られます。たとえば、クラスター分析を用いて顧客をロイヤリティ別にセグメント分けし、それぞれに適切なアプローチ(ハイタッチ・ロータッチなど)を実施する、機械学習によって顧客の解約リスクを予測する、自然言語処理で顧客からの問い合わせ内容を分析し、解約の予兆となるキーワードを自動で検出する、といったより戦略的なアクションにつなげられます。
ただし、高度なツールや言語を活用するためには統計学的な知識や分析結果に対する思考力などの専門的なスキルを備えた人材の確保が不可欠です。ツールの導入時やデータの整備などにもコストがかかるため、費用対効果を十分に考慮するようにしましょう。
データ分析能力を含むカスタマーサクセスに必要なスキルは「カスタマーサクセス部門において育成すべきスキルや人材育成方法を解説」で説明していますので是非参考にしてみてください。
まとめ
データドリブンなカスタマーサクセス組織の構築は、データを単に集めるだけでなく、顧客価値を最大化するために活用し続ける文化と仕組みを組織全体に浸透させることが求められます。
そのためには、トップダウンによる明確な方向性とリソースの最適化、全社員のデータリテラシー向上、そしてデータのサイロ化解消と民主化の推進が必要です。さらに、意思決定のフレームワークを取り入れることで、分析結果を確実にアクションへつなげられる環境が整います。
データ分析を始める際は、現状把握と課題・目的の整理、目的に適したKPIの設定、ツールやテクノロジーの導入、分析プロセスの理解といった準備を丁寧に進めることが重要です。特に、CRISP-DMなどの体系的なプロセスと比較・時系列・要因理解の視点を組み合わせることで、より精度の高い分析と再現性のある意思決定が可能になります。
日常業務にデータ分析を組み込み、根拠ある判断を継続的に行うことで、顧客満足度やLTVの向上はもちろん、事業全体の持続的な成長へとつなげることができるでしょう。
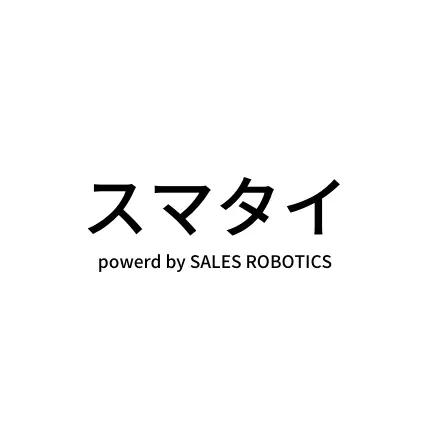
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
現在受付中のセミナー・イベントはありません。
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る