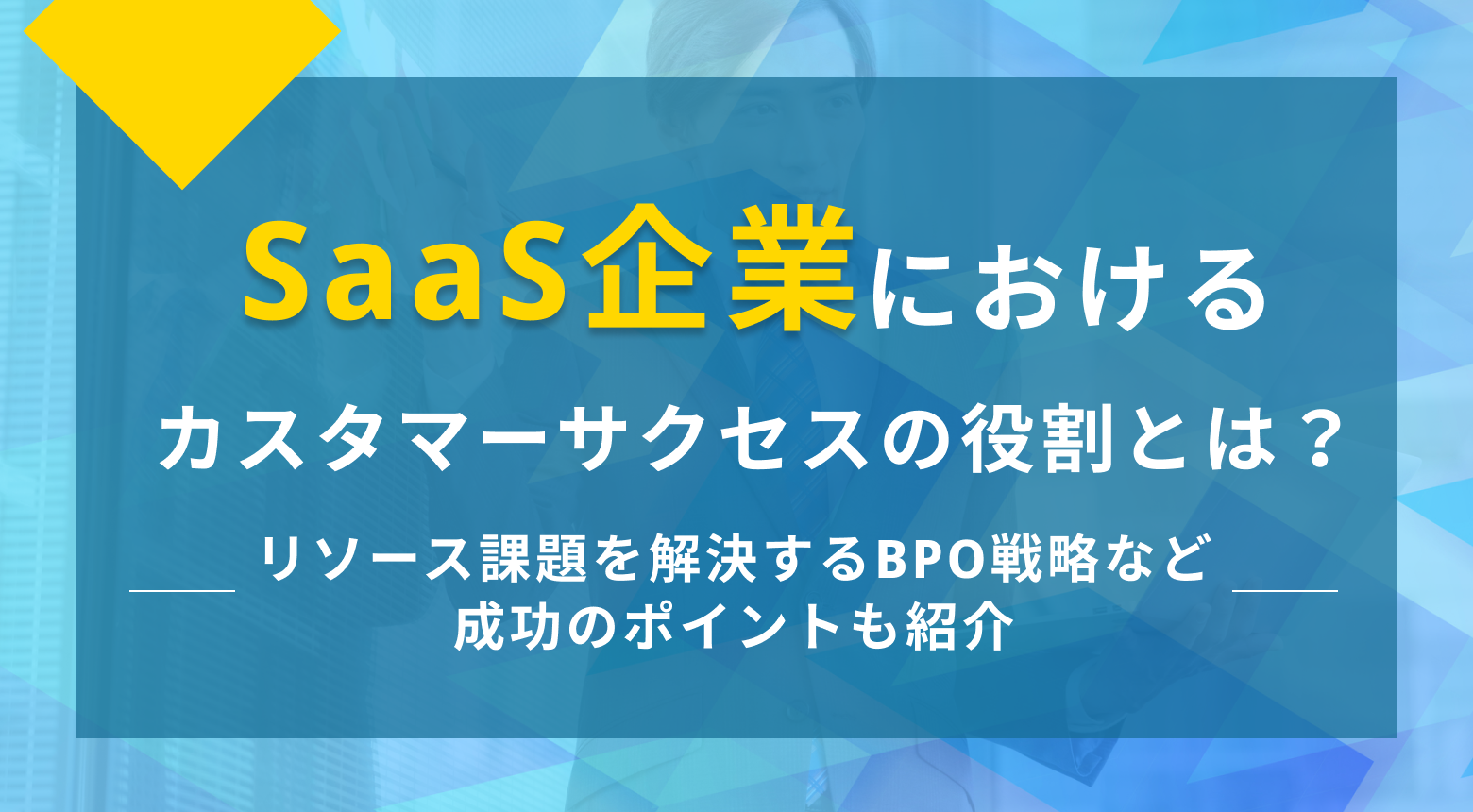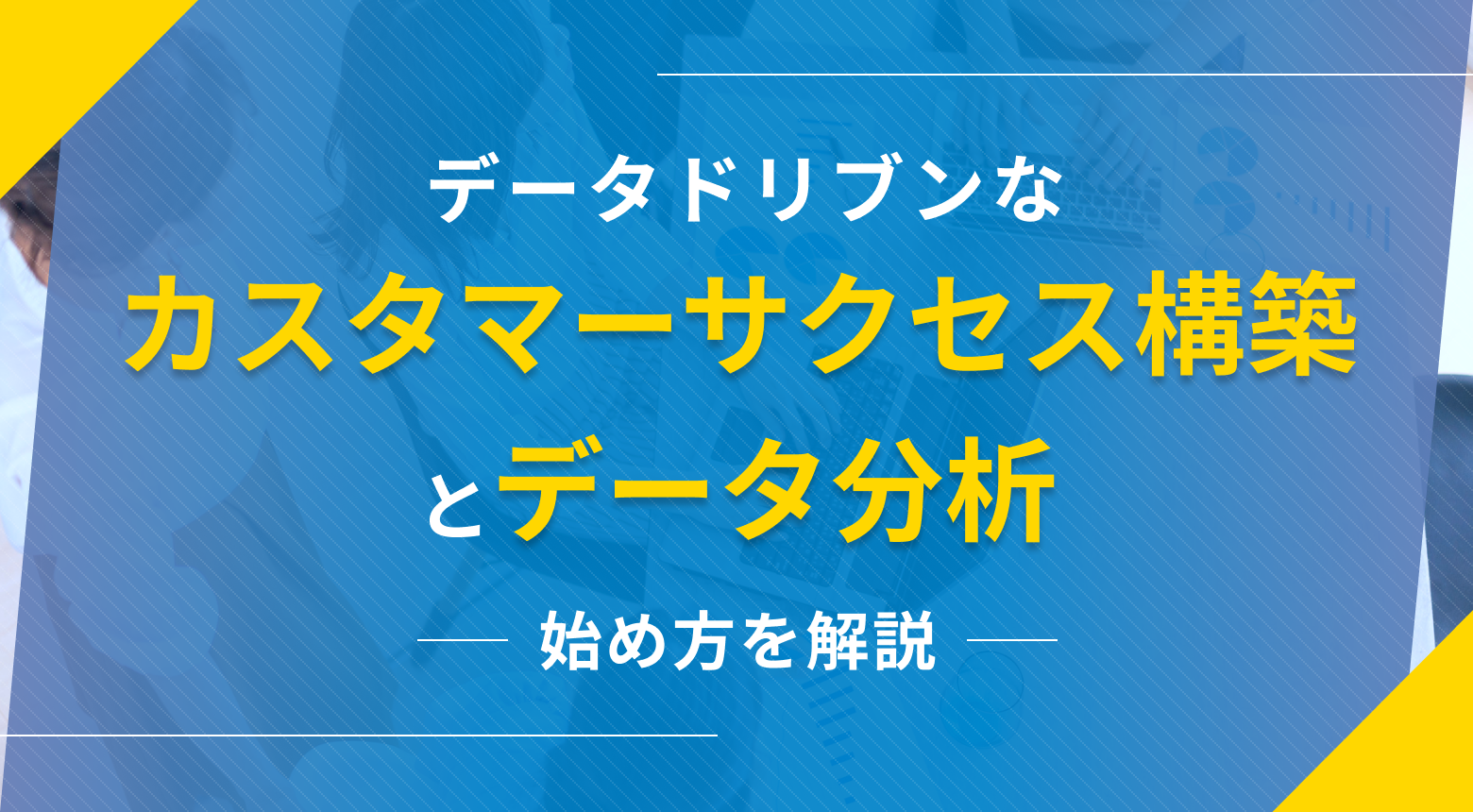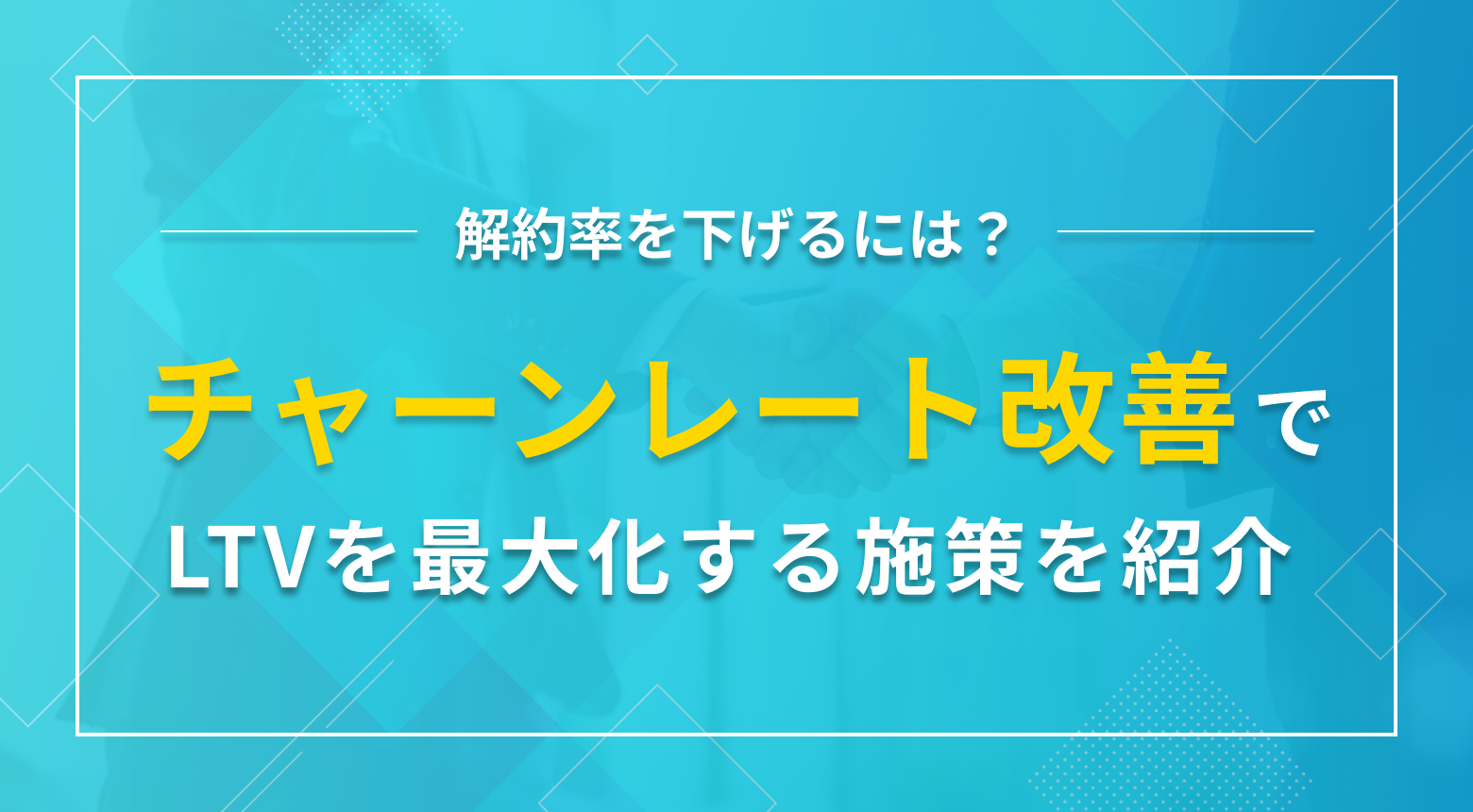顧客満足度(CS)向上の具体的な取り組みと実践ポイントを解説
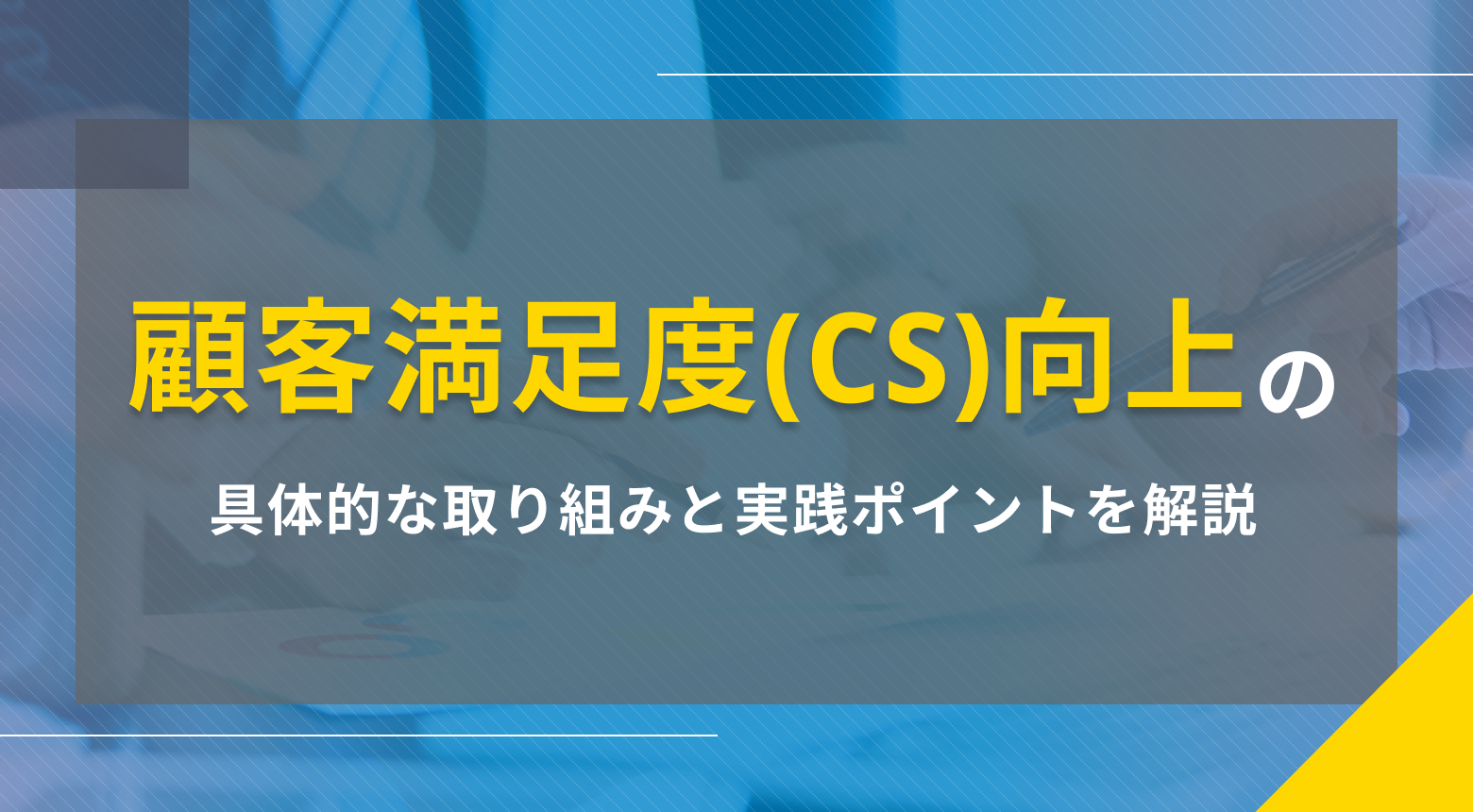
現代のビジネス環境では市場の成熟と競争の激化によって新規顧客の獲得が難しい傾向にあります。同時に、既存顧客の離反や顧客単価の低迷なども多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。
このような状況において企業が持続的な成長を実現していくためには、顧客満足度(CS)の向上に向けた取り組みが不可欠です。顧客ロイヤルティや顧客エンゲージメントの向上に注力することでLTV(顧客生涯価値)の最大化を目指すことが求められています。
当記事では、顧客満足度(CS)向上の具体的な取り組みと実践ポイントを解説します。顧客満足度の向上に課題を感じている人は、是非参考にしてみてください。
顧客満足度(CS)とは
顧客満足度(CS)とは、顧客がプロダクトを利用した際にその品質や体験にどの程度満足しているかを測る指標のことです。顧客がプロダクトに満足すればするほど企業に対する好感度や信頼感が高まり、結果としてブランドイメージが向上します。
企業のブランドイメージは企業価値や競争優位性に直結し、高評価を維持することで売上増加や市場シェア拡大などのビジネス成果に繋げやすくなります。さらに、既存顧客がエンドーサー(Endorser)としての役割を果たすとリファラル(紹介)による新規顧客獲得効果も期待できます。
ただし、顧客満足度はあくまで過去の経験に対する評価のため、顧客満足度だけを追っていては企業の持続的な成長には繋がりません。そこで、顧客満足度と類似する概念である「顧客ロイヤルティ」と「顧客エンゲージメント」を区別して理解することが重要です。
顧客ロイヤルティは顧客が特定の企業やブランドに対して抱く信頼や愛着を指します。これは単にプロダクトに満足しているだけでなく、競合他社に乗り換えようとしない、繰り返し購入する、あるいは他者に推奨するといった行動に表れ、過去の経験に基づいて形成される信頼やそのブランドの価値観への共感から生まれる持続的な関係性といえます。
一方、顧客エンゲージメントは顧客と企業との間に存在するより能動的で感情的な繋がりを意味します。これは単に製品を購入するだけでなく、ブランドのSNSをフォローしたり、イベントに参加したり、フィードバックを提供したりするなど、顧客が企業に対して積極的に関わろうとする状態を指し、顧客がブランド体験を通じて得られる感情的な価値や企業とのインタラクションから生まれる深い結びつきによって育まれます。
このように、顧客満足度、顧客ロイヤルティ、顧客エンゲージメントの3つの要素はLTVの最大化に不可欠な要素として密接に関わっています。これらを包括的に高めることで顧客との長期的な関係を構築し、結果として企業の持続的な成長と収益向上に貢献します。
なお、LTVを向上させるための施策は「LTVを向上させるための施策と成功に導くポイントを解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
顧客満足度向上の具体的な取り組み
顧客満足度を向上させるためにはプロセスを体系的に理解し、各ステップを着実に進めていくことが重要です。課題の特定から改善策の実行、効果測定までを一貫して行うことで効果的かつ持続的な成果が創出できます。
また、単に課題を解決するだけでなく、解決に至るプロセスの再現性を高め、組織に知見を蓄積する効果もあることから、従業員のモチベーション向上や企業文化の醸成にも寄与し、継続的な成長を実現するための強固な基盤を築けるようになります。
【顧客満足度向上のプロセス】
- 顧客満足度を調査して現状を把握する
- 調査結果を分析して仮説を立てる
- 仮説に基づいて目標(KPI)を設定する
- カスタマージャーニーを最適化する
- 顧客視点に立って施策を実行する
- 業務改善のフレームワークを活用する
①顧客満足度を調査して現状を把握する
顧客満足度調査は顧客満足度の向上に不可欠な顧客のニーズや期待、プロダクトに対する評価を深く理解するための基盤です。調査を通じて顧客の行動や背景に関する詳細なデータを収集・分析し、顧客満足度を定量的・定性的の両面から測定します。
顧客満足度調査は、一般的に次の手順で実施します。
- 調査目的の明確化
- 調査対象と範囲の設定
- 調査方法の決定
- 質問票の設計
- データ収集の実施
- データ分析と報告
顧客満足度調査を実施する上で重要なのは、目的に適した調査方法を選択することです。調査方法によって収集できるデータの種類や深さは異なり、調査目的に合致しない方法を選択すると望むような結果が得られない可能性があるからです。
適切な調査方法の選択は、調査の目的と獲得したい情報の種類を明確にすることが重要です。煩雑なデータから顧客満足度を正確に測定し、顧客が満足感を得られている理由や不満に感じている原因を特定できれば、漠然とした顧客の声も具体的な改善策へと落とし込みやすくなります。
| 分類 | 調査方法 | 概要 |
|---|---|---|
| 定量調査 | ネットリサーチ | Web上でアンケートを実施し、多くの回答を効率的に収集する。選択肢形式の質問で数値化されたデータを集めるのに適している。 |
| アンケート調査 | 店舗、訪問、街頭、電話、郵送などの様々なチャネルを通じて回答を収集する。顧客の属性情報や利用実態、満足度などを数値で把握できる。 | |
| 会場調査(CLT:セントラルロケーションテスト) | 特定の会場に対象者を集め、プロダクトを体験してもらった後でアンケートやインタビューを実施する。新製品の感想や競合品との比較、パッケージデザインの評価など、実体験が必要な調査に適している。 | |
| 覆面調査(ミステリーショッパー) | 調査員が一般顧客を装って店舗やサービスを利用し、接客態度、店舗の清潔さ、商品陳列、サービス品質などを評価する。従業員のパフォーマンスやサービス提供の実態を客観的に把握できる。 | |
| 定性調査 | インタビュー調査 | 対象者と直接対話することで顧客の深層心理や行動背景、感情、潜在的なニーズなどを深く掘り下げる。1対1の面接形式(デプスインタビュー:深層面接法、ディテールドインタビュー:詳細面接法)やグループインタビューなどがある。 |
| 行動観察調査(エスノグラフィ) | 調査員が対象者の日常生活や特定の状況下での行動を直接観察し、その行動の背景や意味を理解する。顧客自身も意識していない無意識の行動や習慣、利用実態などを把握できる。 | |
| VOC(Voice of Customer)分析 | 顧客からの問い合わせ、クレーム、SNS投稿、レビュー、フリーコメントなどの多用なチャネルから顧客の生の声(VOC)を収集し、分析する。顧客の不満、要望、プロダクトの改善点などを包括的に把握できる。 |
顧客満足度調査の中でもVOC(Voice of Customer)分析は費用対効果が高く、多くの企業で導入されています。顧客の声に直接耳を傾けることで定量調査では見えにくい深層的なニーズや課題、感情を把握でき、アンケートでは引き出せない本音や企業側が想像もつかないような貴重な意見を発掘できる可能性があります。
たとえば、問い合わせやクレームには製品の具体的な不具合や利用上の不満が込められ、SNS上の投稿やレビューからはユーザーのリアルな使用感や推奨度が読み取れます。また、フリーコメントでは定型的な質問では測れない自由な発想に触れられるなど、顧客の生の声を収集することで顧客体験(CX)の改善や新たな価値創造に貢献します。
顧客満足度調査は調査方法を組み合わせるとより多角的な知見が得られます。具体的には、ネットリサーチで広範な顧客層の定量的な満足度を把握しつつ、特に不満が高い層にはデプスインタビュー(深層面接法)を実施してその原因を深掘りする方法などがあります。
また、新製品の市場投入前に会場調査(CLT:セントラルロケーションテスト)で機能面やデザインの受容性を確認した後、実店舗での販売開始に伴って覆面調査(ミステリーショッパー)を実施すると接客や陳列状況などから顧客体験の全体像を把握でき、より効果的な改善に取り組めるようになります。
定量調査で全体的な傾向を把握し、定性調査でその背景や理由を深掘りするというように、目的に応じて複数の調査手法を組み合わせるとより深く多角的なインサイトを獲得できます。なお、VOC分析の詳細は「VOC分析を導入するべき企業の特徴や収集方法を解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
②調査結果を分析して仮説を立てる
顧客満足度調査の分析と仮説は具体的な改善策や戦略の立案に繋げる重要なステップです。調査を実施しただけでは現状を把握したに過ぎず、本質的な課題の解決には顕在化した顧客の不満や要望を汲み取る作業が必要です。
具体的には、顧客満足度の分析手法を活用し、顧客がプロダクトに対してどのような感情を抱いているか、どのような体験をしているかといった定性的な情報と、アンケート結果や購買データなどの定量的な情報を結び付け、顧客の真のニーズや課題を深掘りしていきます。
調査結果を単なる数値として見るのではなく、その背景にある顧客の心理や行動パターンを深く理解し、真のニーズやペインポイントを特定するための具体的な仮説を立てて検証していきましょう。
| 手法 | 概要 | 例 | 目的・効果 |
|---|---|---|---|
| 単純集計 | 顧客満足度調査で得られた個々の質問項目について回答の分布(各選択肢の割合)を算出する | 「製品Aの満足度は?」に対して「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」の割合を算出 | 各質問項目における顧客の全体的な傾向や満足度レベルを把握する。現状把握が手軽なため、初期段階の分析に適している。 |
| クロス集計 | 複数の質問項目を組み合わせて集計し、特定の属性や行動と満足度の関係性を明らかにする | 「性別×製品満足度」「年代×サービス満足度」の関係を分析 | 顧客セグメントごとの満足度傾向を詳細に把握する。特定の顧客層に特化した改善策や戦略を立案できる。 |
| ポートフォリオ分析 | 顧客満足度を「重要度」と「満足度」の2軸で評価し、その結果をマトリクス(散布図)上にプロットする | 顧客にとって「重要だが満足度が低い項目」や「重要度も満足度も高い項目」を可視化 | 優先度の高い改善項目や維持すべき自社の強みなどを明確にする。限られたリソースで注力すべき点を客観的に判断し、顧客の期待値と実際の満足度のギャップを視覚的に把握できる。 |
顧客満足度調査で得られたデータは単純集計によって全体像を把握できます。たとえば「製品Aの満足度は80%だ」という質問に対し、顧客の回答(選択肢)の割合や平均値を算出すると顧客満足度の全体的な傾向が読み取れます。評価の高い点や低い点を洗い出すこともできるため、改善すべき弱みや伸ばすべき強みを特定する手がかりになります。
一方、クロス集計は特定の質問項目と別の質問項目を掛け合わせて集計することで、より詳細な顧客の特性や行動パターンを把握できます。たとえば「製品Aの満足度は高いが、その中でも20代男性の満足度が特に低い」といったように、属性や利用状況と顧客満足度の関係性を明らかにすることが可能です。
ポートフォリオ分析は優先度を把握したい場合に有効です。「重要度」と「満足度」の2つの軸で項目をプロットし、4つの領域にマッピングすることで分析結果を視覚的に把握できます。たとえば「顧客が重要視しているが満足度が低い」項目は優先的に改善すべき課題として特定でき、「満足度は高いが顧客があまり重要視していない」項目は現状維持で問題ないと判断できる可能性があります。
顧客満足度の分析結果から想定した仮説は、データによって導き出された検証可能な推測として改善策の方向性を定める効果があります。たとえば「製品Aに対する20代男性の満足度が低いのは若年層の好みとデザインが合致していないためではないか」という仮説を立てたとすると、具体的なデザイン変更の検討や20代男性を対象としたデザインに関する追加調査の実施など、次の行動を明確にできます。
また、ポートフォリオ分析で「重要度が高いのに満足度が低い」と判明した項目が「サポート対応の速さ」であるならば「サポート対応の遅さが顧客満足度全体の低下を招いているかもしれない」という仮説が立てられ、サポート対応の平均時間を短縮して即時対応を心がけながら顧客満足度の変化を追跡するといった具体的な行動に移せます。
このように、調査結果を基にした仮説は漠然とした課題を検証可能な問いに変え、改善サイクルを効果的に回す効果が期待できます。限られたリソースの中で顧客満足度向上に最も適した改善策に注力し、費用対効果の高い施策を立案していきましょう。
③仮説に基づいて目標(KPI)を設定する
顧客満足度向上に向けたKPI(重要業績評価指標)は、調査結果から得られた仮説に基づいて設定します。顧客満足度のような抽象的な目標は初めから具体的なKPIを定めることは難しいため、顧客満足度の構成要素がどのような要因に影響するのかを仮説を立てて検証する必要があります。
仮説に基づくKPIは施策の効果を明確に測定し、その成果を客観的に評価します。さらに、KPIが未達成の場合でもどの段階で問題が生じたのかを特定しやすくします。当初の仮説が顧客満足度向上に本当に貢献しているかを検証しながら、施策の立案や改善を効果的に進めましょう。
| 指標 | 概要 | 算出方法 | KPIの例 |
|---|---|---|---|
| CSI(Customer Satisfaction Index) | 顧客がプロダクトに対してどれだけ満足しているかを測る総合的な指標 | 「顧客期待値」「顧客不満度」「顧客忠実度」「知覚品質」「知覚値」の5項目で構成された質問の回答結果を収集し、平均値を算出する | 総合的な顧客満足度スコア、各項目(プロダクト・サポート・価格など)に対する満足度スコア、競合他社との満足度比較 |
| JCSI(日本版顧客満足度指数) | 日本のサービス産業に特化した顧客満足度指標(日本産業標準調査会が開発) | CSIの項目に「推奨意向」を加えた6項目の平均値を算出し、「顧客が感じた価値 - 事前期待値」で顧客満足度を数値化する | JCSIスコア、顧客ロイヤルティ、口コミ |
| NPS®(Net Promoter Score) | 顧客が企業やプロダクトを友人や同僚に「どれくらい勧めたいか」を数値化した指標 | [推奨者の割合 ー 批判者の割合] | NPS®スコア(推奨者、中立者、批判者の割合に基づく)推奨理由、批判理由のフリーコメント分析 |
| C-SAT(Customer Satisfaction) | プロダクトに対する顧客の満足度を直接的に測定する指標 | 「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」などの項目を星や数字によって視覚的に計測する[満足した顧客の数 ÷ 全体の回答数 × 100] | 特定のプロダクトやインタラクションに対する満足度スコア(例:5段階評価)、満足と回答した顧客の割合 |
| CES(Customer Effort Score) | 顧客が特定の問題解決やタスク完了のために「どれくらいの労力を要したか」を測る指標 | 5~7段階で得られた回答結果について、上位2区分の回答割合から下位3区分の回答割合を引いて算出する | 特定の問題解決やタスク完了にかかった労力スコア、次回も利用したいと回答した顧客の割合 |
| CRR(Customer Retention Rate) | ある期間内に企業が既存顧客をどれだけ維持できたかを示す指標 | [期間終了時の顧客数 - 期間中の新規顧客数 ÷ 期間開始時の顧客数] | 特定期間における顧客維持率、解約率(チャーンレート)、リピート購入率、顧客LTV(Life Time Value) |
顧客満足度の向上に適したKPIを設定するためには、事業や施策の目標を明確にし、その目標達成に貢献する「指標」を特定することが重要です。指標は事業の状態や成果を測るための広範な尺度であり、KPIの土台となるものです。
仮説や指標を立てずにKPIを設定すると闇雲に目標を追うことになりかねません。顧客満足度向上に向けた具体的な道筋を明確にするためには、顧客の課題やニーズに対して具体的な仮説を立て、その有効性を正しく検証できる指標に則してKPIを選択する必要があります。
たとえば、顧客満足度の低さに対して「サポートの対応時間が長いからではないか」といった仮説を立てたとすると、顧客の労力を測るCES(Customer Effort Score)を指標として「平均サポート対応時間」や「初回解決率」などの具体的なKPIが測定でき、仮説の有効性を検証することができます。
また、顧客満足度向上に向けた具体的な施策を立案する際にも仮説は重要な役割を果たします。たとえば、「Webサイトの使いにくさが顧客満足度を下げているかもしれない」という仮説にはUI/UXの改善やA/Bテストの実施といった施策を検討でき、「サイト滞在時間」や「ページビュー数」などのKPIを測定することで施策の効果を評価することができます。
このように、仮説に基づいてKPIを設定することで何を改善すれば目標達成に繋がるのかが明確になり、効率的なアクションプランを立てられるようになります。KPIの詳細は「NPSとはどんな指標?顧客満足度との違いや測定方法を解説」や「カスタマーサクセスで重視される12のKPIと設定の手順を解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
④カスタマージャーニーを最適化する
カスタマージャーニーを最適化すると顧客の感情や要求をより深く理解でき、顧客体験(CX)の向上に繋がります。カスタマージャーニーとは顧客が自社のプロダクトと接する一連のプロセスを指し、個々の接点において顧客のニーズに合致したアプローチを可能にします。
カスタマージャーニー全体を俯瞰的に捉えることで顧客がどのような状況で何を考え、何を感じているのかを顧客の視点に立って把握できるようになります。各タッチポイントで顧客が求めているものを正確に捉え、顧客満足度の向上を図りましょう。
| 方法 | 詳細 | 具体例 | 効果 |
|---|---|---|---|
| データ駆動型のインサイト | 解析ツール、CRM、SFA、MAなどを活用し、顧客データを一元管理・分析する | 顧客の購買履歴やウェブサイト閲覧データから傾向を分析する | 顧客のニーズを正確に把握し、最適なアプローチを特定できる |
| パーソナライズされた顧客体験 | 顧客の行動履歴や属性に基づいて関連性の高い情報やサービスを提供する | キャンペーンメール、動的コンテンツ、レコメンデーション、個別のプロダクト提案など | 顧客満足度の向上、購買意欲の促進、リピート率の増加 |
| オムニチャネル戦略 | 複数のチャネル(オンライン・オフライン)を統合し、顧客に一貫性のあるシームレスな体験を提供する | オンラインストアで購入した商品を実店舗で受け取れるサービス | 顧客の利便性向上、チャネル間の連携強化、顧客エンゲージメントの深化 |
| 顧客サポートの強化 | ケイパビリティ(企業全体の組織力)を高め、問題解決の迅速化とサポート体制の強化を図る | FAQの充実、チャットボット導入、24時間対応コールセンター | 顧客からの問い合わせへの迅速な対応、問題解決率の向上、ブランドロイヤルティの構築 |
| フィードバックの活用と継続的な改善 | 顧客からのフィードバックを積極的に収集し、プロダクトの改善に繋げる | アンケート調査、レビュー機能、SNSでの顧客の声のモニタリング | プロダクトやサービスの品質向上、顧客の期待値とのギャップ解消、顧客満足度の持続的な向上 |
カスタマージャーニーの最適化においては、それぞれの方法を相互に連携させることでより効果を発揮します。たとえば、データ駆動型のインサイトによって顧客のニーズを深く理解し、そのインサイトに基づいてパーソナライズされた顧客体験を提供することで顧客のエンゲージメントを効率良く高めることができます。
さらに、オンラインとオフラインのチャネルを統合するオムニチャネル戦略を展開することで顧客はどのチャネルを利用しても一貫性のあるシームレスな体験を得ることができ、利便性が向上します。
顧客サポートの強化は顧客が問題に直面した際に迅速かつ的確に対応できることが重要なため、チャットボットや充実したFAQを導入して顧客自身で問題を解決できる機会を提供しながら複雑な問い合わせには専門の担当者が迅速に対応できる体制を整えます。
そして、これらの取り組みを通じて得られたフィードバックを継続的に活用し、改善を繰り返すことでプロダクトの質を常に高め、顧客満足度を最大化することができます。このように各要素が連携し合うことで顧客はよりスムーズで満足度の高い体験を得られるようになり、結果として企業へのロイヤルティも向上していくことが期待できます。
なお、カスタマージャーニーの詳細は「カスタマージャーニーとは?マップの作り方や注意点を解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
⑤顧客視点に立って施策を実行する
顧客満足度の向上においては、顧客の深層にあるニーズや価値観を理解する「顧客視点」が基盤となります。顧客視点とは、製品、サービス、企業活動の全てを顧客の立場から捉え、顧客が何を求めているか、どのような体験を欲しているかを深く理解することです。
顧客が抱える潜在的な不満や期待を先回りして察知し、解決策や付加価値を検討していくことで顧客にとっての本当の価値が提供できるようになります。顧客視点を持つことは顧客満足度の向上に加え、顧客ロイヤルティの向上や競争優位性の確立にも繋がります。
| 区分 | ポイント | 詳細 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 顧客理解の深化 | 顧客の真のニーズを掘り下げる | 表面的な要望だけでなく、その背景にある根本的な欲求や目的を深く理解する | 顧客が本当に求めている価値を提供できるようになり、プロダクトの満足度が向上すると共に、顧客ロイヤルティが強化され、長期的な関係構築に繋がる |
| 顧客のインサイトを正確に捉える | 顧客自身も意識していないような購買行動や意思決定に影響を与える隠れた動機・感情を洞察する | 顧客の期待を上回る体験を提供することで競合との差別化が図れ、顧客の企業への信頼感が深まる | |
| 期待値を超える付加価値を考える | 顧客が期待するレベルを超え、驚きや感動を与えるようなプロダクトの付加価値を創出する | 顧客の期待値を上回ることで口コミや紹介による新規顧客獲得にも繋がり、顧客は期待以上の価値に喜びを感じ、企業へのエンゲージメントが高まる | |
| 顧客との共感 | 顧客体験を共有する | 実際に顧客と同じ立場でプロダクトを利用してみることで顧客が感じるであろう不便さや喜びを肌で感じる | 共感を通じて顧客との信頼関係を築き、顧客は企業に対して親近感を覚えるようになることでより効果的なソリューションが提供できる |
| 顧客の声に耳を傾け、その感情を想像する | 直接的・間接的な声の全てに注意を払い、言葉の裏にある感情や意図を想像する | 顧客の不満や課題を迅速に解決できるようになり、顧客は自分の声が反映されていると感じ、企業への信頼感とロイヤルティを深める | |
| 顧客の課題を自分事として捉える | 顧客が抱える課題を自分自身の問題であるかのように真剣に考え、解決策を探す | 顧客は単なる取引相手ではなく真のパートナーとして企業を認識するようになり、長期的な関係構築と企業としての存在意義向上に繋がる | |
| 顧客中心の意思決定 | 顧客にとってどうかを常に問う | 意思決定を行う際に短期的な利益だけでなく、顧客への長期的な価値提供を重視する | 顧客のニーズと期待に合致したプロダクトを提供できるようになり、顧客満足度とロイヤルティが向上する |
| 顧客が得られる価値を明確に言語化する | プロダクトが顧客にもたらすメリットや恩恵を具体的かつ分かりやすい言葉で伝える | 顧客はプロダクトの価値を明確に理解した上で安心して購入・利用できるようになる | |
| 顧客の成功にコミットする | 顧客がプロダクトを通じて目標を達成したり、問題を解決したりできるよう積極的にサポートし、長期的なパートナーシップを築く | 顧客は企業に対して強い信頼と感謝を抱き、長期顧客となるほか、企業のブランドイメージ向上によって新規顧客獲得の好循環が生まれる |
顧客視点において重要なのは、プロダクトを提供する側ではなく実際に利用する顧客の立場に身を置いて物事を考え、判断する姿勢です。顧客の視点から捉えることでこれまで気づかなかった課題や顧客が本当に求めている価値を発見できるようになります。
顧客視点を組織全体に醸成していくためには、顧客との直接的な接点を増やすことが不可欠です。コールセンターの問い合わせを傾聴したり、営業担当者からのフィードバックを共有したりするだけでなく、実際にユーザーと同じようにプロダクトを使ってみることで顧客が直面する細かな不便さや潜在的なニーズを肌で感じることができます。
また、顧客にプロダクトの価値を明確に伝える手段として、FAB分析などのフレームワークを活用することも有効です。FAB分析は「特徴(Features)」「利点(Advantages)」「顧客便益(Benefits)」の3つの要素からプロダクトの価値を分析する手法で、プロダクトの単なる機能紹介に留まらず、顧客にとっての価値を深く理解してもらいやすくなります。
ただし、顧客視点を持つ上では注意すべき点もあります。特に気を付けなければならないのは「顧客の声を鵜呑みにしないこと」です。顧客が口にする要望は必ずしも真のニーズではない可能性があり、その背景にある感情や動機を深く掘り下げる必要があります。
また、特定の顧客の声に影響されすぎず、多様な顧客層の声をバランス良く聞くことも大切です。特定の顧客に傾倒しすぎると他の顧客層のニーズを見落とす可能性があることから、広範な意見を多角的な視点から分析することが大切です。
顧客視点は一度身につければ終わりではありません。市場環境や顧客の価値観は常に変化するため、継続的に顧客理解を深化させ、顧客視点をアップデートしましょう。なお、顧客の成功を起点とした経営戦略は「カスタマーレッドグロース(顧客起点経営)とは?実践方法や手法例を解説」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
⑥業務改善のフレームワークを活用する
業務改善のフレームワークを活用すると顧客満足度を効率的かつ効果的に高められます。代表的なフレームワークには「PDCAサイクル」「OODAループ」「PDRサイクル」があり、それぞれの異なる特性を理解して状況に応じて使い分けることが重要です。
また、顧客満足度向上の取り組みは一度で終わりではなく、常に変化する市場や顧客のニーズに対応し続ける必要があります。業務改善のフレームワークを実践し続けることで常に最新の状況に合わせて最適な顧客体験を提供し、持続的な顧客満足度の向上を実現しましょう。
| 区分 | PDCAサイクル (Plan-Do-Check-Act) | OODAループ (Observe-Orient-Decide-Act) | PDRサイクル (Prep-Do-Review) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 業務の継続的な改善、品質管理、プロセスの標準化 | 刻々と変化する状況下での迅速な意思決定と行動 | 素早い改善の積み重ね、個人や小規模なタスクの効率化 |
| 実行速度 | 比較的慎重で時間がかかる(中長期的な改善) | 非常に迅速(数秒〜数分で回す場合もある) | 比較的迅速(PDCAより速い) |
| 注意点 | ・計画に時間をかけすぎると実行が遅れる ・変化への対応が遅れる可能性がある ・形骸化しやすい | ・計画性がないと場当たり的になる ・熟練者の経験や直感が重要になる場合がある | ・準備が不十分だと効果が出にくい ・大きな組織や複雑なプロセスには不向きな場合がある |
PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act:計画・実行・評価・改善)は、比較的安定した環境下で計画に基づいた継続的な改善を目指す場合に適しています。たとえば、定型業務の効率化や品質管理など、着実に効果を積み上げていきたい場面でその効果を発揮します。
一方、OODAループ(Observe-Orient-Decide-Act:観察・状況判断・意思決定・実行)は、不確実性の高い状況や緊急性の高い意思決定が求められる場合に有効です。市場の変化が激しい現代において競合他社の動向や顧客ニーズの急変に迅速に対応し、即座に行動を修正していく必要がある場合に特に効果を発揮します。
PDRサイクル(Prep-Do-Review:準備・実行・評価)は、PDCAサイクルよりも評価・改善のフェーズを簡素化し、迅速な試行錯誤を繰り返すことを重視するフレームワークです。新規事業開発やアジャイル開発など、スピード感を持ってアイデアを具体化し、市場の反応を見ながら柔軟に軌道修正していく場面に適しています。
これらのフレームワークを効果的に回すためには、意思決定の概念である「トップダウン」と「ボトムアップ」を戦略的に使い分けることが重要です。
トップダウンは組織の上層部(トップ)が決定した方針や指示を下位層(ボトム)に伝える意思決定スタイルで、組織全体の進むべき方向性を統一します。一方、ボトムアップは現場の従業員からアイデアや意見を吸い上げ、それを基に意思決定を行うスタイルであり、現場の実情に即した改善活動を進められます。
さらに、迅速な意思決定と現場の活力を両立させたい場合は「トップダウンデモクラシー」があります。これは、トップダウンとボトムアップの両方の利点を組み合わせたスタイルで現場の声を集めながらトップ主導による意思決定を可能にします。
このように、業務改善のフレームワークと意思決定スタイルを状況に応じて組み合わせるとそれぞれの機能がより実効性を持つようになります。フェーズごとに最適な方法を選択し、組織全体の連携を強化しながら顧客満足度向上への取り組みを加速していきましょう。
顧客満足度向上のポイント
顧客満足度向上のポイントは顧客のニーズに合致した最適なソリューションを提供することです。一般的にBtoCビジネスでは個人の感情や短期的な満足度が重視されますが、BtoBビジネスでは企業の事業目標達成に貢献できるかが重視され、アプローチが異なります。
特にBtoBビジネスの対象顧客は個人的な感情よりも企業の目標達成や利益向上に繋がる合理的な判断に基づいてプロダクトを選定する傾向があります。単に高品質な製品や優れたサービスを提供するだけでは不十分な場合があるため、顧客満足度向上のポイントを実践して企業の対応力を高めていきましょう。
【顧客満足度向上のポイント】
- ITツールを導入して顧客サポートを強化する
- 品質マネジメント(QM)を通じてプロダクト品質を高める
- 従業員満足度(ES)を上げる
- 企業の社会的責任(CSR)を果たしてブランド価値を高める
ITツールを導入して顧客サポートを強化する
顧客満足度の向上にITツールを導入することは有効な手段の一つです。ITツールを適切に導入して活用することで業務効率化、顧客対応品質の改善、顧客理解の深化が促進され、顧客サポートの強化に繋がります。
従来の電話やメールでの顧客対応には限界があり、顧客満足度向上に向けた積極的なアプローチが難しい側面がありました。一方、ITツールが普及した現代のビジネス環境では顧客との接点が多様化し、適切なツールを活用することで迅速かつパーソナルな対応が実現可能となっています。
| ITツール | 活用事例 | 施策例 |
|---|---|---|
| CRM×メール配信ツール | CRMに蓄積された顧客情報を活用し、顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた情報を提供する | ・導入サービスの活用支援メール ・セミナー・イベントの個別案内 ・契約更新前のフォローアップ |
| メール共有・管理システム×チャットボット | 顧客からの問い合わせに迅速かつ的確に対応し、サポートの効率化と品質向上を実現する | ・FAQの強化とチャットボット連携 ・問い合わせ履歴の一元管理 ・担当者情報と連携した自動応答 |
| CRM×アンケート作成ツール | 顧客の生の声を定期的に収集し、サービス改善に繋げる | ・オンボーディング後の満足度調査 ・定期的なNPS調査 ・機能追加・改善に関する意見募集 |
顧客満足度向上に適したITツールを導入すると、時間の制約に囚われず、顧客一人ひとりの購買履歴や問い合わせ履歴に基づいたパーソナルな情報提供が可能になります。
たとえば、CRM(顧客管理システム)を導入すると顧客情報の一元管理が可能になります。過去のやり取りや購入履歴、好みなどを瞬時に把握し、顧客に合わせた的確な提案やサポートを提供することで顧客は自身に対する理解度の深さを実感し、プロダクトや企業に対して信頼感を高めやすくなります。
また、チャットボットをWebサイトに導入した場合は、24時間体制でよくある質問に即座に回答でき、顧客の待ち時間を削減できます。複雑な問い合わせに対してはオペレーターにスムーズに引き継ぐことで顧客はストレスなく問題解決へと進めます。
さらに、アンケート作成ツールを使って顧客からのフィードバックを定期的に収集すると、顧客の声をサービス改善に活用できます。顧客は企業が自分たちの意見を真摯に受け止めていると感じ、満足度を高める効果が期待でき、企業の競争力強化にも貢献できるでしょう。
なお、CRMの詳細は下記のリンクで説明していますので、是非参考にしてみてください。
「CRMとは?営業業務改善ができる主な機能と導入メリットをご紹介」
「SFAとは?CRMとの違いと導入までの注意点、有効活用するための方法」
目標や施策に適したフレームワークを活用する
目標や施策に適したフレームワークを活用すると顧客満足度を効率的かつ効果的に高めることができます。顧客満足度向上に寄与するフレームワークは現状分析から課題特定、具体的な施策立案までの一連の流れを構造化し、体系的なアプローチを可能にします。
| フレームワーク | 概要 |
|---|---|
| SWOT分析 | 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を把握し、戦略立案に活かす |
| 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場との関係性を理解し、成功要因を見つけ出す |
| SMARTの原則 | 目標を「Specific(具体的に)」「Measurable(測定可能に)」「Achievable(達成可能に)」「Relevant(関連性のある)」「Time-bound(期限を定めて)」設定することで、より具体的で達成しやすい目標を立てる |
| 成功循環モデル | グッドサイクルを回してチームや組織が良好な関係性を築くことで思考、行動、結果が良い方向に循環し、生産性やパフォーマンスが向上するモデル |
顧客満足度向上のフレームワークは、複数を組み合わせることでより多角的なアプローチが実現します。たとえば、初めにSWOT分析で自社の強みと弱みを把握した後で、3C分析を活用して市場の状況と顧客のニーズを深く理解します。すると、自社がどこに注力すべきか、どのような戦略が有効かが明確に把握できます。
次に、分析結果に基づいてSMARTの原則を活用し、具体的な顧客満足度向上の目標を設定します。目標は具体的(Specific)で測定可能(Measurable)であり、達成可能(Achievable)で関連性があり(Relevant)、期限が明確(Time-bound)であるように策定することが前提です。これにより、目標達成に向けた進捗を明確に把握し、効果的なPDCAサイクルを回せるようになります。
そして、目標達成に向けて施策を実行する際には、成功循環モデルを活用します。このモデルは、関係性の質、思考の質、行動の質、結果の質という4つの要素が相互に影響し合うことで組織全体のパフォーマンスを向上させることを目指します。関係者間の良好なコミュニケーションと相互理解を促進して組織全体にポジティブなサイクルを生み、継続的な顧客満足度向上に繋げます。
なお、営業戦略の実践的なフレームワークは「営業戦略で活用できるフレームワーク10選と活用メリットを紹介!」で説明していますので、是非参考にしてみてください。
品質マネジメント(QM)を通じてプロダクト品質を高める
品質マネジメント(QM)を通じてプロダクト品質を高めると顧客体験が改善され、顧客の期待値との合致や信頼性の向上に繋がります。品質マネジメント(Quality Management)とは品質に関わる機能全般を管理するための活動体系のことです。
品質マネジメントはプロダクトの品質を一定水準に保つための品質管理(Quality Control)とプロダクトの品質が確実に保証されていることを客観的に示す品質保証(Quality Assurance)の考え方を含み、製品自体の品質だけでなく品質向上や品質保証に関する取り組みを包括しています。
品質マネジメントを効果的に実施するために、国際標準化機構(International Organization for Standardization)は「品質マネジメント7原則」を提唱しています。7原則は組織が顧客満足度を高めて継続的に改善していくための指針となる基本的原則を示すもので「ISO9001」をはじめとする品質マネジメントシステム規格の基礎となっています。
| 原則 | 概要 |
|---|---|
| ①顧客重視 (Customer focus) | ・顧客のニーズを深く理解し、期待値を超えることを目指す ・顧客の期待するQCD(品質・価格・納期)を満たし続ける |
| ②リーダーシップ (Leadership) | ・リーダーは組織の目的と方向性を確立し、目標達成に導く ・共通の目的意識を持って組織全体の品質への意識を高める |
| ③人々の積極的参加 (Engagement of people) | ・改善活動における人々の参画を拡大する ・個人のスキルを最大限に発揮できるよう組織体制を強化する |
| ④プロセスアプローチ (Process approach) | ・改善活動を相互に関連するプロセスとして理解する ・各プロセスの役割や課題を明確にし、体系的に管理する |
| ⑤改善 (Improvement) | ・組織は常に顧客満足を追求し、最良の改善を続ける ・環境や状態の変化に反応し、継続して最適化していく |
| ⑥客観的事実に基づく意思決定 (Evidence-based decision making) | ・データと情報を分析し、客観的事実に基づいて意思決定する ・確かな根拠の基でマネジメントシステムを改善する |
| ⑦関係性管理 (Relationship management) | ・持続的成功のために組織は利害関係者(ステークホルダー)との良好な関係を管理する ・両者は対等で平等であるという考え方のもと、双方向のコミュニケーションを維持する |
品質マネジメント7原則を顧客満足度向上に活用するためには、それぞれの原則を具体的な施策に落とし込み、組織全体で実践する必要があります。たとえば「顧客重視」の原則に従って顧客の期待するQCD(品質・価格・納期)を満たすには、アンケート調査や顧客インタビュー、SNS上の意見などを収集し、顧客の声を積極的にプロダクト開発に反映します。
「リーダーシップ」の原則では、経営層が打ち出した品質へのコミットメントを組織全体に浸透させることが重要です。品質目標を明確に設定し、達成に向けたリソース配分や方針決定を行うことで顧客が享受するプロダクト品質を安定させ、信頼性の向上に繋げます。
「人々の積極的参加」の原則は、従業員一人ひとりが品質向上の担い手であるという意識を醸成します。従業員の教育訓練を強化し、品質に関する知識やスキルの向上に加え、改善提案を奨励する仕組みを導入することで各々が顧客視点に立ったサポートを自律的に考え、実行できるようになります。
「プロセスアプローチ」の原則では製品開発からアフターサービスまでの一連の活動を効率的かつ効果的なプロセスとして捉え、「改善」の原則に従って定期的にシステムの有効性を評価し、問題点を見つけ出します。そして、「客観的事実に基づく意思決定」によって問題の根本原因を特定し、効果的な対策を実行することで継続的なパフォーマンスの向上を目指します。
最後に「関係性管理」の原則では、サプライヤーやパートナーなどの利害関係者(ステークホルダー)との良好な関係構築が重視されます。利害関係者との連携を強化し、共通の品質目標を設定することでサプライチェーン(供給連鎖)全体の品質向上が期待できます。
このように、品質マネジメントを導入すると顧客ニーズへの適合や不具合の削減、パフォーマンスの向上などが図れ、顧客の期待を超える価値を提供できるようになります。さらに、顧客ロイヤルティの基盤が構築され、ブランドに対する信頼感の醸成も実現するため、結果として顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
従業員満足度(ES)を上げる
従業員満足度(ES)を上げると顧客満足度(CS)も高まる傾向にあります。これは「サービス・プロフィット・チェーン」の理論に基づくもので、「従業員満足」「顧客満足」「企業収益」の3つがそれぞれ相関関係にあり、良い循環を生み出すという考え方です。
しかし、近年の日本の従業員エンゲージメントはわずか6%に留まり、世界で最もエンゲージメントの低い国の一つとなっています。これは多くの日本企業において従業員が仕事に対して積極的に関与し、情熱を持って取り組む姿勢が不足していることを示しています。
企業が持続的に顧客満足度を高め、競争力を維持し続けるには、従業員エンゲージメントの低下を是正し、従業員満足度を上げるための取り組みが急務であるといえます。従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる仕組みを構築し、顧客のために存分に尽くせる環境を整えましょう。
| 取り組み | 概要 |
|---|---|
| 明確なビジョンの共有と浸透 | 具体的な行動への落とし込み、多角的な発信と対話、リーダーによる体現 |
| 情報の透明性向上 | 経営状況の共有、意思決定プロセスの可視化、オープンなコミュニケーション文化の醸成 |
| 社員や顧客とのタッチポイントの重視 | 定期的なフィードバックと対話、顧客の声の共有と活用、社内イベントや交流の促進 |
| 福利厚生の充実と柔軟な働き方の推進 | 多様なニーズに対応した福利厚生、柔軟な働き方の導入、キャリア開発支援 |
従業員満足度を上げるためには明確なビジョンの共有と浸透が不可欠です。経営層がビジョンを多角的に発信して浸透させ、リーダーが率先して体現することで従業員はより具体的なイメージを持つことができます。これにより、従業員は単なる作業者ではなくビジョン達成の一翼を担う重要な存在として、仕事に誇りとやりがいを感じられるようになります。
この考え方は「バリュー・プロフィット・チェーン」の理論にも通じています。企業が提供する価値の源泉は従業員にあり、その従業員が顧客価値を創造することで利益が生まれるという考え方で、実質的にはサービス・プロフィット・チェーンと同様の概念です。
そして、情報の透明性を向上させる取り組みも従業員エンゲージメントの向上に欠かせません。経営状況や意思決定プロセスをオープンにすると従業員は会社の現状を自分ごととして捉えやすくなり、当事者意識を持って業務に従事できます。従業員が安心して意見を述べられる職場環境を構築することで、建設的な議論を通じてより良い組織作りに貢献しようという意欲が生まれるでしょう。
また、社員や顧客とのタッチポイントを重視すると従業員が自身の仕事の価値を実感し、顧客満足度への貢献を認識しやすくなります。定期的なフィードバックと対話の機会を設け、従業員が成長を実感できる場を提供することも有効です。さらに、顧客からの感謝の声や改善要望などはサービス提供へのモチベーションを高め、社内イベントや交流の促進によって従業員間の協力体制の強化が期待できます。
最後に、福利厚生の充実と柔軟な働き方の推進は、従業員が安心して長く働き続けられる環境を整備するために不可欠です。多様なライフスタイルや価値観を持つ従業員に対応できるよう選択肢の多い福利厚生を提供し、ワークライフバランスを重視した柔軟な働き方を導入することが求められます。
たとえば、リモートワーク、フレックスタイム制、育児・介護支援制度などを充実させることで従業員は自身の状況に合わせて働き方を選択でき、仕事とプライベートの調和を図ることが可能になります。加えて、キャリア開発支援を積極的に行うことで従業員のスキルアップやキャリアパスを促進し、結果として個人の成長と組織への定着に繋がります。
従業員が自身の成長と将来への展望を描きやすくなるようサポートしながら従業員満足度を高め、企業へのエンゲージメント向上を図りましょう。
企業の社会的責任(CSR)を果たしてブランド価値を高める
企業の社会的責任(CSR)を果たすと顧客や社会からの信頼と共感を得やすくなり、プロダクトや企業全体のブランド価値が高まります。
企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)とは、企業活動に対して利益追求だけでなく環境や次世代への配慮を実践し、顧客、従業員、地域社会などの様々なステークホルダーに対して責任ある行動を取り、持続可能な社会の実現に貢献する考え方のことです。
国際標準化機構(International Organization for Standardization)は企業や団体がCSRを果たすための国際規格として「ISO26000」を定めています。ISO26000にはCSRの基本的概念である「7つの原則」と具体的な行動の枠組みである「7つの中核主題」が含まれ、組織が社会的責任を果たしていくためのガイドラインとして活用されています。
| 7つの原則(基本概念) | 7つの中核主題(具体的な行動の枠組み) |
|---|---|
| 1.説明責任 | 1. 組織統治 |
| 2.透明性 | 2. 人権 |
| 3.倫理的行動 | 3. 労働慣行 |
| 4.利害関係者の利益を尊重 | 4. 環境 |
| 5.法規制の遵守 | 5. 公正な事業慣行 |
| 6.国際規範の尊重 | 6. 消費者課題 |
| 7.人権の尊重 | 7. コミュニティへの参画及び発展 |
ISO26000に沿ったCSRの取り組みは企業の透明性や信頼性を高め、顧客を含むあらゆるステークホルダーからの評価を向上させる効果が期待できます。
具体的な取り組みとしては「公正な事業慣行」に基づいてプロダクトの安全性や品質に関する情報公開を徹底し、「消費者課題」に対して誠実な対応を心がけ、「人権」と「労働慣行」の原則を尊重した事業活動によって顧客が安心してプロダクトを選択できる環境を構築します。
これに加え、企業の意思決定と説明責任の基盤となる「組織統治」を確立し、事業活動が環境に与える影響を最小限に抑えるための「環境」保全に努めます。さらに、地域社会との良好な関係を築き、その持続的な発展に貢献する「コミュニティへの参画及び発展」にも積極的に取り組みます。
こうした取り組みは企業のブランド価値を高めるだけでなく顧客ロイヤルティの向上にも直結します。社会貢献に積極的な企業姿勢は消費者が企業を選ぶ上で重視する要素の一つであり、共感を呼ぶことで顧客はプロダクトを利用し続け、友人や家族にも推奨する可能性が高まるためです。
さらに、これらのCSR活動を具体的な成果として顧客に分かりやすく伝えることで顧客の信頼とエンゲージメントをより一層深めることができます。たとえば、プロダクトの製造過程における環境負荷低減への貢献度やサプライチェーンにおける人権配慮の状況をウェブサイトや報告書で公開することで顧客は企業の真摯な姿勢を具体的に認識しやすくなります。
また、顧客からのフィードバックをCSR活動に積極的に反映すると顧客は自身の声が企業に届いていると感じ、企業への愛着を深めやすくなります。「7つの原則」と「7つの中核主題」を事業活動に組み込み、効果的にCSRを推進しながら企業の社会的価値を最大化していきましょう。
まとめ
顧客満足度(CS)の向上は、現代ビジネスにおいて企業の持続的成長に必要です。新規顧客獲得が困難な中、既存顧客の離反防止とLTV(顧客生涯価値)最大化のため、顧客ロイヤルティや顧客エンゲージメントの向上が求められています。
顧客満足度向上のための具体的な取り組みとしては、現状把握のための調査から仮説設定、KPI設定、カスタマージャーニーの最適化、顧客視点での施策実行、そしてPDCAなどの業務改善フレームワーク活用による継続的な改善が重要です。
また、顧客満足度の向上には、ITツール導入による顧客サポート強化やSWOT分析などの適切なフレームワークの活用、プロダクト品質向上、従業員満足度(ES)、ブランド価値向上なども重要です。
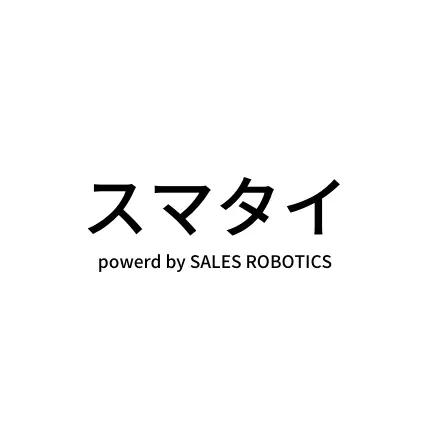
不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。
イベント・セミナー
現在受付中のセミナー・イベントはありません。
オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中
インサイドセールス支援のサービスについて知る